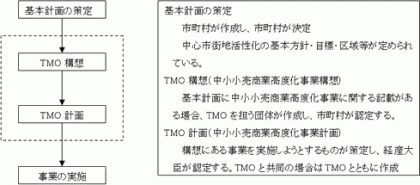Thesis
介護保険の現場から その2 特養研修
先月に引き続き、今月は、特別養護老人ホーム(以下、特養)での研修について報告する。これら一連の研修を通して、介護保険について疑問に思ったこと、高齢社会に対して思ったことを書いていきたい。
構成は、2部構成とする。内容は以下のとおり。
1部:研修体験として、特養「花みさき」での6日間の研修内容について
2部:研修を通して感じたことや、介護保険について疑問に思ったことについて
◆介護保険の現場体験報告
<特別養護老人ホーム花みさきでの研修>
5月29日(水)~6月3日(月)までの6日間、神戸のウイングスタジアムから歩いて1分の特別養護老人ホーム「花みさき」にて研修を行った(具体的な時間の流れについては下記の添付資料参照)。
(1)特別養護老人ホーム
介護保険制度において、提供される施設サービスのひとつ。常に介護が必要で自宅での生活が困難な寝たきり、痴呆性のおとしよりを介護する施設である(神戸市の介護保険のパンフレットより)。
(2)施設概要
2F:デイサービスとショートステイと一部が特養、3F:特養となっている。定員は、デイサービス(1日40名)、ショートステイ(20名)、特養(50名)となっている。デイサービス・ショートステイともに在宅の高齢者に対する介護サービスである。
※デイサービス(通所介護)・・・デイサービスセンターなどに通い、入浴・食事の提供、機能訓練などを受けるサービス
※ショートステイ(短期入所生活介護)・・・特別養護老人ホームなどに短期間入所し、介護や日常生活の世話を受けるサービス
(神戸市の介護保険のパンフレットより)
(3)研修概要
6日間の研修の概要は以下のとおり ※SSはショートステイ研修場所 研修時間
|
資料 花みさき 研修スケジュール(PDF版 120KB)
(4)研修詳細
老人保健施設での研修と同様、まだこれといった介護技術を身に付けているわけではないので、簡単なことしか手伝えず、むしろ職員の足をひっぱったような気もしたが、自分の研修内容を書いてゆきたい(具体的な時間の流れについては上記の添付資料参照)。
「花みさき」は、神戸市の中心街、三ノ宮から15分くらいで行くことができる。街中にある特養であり、園長も積極的に実習を受け入れる人であるので、毎日多くの実習生がやってくる。私が研修をしている期間でも毎日3~7人くらいの人たちが実習を行っていた(多いときは10人を超える)。
<デイサービスでの研修>
一日目(水):8:40~17:00
午前
8:40からケアマネージャーから「花みさき」での6日間の研修についての説明を受ける。9時前に3Fに上がり、毎日の職員のミーティングに研修生達とともに参加する。
ミーティングで伝えられる事項は以下のとおり
- 当日の入所者数と退所者数
- 昨日の入浴状況
- 昨日のレクリエーションの実施内容
- 個人別に排便、排尿の状況(便秘が長い場合(3日を目安)には浣腸をして排便を促すことも)
- 個人別の食事量、薬の飲み具合
- 個人別の健康状態(発熱・血圧・睡眠状態など)
- 実習生の研修先、担当者発表
- その他特記事項(散髪サービス、体重測定など)
ミーティング終了後、研修の挨拶もかねて1Fの在宅介護支援センターのミーティングに参加する。10:15ごろに2Fのデイサービスに向かう。すでに多くのデイサービス利用者がやってきている。職員に挨拶をした後、さっそく「おはようございます」の挨拶をしながら利用者の血圧と体温計測の手伝いを行う。
10:25頃から、朝の会が始まる。司会役の職員が利用者一人一人にマイクを向ける。向けられた利用者は名前を言って、場合によっては感じたことや、挨拶をしたりしていた。利用者全員が終わったら、司会者・職員の紹介があり、そして実習生として私も自己紹介を行った。その後は、ラジオ体操をし、軽快な音楽とともにリハビリ体操を行って、朝の会終了となった。
終了後は、レクリエーションをしながら、順次入浴していく。レクリエーションは、5~6テーブルに分かれて貼り絵や塗り絵をする。私もいろいろなテーブルを渡り歩きながら、利用者とともに貼り絵に取り組んだ。入浴終わった利用者も三々五々に戻ってきて、レクリエーションに加わっていく。職員の大半は入浴介助に向かい、レクリエーションにはそれほど多くの職員はいない。11:30前くらいに片付けをし、昼食の準備(お茶・オシボリを配る)に入る。
※食事は、糖尿病等の病気や、アレルギー、刻んであるもの(きざみ)、さらに刻んであるもの(極きざみ)や、ペースト状になっているものに分かれている。利用者のネームプレートに指定内容(たとえば、糖尿食など)が書かれているので、それに従って、配膳を行う。
12:00に昼食となる。12:30まで利用者の食事振りを観察しながら、12:30~13:30まで休憩時間ということで私も食事を摂った。
※「花みさき」でも、先月の老健施設のエスペランサと同様、食事ごとに食事量のチェックを行っている。基本的に栄養補給は3度の食事のみなので、食事量の管理を行っているようだ。
午後
昼食後は、入浴介助を行った。女性の方を脱衣所に連れて行き、着替えの補助と、上がってきた利用者の髪を乾かすことを行った。窓を開けて風を通してはいるが、とても暑く、汗だくになりながら入浴介助を行った。
入浴介助の後は、自由時間で過ごしていた男性の利用者と将棋を指した。とても強い方で結局は負けてしまったが、小学校の頃にやっていた将棋がこんなところで生かされるとはなーと思ってしまった。
15:00におやつの時間となる。おやつの前にリハビリ体操を行う。軽快な音楽とともに手足、首を動かす体操で、職員とともに見本として前に出てリハビリ体操を行った。体操終了後は日替わりのおやつを食べる。おやつはみんな楽しみらしく、あっと言う間になくなってしまう。
15:30に帰りの会を行う。朝の会と同様の感じで行われ、最後には長寿の歌(100歳まで元気に生きるという内容の歌)を歌って、一日が終了となる。
この日は、5月の誕生日の方を祝うということで、利用者2名の誕生祝を行った。ハッピーバースデーの歌を歌い、メッセージと花の贈呈を行った。利用者もうれしそうに受け取っていた。
16:00過ぎ、帰宅ということで荷物をまとめて、送迎のバスに乗る。1Fには園長・副園長をはじめとする職員が見送りに出てきていて、「さようなら」の挨拶が交し合わされる。数台の送迎車に分乗して、利用者はそれぞれ帰路についた。私もその一台に便乗させていただいた。
一人一人の家の近くまで行き、一緒に家まで送っていく。場合よっては家族の方が停車場まで迎えに来ていることもある。そんなときは利用者がとてもうれしそうに降りていく。
デイサービスの場所ではそんなに笑っていなかった人の家族の迎えを見つけると笑みを浮かべてうれしそうにする姿に、この人の家庭が良い関係にあるのだろうなと実感した。
一日目はこの送迎サービス終了とともに実習終了となった。
二日目(木):8:40~17:00
午前
今日の研修は、9時からのミーティングに参加するのではなく、デイサービスの朝のお迎えに同行することから始まった。
8名(うち3名は車椅子)の利用者を迎えに行った。送迎車で家の近くまで行き、職員とともに家まで迎えに行った。着替えを待ったり、時には家のかぎ閉めを行ったりしながら、一人一人迎えに行った。
※ここは、先月の老人保健施設「エスペランサ」と違って、迎えに行くときに前もって携帯であと10分等の連絡することをあまりしない。その理由を聞いてみると電話することで逆に焦らせてしまったりするので、電話しないとのことだった。
10時過ぎくらいに「花みさき」に到着すると、昨日の帰りと同様に園長・副園長を始めとして職員が迎えに出てくる。「おはようございます」の挨拶を交し合い、とてもにぎやかになる。私は利用者の車椅子を押しながら、2Fデイサービスへと向かっていった。
まず、それぞれの荷物を保管場所に収め、名札をつけて座席へと誘導する。その後は昨日と同様に一人一人の体温と血圧を測り、10:25ころから朝の会が行われ、レクリエーションと入浴が始まった。今日のレクリエーションは昨日の貼り絵と塗り絵に加えて、七夕用ミニチュアの笹の葉飾りを作っていた。
昨日同様、11:30頃に昼食の準備に入り、12:00に昼食となった。私も12:30~13:30まで昼休みということで昼食を摂った。
午後
昼食後、昨日と同様に入浴介助を行った。今回は、男性利用者の入浴介助で、脱衣所まで誘導し、着替えの介助、髪を乾かした。今回はさらに風呂場で利用者の体を洗い、浴槽まで誘導することをした。風呂場はさらに暑く、たった一人の体洗いだったけど、汗と風呂の湿気でずぶぬれ状態になってしまった。
入浴介助と脱衣所の掃除が終わるとすでに15時前で、おやつの時間で、汗も乾かないうちにラジオ体操をした。
今日は、NALC神戸という団体がデイサービス利用者を対象にミニ喫茶をするということだった。NALC神戸の方が利用者一人一人にコーヒー・紅茶のどちらを飲みたいのかを聞き、ケーキとともに利用者に提供されていた。
その後は、昨日同様に、15:30に帰りの会をし、16:00くらいに送迎車に分乗して帰路に着いた。私のデイサービスでの研修も終了となった。
<特養・ショートステイで研修>
三日目(金):9:00~11:30(3F特養) 18:30~20:00(花みさきミニバー)
当初の予定では三日目もデイサービスだったが、園長に同行して外出することになったので、午前中だけ特養にて研修することとなった。夜は特養・ショートステイ利用者を対象にミニバーが開かれるということで私も参加した。
特養は基本的には4人部屋だが、1人部屋に住んでいる人もいる。
午前
9:00前に3Fに行き、まずミーティングに参加した。ミーティング終了後、特養の利用者に挨拶を兼ねて話をしにいった。といっても朝食も終わって部屋に帰っている人が多く、ほんの数人しかいなかった。
9:30くらいからもう1人の実習生とともに各部屋を巡り、お茶の補給とゴミ箱のゴミの回収を行った。ゴミの回収といっても部屋に私物をそれほど多く持ち込めるわけでもないので、ゴミの量はそれほど多くなかった。
ゴミ回収後は、食堂に出てきている利用者と話をし、11:30から昼食の準備として部屋で休んでいる利用者を食堂に誘導し、オシボリとお茶を配った。2Fの特養・SS利用者も食事は3Fで摂るので、続々とエレベーターで上がってきた。
今日は、昼から園長とともに外出するために、昼食の準備で研修終了となった。
夜
夜は、2F特養・SSと3F特養の利用者を対象に月一回のミニバーが開かれるということで私も参加した。
2Fのデイサービスの場所で、職員は業務としてではなくボランティアとして利用者を歓待するために参加する。お酒やジュースを出したり、お菓子や焼き鳥を焼いて出したりと、忙しそうに利用者のテーブルを動き回っていた。私は園長とともにビールを飲みながら、焼き鳥を食べて、お客様として楽しませていただいた。途中からピアノ演奏付のカラオケタイムとなり、利用者が自分達の若かりし頃の歌を歌い、私も中学校の頃に習った記憶のある歌を歌った。
みんなとても楽しんでいるようで、ときにはこういった楽しみも必要なんだろうと思いながら、私も楽しませていただいた。
四日目(土):9:00~18:30(3F特養)
昨日のミニバーは、利用者はとても楽しんだらしく、ほとんどの人が夜はぐっすりと眠ることができたということを園長に教えてもらった。改めてこういった娯楽の重要性を確認した。
午前
三日目と同様にミーティングから始まる。ミーティング後はまず居室のシーツ交換を行った。その後は、実習生の人と居室のトイレ掃除を行うことになった。私は便器を磨き、もう1人は便器やその周りを木搾液を含ませた雑巾で拭く(消毒になるらしい)という分担で始めた。
便器を磨くのもなかなか大変なもので、10部屋分くらいあるので時間もかかり、締め切った状態でやるので終わる頃には汗びっしょりになってしまう。それでも今回は楽なほうだったらしく、場合によってはトイレの壁などに便がなすりつけられていることもあり、そうするととても大変なことになるらしい。その話を聞いていただけに少しラッキーと思ってしまった。
トイレ掃除の後は、利用者と話をし、その後、昨日と同じ手順で昼食準備に取り掛かった。
午後
13:00に3Fに戻ってくると、利用者のほとんどは食事を終えていて、部屋に戻っていた。私が3Fを歩いていると、1人部屋で話し込んでいた2人の利用者が私を部屋に招いてくれた。2人で話をしながら果物とかを食べていたらしく、私にも付き合えということで果物を分けてくれた。
しばらく話し込んだ後、14:00ごろ、午後のレクリエーションということで、部屋にいる利用者を食堂に誘導した。レクリエーションは名前ビンゴゲームだった。これは自分の名前をひらがなでかいて、職員がひらがなを書いてあるボールをひとつずつ取り出して、名前のすべてが出てきたら、ビンゴということになる。私は、10人くらいの利用者の周りをまわって、名前をひらがなで書いたり、どれが出たかを教えたりしていた。
15:00、おやつの時間となり、ラジオ体操の後、おやつとなった。おやつが終わると利用者の大半は部屋に戻っていった。
16:30、夜勤の職員に対しての申し送りが行われた。私はある利用者の湿布の張替えを依頼されたのでそれを行った。その女性は両手両足両肩にと至るところに湿布が貼られている。その女性に痛いところを聞き、貼り方を教わりながらやっていたが、手馴れていないせいでいつのまにか夕食の時間になっていたので、慌てて食堂に誘導し、夕食終了後に残りの部分の湿布を貼って、今日の研修は終了となった。
五日目(日):9:00~17:00(2F特養&ショートステイ)
<午前>
昨日同様に9:00からミーティングに参加し、その後、2Fに移動して、利用者達と話をして過ごした。
9:30から、3人の方の足浴を行った。すこし熱めのお湯を張った大きな風呂桶に足を入れてもらって温める。足浴をする利用者の足は、靴下を脱がせると、浮腫んで膨らんでいて、とても冷たく、肌の色も赤黒くなっている。15~20分くらい足をつけてもらうが、熱くなってくるらしく、途中からすぐに足を出してしまう。その出してしまう足をまた入れてもらって温まってもらうことを繰り返すと、だんだん足の血行が良くなってくるようで膨らみもなくなってきて、足の色もきれいな赤色に変わってくる。
10:30からは、午前のレクリエーションということで、2チームに分かれて、風船バレーボールを行った。バレーボールといっているが、実際のところはキャッチボールになっていた。積極的に楽しんでいる人もいれば、まったくやろうとしない人もいた。
昼食では、今回初めて食事介助を行った。ペースト状の食事をスプーンですくって食べさせることをした。しかし、その女性は話せないし、常に口が動いているので、いつスプーンを口元に運んでいいのか分からず、何回も拒否されながら、悪戦苦闘の末、どうにか食事をしてもらった。自らの介護技術のつたなさを恥じるとともに、食事介助のタイミングの難しさを知らされた。
<午後>
昼休み後、昼のレクリエーションということで黒ひげゲームを行った。しかしみんなあまりやりたがらず、外に出ることになった。外に出るのはうれしいらしく、黒ひげのときは全然やる気を見せずに眠ろうとしていた人も、起きて笑っていた。毎日を施設の中で過ごす人にとって、わずかの時間でも外に出ることができるというのは、本当にうれしいことなんだろう。
レクリエーションの後は、職員とともにおむつ交換を行った。はじめてのおむつ交換で四苦八苦したが、職員に教わり、助けられながらどうにかこなすことができた。
その後は、夕食の準備をし、夕食を配膳し終わったところで、研修終了となった。
六日目(月):9:00~17:30(3F特養)
<午前>
昨日と同様に、9:00からミーティングに参加した。ただ、違ったのは、今回はトイレ掃除を1人でやるということで、9:30からトイレ掃除に取り掛かった。今回は便器磨きだけでなく、その周りも拭くということで、前回以上に汗だくになりながら、便座にこびりついた便をふき取っていた。前回と比べてかなり大変で、正直ちょっとアンラッキーと思ってしまった。
<午後>
午後は、ボランティア団体がやってきて、利用者とともに歌を歌った。私にとっては、昭和を思い出すという内容のテレビレベルでしか聞かない歌ばかりで、なかなか歌えなかったが、利用者の多くはこの日を楽しみにしているらしく、一生懸命歌っていた。しかし、中には完全に拒否している人もいた。
おやつの後は、職員に足浴をするように言われたので、3人の利用者を風呂場に連れて行って足浴をしようとしたが、1人には完全に嫌がられてしまったので、職員と相談をして断念した。残りの2人はとても協力的で、私もお湯に使っている足をマッサージしながら話をした。血行障害で膨れ上がった足は冷たく、マッサージで圧すと奇妙なやわらかさがあって、なんともいえない感覚だった。
その後、夕食の準備をして、配膳し終わったところで研修終了となった。
◆研修を通して思ったこと・感じたこと
<在宅介護を支えるデイサービス・ショートステイについて>
在宅介護を支えるという意味で、デイサービスやショートステイの利用が大切だと実感した。上手に使えば、利用者本人を支えるだけでなく、介護する家族を支える上でも非常に有効なものである。
在宅で家にこもってしまっては、利用者は家族とヘルパーだけというとても限られた人間関係の中で過ごすことになってしまう。デイサービスに行けば、多くの利用者(同じような境遇にある人たち)と出会うことにもなり、友人ができ、新たな刺激を得ることができると思われる。
家族にとっては、旅行をしたいと思っても、だれかに頼んで旅行するのもなかなか難しい。しかし、ショートステイを使って、2・3日の間でも特養や老健のような専門施設に預かってもらえれば、誰かに任せるよりかは安心して旅行に行くこともできる。利用者もショートステイで多くの利用者(同じような境遇にある人たち)と出会い、友人ができて、新しい刺激を得ることができると思われる。実際に今回の研修で出会った利用者の中には、普段は在宅で娘さんに介護してもらっているが、その娘さんが同窓会で旅行に行くので、その間、ここに泊まりにきている(ショートスティ)ということを話してくれる人がいた。その人は利用者とも楽しそうに話をしており、利用者・家族双方にとって有意義なものだろうと思われた。
実際に見ていると私が利用者と話すよりも、利用者同士のほうが結構うまく会話があっているようで(特に、痴呆の高齢者の場合は、はたから聞いている自分にとってはよく分からないのだが、とても絶妙にかみ合っていて、笑いあったりしている)、そういった新しい人間関係を築くという意味では、在宅介護でもこういったサービスを使うのはいいのではないかと思われる。
<終のすみか、特別養護老人ホーム>
花みさきに提供していただいたデータ(詳細は下の添付資料参照)を見てわかることだが、特養は、「終の棲家」である。退所者の半数近く(48.1%)が退所の理由が死亡である。入院も含めると約4分の3となり、特養から在宅に戻るというケースはほとんどない。先月の老健施設のデータでは、退所の内訳で約4分の1が在宅で、死亡は0.5%だったことからすると、特養は人生の終着駅の一つになっているのだろう。
一施設のデータだけでは断言はできないが、先月の老健データと合わせて考えると、病院⇔老健を繰り返した後、特養に入所し、最期を迎えるという形になっているのではないかと推測される。
※介護保険導入後、多くの自治体で特養の入所待ちが増加している(神戸市・横浜市においては、導入後、導入前の3倍の入所待ちの状態)ことからも、この推測はまったく的外れのものではないであろう。
「最後」の施設ではあるが、そう呼ぶにふさわしいのかというと正直疑問に思うことがある。先月の老人保健施設と同様ではあるが、人員配置が表示上は、3(利用者):1(職員)となっているが、現実は、7(利用者):1(職員)になっているため、一人一人にサービスを完全に提供しきれないということである。
容易に想像のつくことだと思われるが、どんな状況下に置かれていても、一人の人間が一度に七人の人の面倒を見ることはとても難しい。ましてや特養の入所者は重度の要介護者(花みさきの場合、介護度数4・5の利用者が全体の約54%)であるので本当に難しい。
やはり、本当の意味での適正な人員の配置を考える必要があると思われる。今、介護保険の見直しの中で、特養は利益を上げているので、介護報酬を下げようという議論が起こっている。しかし、その利益を使って、もっと人員の適正にそれを使い、その上でも利益を上げるのなら介護報酬を下げて、介護保険料の上昇を抑えることを図るべきだと私は考える。
施設の職員は忙しそうに動き回っている。利用者の多くはかまってもらえないで、おとなしく過ごしている。そういった光景を見ていると、人員の適正化は、利用者・職員双方にとっていいことではないかと思われる。
◆研修先
今回のレポートを作成するに当たっての研修先は以下のとおり
- 特別養護老人ホーム 花みさき(神戸市)・・・特養・ショートスティ・デイサービス研修
- 第5回ヘルパー研修会(花みさき内)・・・勉強会傍聴
- COM総合福祉研究所(神戸市)・・・ホームヘルパー2級講座受講
- 民主党介護保険をよくするWT・・・会議傍聴
◆参考資料
- 神戸市の介護保険のあらまし
- 介護保険利用の手引き(神戸市)
- ホームヘルパー養成研修テキスト2級課程
- 図解雑学 介護保険(著:北田信一 ナツメ社)
海老名健太朗の論考
Thesis
-
- 2004/2/27
- 医療・福祉・介護
ノーマライゼーション社会を目指して ~これまで これから~
-
- 2004/1/29
- 思想・哲学
茅ヶ崎アロハ ~5月15日・16日はアロハマーケット~
-
- 2003/12/29
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~理想の投票所プロジェクト~
-
- 2003/11/28
- 医療・福祉・介護
少子・高齢社会のあり方 ~生涯現役社会を目指そう!~
-
- 2003/10/29
- 地域活性化
茅ヶ崎まちおこし ~茅ヶ崎スタイルとまちおこし~
-
- 2003/9/28
- 医療・福祉・介護
ユニバーサルデザインを学ぶ ~いわてUD学校 ピポ・ユニバーサルミニ駅伝~
-
- 2003/8/29
- 思想・哲学
ユニバーサルデザインって何だろう? ~「ユニバーサルデザイン体験in茅ヶ崎」を開催して~
-
- 2003/7/29
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~総務省に結果提出~
-
- 2003/6/28
- 思想・哲学
修験道 奥駆け修行記 ~日本海から太平洋まで~
-
- 2003/5/29
- 思想・哲学
茅ヶ崎TMO活動報告 ~”あい”のまち 茅ヶ崎~
-
- 2003/4/28
- 思想・哲学
ユニバーサルデザインへ(後編) ~安全と美観~
-
- 2003/3/29
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~運動から見た選挙(投票)制度の問題~
-
- 2003/2/26
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~みんなが利用できる選挙公報を~
-
- 2003/1/29
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~投票所バリアチェック10~
-
- 2002/12/29
- 経済・産業
ものづくりの現場から ~日本酒をつくる 蔵人体験~
-
- 2002/11/28
- 法律・法制度
誰もが参加できる選挙制度 ~選挙制度は違憲状態!?~
-
- 2002/10/29
- 医療・福祉・介護
ユニバーサル・デザインへ(前編) ~バリアフリーへの疑問~
-
- 2002/9/28
- 医療・福祉・介護
第6回DPI(障害者インターナショナル)世界会議札幌大会に参加して
-
- 2002/8/29
- 医療・福祉・介護
ホームヘルパー2級資格取得を通して ~だからこそ、生涯現役社会を目指そう~
-
- 2002/7/29
- 医療・福祉・介護
イーハトーブ・by・Oneself ~チャレンジド・ジャパン・フォーラム2002に参加して~
-
- 2002/6/28
- 医療・福祉・介護
バリアフリーを考える ~車椅子議員との2日間の随行から~
-
- 2002/5/29
- 医療・福祉・介護
介護保険の現場から その2 特養研修
-
- 2002/4/28
- 医療・福祉・介護
介護保険の現場から その1
-
- 2002/3/29
- 医療・福祉・介護
ノーマライゼーション社会の実現 ~すべての人が、自立し、自律でき、矜持をもつことのできる社会を目指して~
Kentaro Ebina

第22期
海老名 健太朗
えびな・けんたろう
大栄建設工業株式会社 新規事業準備室 室長
Mission
「ノーマライゼーション社会の実現」