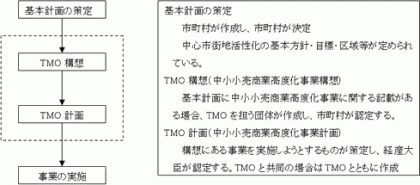Thesis
誰もが投票できる選挙を目指して! ~総務省に結果提出~
今回は、昨年の12月から取り組んでいた「投票所バリアチェック10,000ヶ所全国運動」について、集計作業も終わり、総務省に提出したので、そのことを中心に書いていきたい。
◆「投票所バリアチェック10,000ヶ所全国運動」について
まずは、この運動について説明する。
1.なぜ、この運動がはじまったのか
この運動の始まりは、前回の参議院議員選挙の前に大阪の吹田にある「共働作業所b-free」で働く車椅子使用者が20歳になり選挙権を得たことにある。
彼は、以前から車椅子使用者の先輩たちから投票するには投票所にはバリアが多いから大変だということを聞かされていた。そこで、本当にバリアが多いかを前回の参議院議員選挙のときに、吹田市内の77ヶ所の投票所において調べようということで始まった。
このときは試験的にしたこともあり、あまりうまくデータが取れなかったそうである。
私はまだこのときは、彼とも出会っていなかったので、吹田市内の投票所バリアチェックには関わっていないので、詳細についてはわからない。
2.私のかかわり
昨年秋ごろ「b-free」などの吹田市内にある障害者施設を束ねている社会福祉法人の「ぷくぷくの会」の馬垣氏から、投票所のバリアチェック運動について全国に広げたいということから一緒にやらないかという誘いを受けたのが、かかわりの始まりであった。
実は、私はこの馬垣氏と「障害者の政治参加を進めるネットワーク」にて知り合い、そのときは馬垣氏の団体で研修をさせてもらおうと考えていた。しかし、馬垣氏から研修ばかりではなく、政経塾生としてそろそろ何か形になるようなことをすべきだと強く言われ、そして誘われたのが、この運動であった。
ちょうどそのころの昨年11月、在宅のASL(筋萎縮性側索硬化症)患者が現行の公職選挙法下において選挙権が行使できないことの裁判で、現行制度が違憲であるとの判断が下された。
昨今、選挙で低投票率が問題になっており、投票に行かない人が増えているが、実は行きたくても投票制度の欠陥ゆえに棄権に追い込まれている人たちがいるのではないかと思い、馬垣氏らとともにこの運動に関わることを決め、事務局長に就任し、主に全国の団体に運動参加の呼びかけやマスコミへの取材依頼の営業等を行った。
3.運動について
この運動をする前に、もともと総務省が各選挙管理委員会に対して投票所のアクセスについて調査をしていることは知っていた。しかし、それは、有権者に投票所の場所を提供する側(総務省→各選挙管理委員会)においてチェックするものであり、必ずしもユーザー(有権者)の立場に立っているとは限らない。この運動は、有権者が投票所の利用者の立場から、投票所が利用に適した場所かを確認しようというユーザーの立場に立って展開するものである。
運動参加者は投票に際して、当運動のHPから「投票所バリアチェックシート」を持って、投票所に行き、わかる範囲は自分の目で確認し、わからないところは投票所の職員に質問をする形でチェックする。
4月13日と27日の2回行い、全国から1,300枚超のシートの回収、うち有効枚数1.000枚超のデータを全国から集めることができた。
◆集計・分析結果
1,074枚を集計し、各項目別に分析した結果について書いていく。
1.集計結果
チェック項目別の集計結果は以下の通りである。
これは、「b-free」内の集計結果HP上では、未回答も含めて集計しているので、それを排除した形で、私独自に「あり」と「ない」だけで集計しなおしたものである。
|
なお、その他の集計結果については、「共働作業所b-frre」の集計結果HPを参照
(http://www.future-net.co.jp/b-free/)
2.集計結果から
やはり、スロープは目に付いてわかるものなので、配備率は75%近くあり、全体の中ではとても進んでいる。しかし、意外だったのが、老眼鏡や拡大ルーペの配備率の低さである。高齢社会から超高齢社会へと突き進んでいくわが国において、高齢者向けのものとして、この2つの配備率が5割をきっているのは、想像できなかった。
投票所の施設としては、47.1%が小中学校であった。小中学校といえば、投票所だけに限らず災害時の避難所の役割も果たす、地域コミュニティーの拠点であるはずだが、多目的トイレの配備の低さ(34.3%)は、地域コミュニティーの役割を果たす上で非常に不安な数字である。
※阪神淡路大震災のときに、小中学校に避難したときに、体の不自由な高齢者や障害者にとって、対応できるトイレ(=多目的トイレ)がなくて困ったという話がある。
音声案内と手話通訳については、ほとんど配備されていないといっても過言ではない状態である。
すべてのものが揃っているのは、市役所ぐらいで、市役所以外の地区の投票所においては、憲法第15条がすべての有権者に保障する選挙権がかならずしも無理なく行使できる状態にはない。
ちなみに、盛岡で協力してくれた菊池亨氏は、前々回の選挙で投票所に段差があり、介助員がいるといっても、校舎の入り口で立ち往生をしていても出てきてくれなかったことがあったため、この運動までは常に盛岡市役所で不在者投票を行っていた。
◆総務省への持込み
7月末から、総務省側の都合やこちらの都合で何度も日程を調整して、政策評価広報課を通じて選挙部管理課に提出する交渉を行い、8月22日(金)に結果を門脇氏、障害当事者の代表として池田氏(車椅子使用者)、そして私の3名で持ち込んだ。
政策評価広報課を通じて持込みを行ったのは、直接選挙部管理課に持ち込むと、ただ資料を受け取られるだけで終わってしまう可能性が高いというアドバイスを総務省の方から受け、こちらとしても半年以上の歳月と経費をかけてやってきたこともあるし、全国から参加していただいた皆様のためにも、意見具申をしたいと思っていたので、政策評価広報課に資料提出とともに意見具申の場を設けてほしい旨を伝えて調整していただいた。
<結果提出・意見具申>
総務省の1F会議室にて、総務省自治行政局選挙部管理課の中島学係長に集計結果の冊子を手渡して、意見具申を行った。
運動をした理由や、憲法第15条に保障されている選挙権が本当にすべての有権者に保障されるべきものであるように投票制度を考えていただきたいという旨を伝えた。
中島係長からは、総務省も選挙管理委員会から投票所のバリア問題についての調査を行ってはいるが、当運動のようにスロープだけでなく多岐に渡る調査はしていないので、ぜひ参考にさせていただきたいという意見をいただいた。
他に、全国50,000ヶ所の投票所の中には、10人だけの有権者のための投票所もあり、その10人の状態をわかっているので、チェックシートにあるものすべてを配備しなくてもいいケースもあるから、すべてにおいてはできないとの回答をいただいた。
この回答に対しては、その地区の有権者のことがわかっていて、視覚障害者や聴覚障害者がいないこと等がわかって配備しないのはかまわないが、逆にその地区に配慮が必要な有権者がいることもわかるはずであり、その場合はやはり必要に応じた配備をしてもらいたいと申し入れた。
その後、来年の参議院議員選挙において、再びこの運動を全国展開するので、そのときには運動をすることの挨拶に来るので全国の選挙管理委員会にチェックに際して協力の呼びかけを行ってほしいという申し入れもあわせて行ったが、こちらのほうは回答をはぐらかされた感じではあったが、来年にきちんと挨拶に行こうと思っている。
◆今後の活動
この運動は今回限りではなく、今回を基礎にして以下のように展開していこうと考えている。
1.第2弾は来年の参議院議員選挙にて
投票所は全国に50,000ヶ所ある。正直まだ1,000ヶ所のデータしか集まっていない。それに1,000ヶ所をとってみても、すべての有権者が無理なく投票できる状態にはなく、これからも継続してチェックしていかなければならないものである。
都道府県で見ても、6県(秋田県・山梨県・島根県・香川県・徳島県・佐賀県)で回収0枚のため、全都道府県で回収できるようにしなければならない。
総選挙でとも考えていたが、全国の団体に参加を呼びかける時間が足りないことや実際に今年の秋にあるのかどうかわからないので、選挙だけに動いているわけではないので、確定している参議院議員選挙で行うこととした。
第2弾としては、やはり選挙広報の音訳や点訳といったことを付け加えるとともに、運動としては、結果入力を紙ベース・パソコンだけでなく、携帯でも簡易的な内容にはなるが入力できるようにしたいと考え、検討している。
2.来年の福祉のまちづくり学会で発表に向けて論文作成
今年7月に岐阜県高山市で開催された「福祉のまちづくり学会」に参加してきたが、そのときにユニバーサルデザインで師匠と仰いでいる川内美彦先生から、せっかく全国から1,000件以上のデータを集めたのだから、論文を書いて発表したらどうだと勧められた。神戸国際大学の阿部先生からも同様の話を勧められた。私としてもデータをより詳細に分析して、来年の「福祉のまちづくり学会」で発表できるように論文を作成していきたい。
3.投票所問題フォーラムの開催(予定)
今、岩手県で積極的に協力してくれた「アクセシブル盛岡(代表 石川紀文氏)」と松下政経塾が組む形で、盛岡市において投票所問題フォーラムを開催する予定です。
4月にチェックに参加してくれた菊池亨氏が、障害者の投票について今回の選挙を題材に、投票に行ったのか行かなかったのか、行かなかった場合は、なぜなのかのアンケートをとっているので、その結果とあわせて、憲法第15条が保障している選挙権の問題について話し合う予定です。詳細につきましては決定しだい、松下政経塾HPやMAGAZINE TAOにてお知らせいたしますので、ぜひご参加くださいますようお願いいたします。
◆参考資料・引用
- 共働作業所「b-free」HP http://www.b-free-web.com/
- アクセシブル盛岡HP http://www.acc-m.com/
海老名健太朗の論考
Thesis
-
- 2004/2/27
- 医療・福祉・介護
ノーマライゼーション社会を目指して ~これまで これから~
-
- 2004/1/29
- 思想・哲学
茅ヶ崎アロハ ~5月15日・16日はアロハマーケット~
-
- 2003/12/29
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~理想の投票所プロジェクト~
-
- 2003/11/28
- 医療・福祉・介護
少子・高齢社会のあり方 ~生涯現役社会を目指そう!~
-
- 2003/10/29
- 地域活性化
茅ヶ崎まちおこし ~茅ヶ崎スタイルとまちおこし~
-
- 2003/9/28
- 医療・福祉・介護
ユニバーサルデザインを学ぶ ~いわてUD学校 ピポ・ユニバーサルミニ駅伝~
-
- 2003/8/29
- 思想・哲学
ユニバーサルデザインって何だろう? ~「ユニバーサルデザイン体験in茅ヶ崎」を開催して~
-
- 2003/7/29
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~総務省に結果提出~
-
- 2003/6/28
- 思想・哲学
修験道 奥駆け修行記 ~日本海から太平洋まで~
-
- 2003/5/29
- 思想・哲学
茅ヶ崎TMO活動報告 ~”あい”のまち 茅ヶ崎~
-
- 2003/4/28
- 思想・哲学
ユニバーサルデザインへ(後編) ~安全と美観~
-
- 2003/3/29
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~運動から見た選挙(投票)制度の問題~
-
- 2003/2/26
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~みんなが利用できる選挙公報を~
-
- 2003/1/29
- 法律・法制度
誰もが投票できる選挙を目指して! ~投票所バリアチェック10~
-
- 2002/12/29
- 経済・産業
ものづくりの現場から ~日本酒をつくる 蔵人体験~
-
- 2002/11/28
- 法律・法制度
誰もが参加できる選挙制度 ~選挙制度は違憲状態!?~
-
- 2002/10/29
- 医療・福祉・介護
ユニバーサル・デザインへ(前編) ~バリアフリーへの疑問~
-
- 2002/9/28
- 医療・福祉・介護
第6回DPI(障害者インターナショナル)世界会議札幌大会に参加して
-
- 2002/8/29
- 医療・福祉・介護
ホームヘルパー2級資格取得を通して ~だからこそ、生涯現役社会を目指そう~
-
- 2002/7/29
- 医療・福祉・介護
イーハトーブ・by・Oneself ~チャレンジド・ジャパン・フォーラム2002に参加して~
-
- 2002/6/28
- 医療・福祉・介護
バリアフリーを考える ~車椅子議員との2日間の随行から~
-
- 2002/5/29
- 医療・福祉・介護
介護保険の現場から その2 特養研修
-
- 2002/4/28
- 医療・福祉・介護
介護保険の現場から その1
-
- 2002/3/29
- 医療・福祉・介護
ノーマライゼーション社会の実現 ~すべての人が、自立し、自律でき、矜持をもつことのできる社会を目指して~
Kentaro Ebina

第22期
海老名 健太朗
えびな・けんたろう
大栄建設工業株式会社 新規事業準備室 室長
Mission
「ノーマライゼーション社会の実現」