論考
Thesis
中国における中央政府と地方政府の関係
1996/1/29
- (中国にとっての地方問題)
- お隣、中国の将来を語る際に、最近「中央と地方の関係」がクローズアップされてきた。この問題は世界各国共通して持つ問題であり、わが国でも地方分権が議論されはじめて久しい。しかし、あの広大な大陸と世界の5分の1以上もの人口を有する中国にとっては、その持つ意味はいっそう大きいように思われる。
- (地方分権の概念)
- 地方分権を考察する際の概念として、フランスの思想家トクアビーユ(Alexis de Tocqueville, 1988)は「政治集権」(governmental centralization)と「行政分権」(administrative decentralization)を挙げている。政治集権とは、全国民に共通する問題、つまり一般法体系であるとか国家の対外関係などは1つの権威の下に置くという概念であり、行政分権とは、一部分の民の利益、つまり地方企業の発展などはそれぞれの地域の権威の下に置くという概念である(「論中央-地方関係 呉国光 著」より)。
- (地方分権の度合)
- 中国では、1949年の新中国成立以来、頻繁に中央と地方の財政管理体制が変動してきた。この中央と地方のパワーバランスを知る最も手軽な指標を以て、50年代以降の動きを総括してみると、「50年代、60年代は高度集中類型、つまり政治集権、行政集権といった類型、70年代は集権を主に、適度に行政分権する類型、80年代以降は行政分権を以て主となす(放権譲利)類型」(「挑戦中国 胡鞍鋼 著」より)といえる。
- (広東省の政治分権化)
- 80年代初めの「地方財政請負制度(以下、請負制という。)」の導入により、行政の地方分権の流れが明確になった。これは言うまでもなく「改革開放政策」を進めるために導入したものである。この制度は、都市によって上納の金額や方法が異なっているものの、基本的にはある一定額の上納金を中央政府に納めさえすれば、残りはすべて地方都市の自由裁量によって使用することができるという制度である。地方の経済的活力を発揮、集約させ、経済の活性化を図るために下放された経済権限は、中央政府の目論見どおり、「経済特区」を設置した広東省、福建省の経済的繁栄を促した。しかし、このような権力の下放は一方で、地方独自の利害関係を顕在化させ、また、開放政策による外部世界との結び付きは、各地方の固有の特性を徐々に強化した。政治権力をバックとした中央と地方という一律的な関係に代わって、むしろ経済権力を背景とする地域の分化につながった。特に、広東省では葉選平省長(当時)が税収の90%は内部留保し、省内で使うなど、中央のコントロール外にはみ出す地域もでてきた(政治分権化)。
- (中央政府の引き締め)
- このような地域の分化の行きすぎを恐れた中央政府は、93年11月に開催された「第14回中央委員会第3回会議」、いわゆる三中全会において、地方のコントロールの見直しを表明した。本大会で採択された50カ条の決議「社会主義経済確立のための若干の問題に関する決定」では、中央財政の機能を強化するため、従来の請負制を改め、地方政府に集まった税金をいったん中央に吸い上げ、交付金という形で再度地方へ戻すという制度が採択された。いわゆる中央と地方の「分税制」である。しかし、地方政府からの反発により、「実施に当っては経過措置をとり、また地方の既得権益を侵すことがないよう配慮する」という譲歩を行なっており、当初の中央政府の狙いが外れた形となっている。昨年末の人事移動についても、地方政府のトップの人事刷新を図った江沢民国家主席の意図とは外れ、地域のナンバー1と2との世代交替を行なったにすぎなかった。
行政分権を通り越して、政治分権に片足を突っ込んだ状況、つまり中央のコントロールが利かない状況に既に突入しているような様相をみせている。今まで政治集権を支えていた「社会主義」というイデオロギーが崩れ、その代役として、ナショナリズムをことさら吹聴され始めている。昨夏の異常なまでの抗日戦争報道、台湾独立に対する過剰な反応等はその現れであると推察する。しかし、56の民族、広大な国土による地域差、所得差による都市住民、農民、知識分子などの感情的対立、腐敗による共産党と民衆の離反などを越え、政治集権を支える柱に成り得るのだろうか。2月に発生した雲南省の大地震に対し、北京市民のあまりにもの無関心さが非常に印象的だった。行政分権から始まって、今や政治分権の前夜を迎えた中国。今後、平和裏に共産党独裁政権が崩壊することを望んでやまない。 - (付論)
- さて、わが国に目を転じてみるとそこには、中国では建国当時つまり毛沢東時代に経験した政治集権、行政集権の社会が存在する。長年にわたる地方分権の議論も虚しく、一向に行政分権は進んでいない。中央政府における議論だけで権限(=利権)の地方への移行が進むとは思われない。それはこれまでの歴史がすでに証明している。権限とは本来戦って勝ち取るものではなかろうか。そのためにも地方はこれまでのように東京(=中央政府)の方ばかりを見るのではなく、東京を飛び越えて世界に目を向けるべきだと思う。中国においてすでに実証されたように、外部世界との結び付きは、各地方の固有の特性を徐々に強化する。そして、その結果、経済権力を背景とする地域の分化につながっていくであろう。
高橋幸也の論考
Thesis
-
アジアの時代は地方の時代
-
- 1996/10/29
- 経済・産業
月例報告
-
- 1996/9/28
- 経済・産業
月例報告
-
- 1996/6/28
- 思想・哲学
月例報告
-
中国に観光協力を
-
- 1996/5/29
- 思想・哲学
中国人の二重性
-
- 1996/4/28
- 思想・哲学
現代中国人の思想
-
- 1996/3/29
- 思想・哲学
魂の入った社会の実現に向けて
-
- 1996/2/27
- 思想・哲学
塾主理念の学び方を考える
-
- 1996/1/29
- 思想・哲学
中国における中央政府と地方政府の関係
-
- 1995/12/29
- 思想・哲学
北朝鮮
-
- 1995/11/28
- 経済・産業
社会の現代化に果たす流通業の役割
-
- 1995/10/29
- 国土・交通
優秀観光都市
-
- 1995/9/28
- 思想・哲学
リゾート開発~上と下の融合
-
- 1995/8/29
- 国土・交通
中国は観光立国化を進めるべき(7月報告)の反響
-
- 1995/7/29
- 経済・産業
月例報告
-
- 1995/6/28
- 国土・交通
月例報告
-
月例報告
-
- 1995/4/28
- 国土・交通
月例報告
-
- 1995/3/29
- 教育
語学研修に関する報告
Koya Takahashi
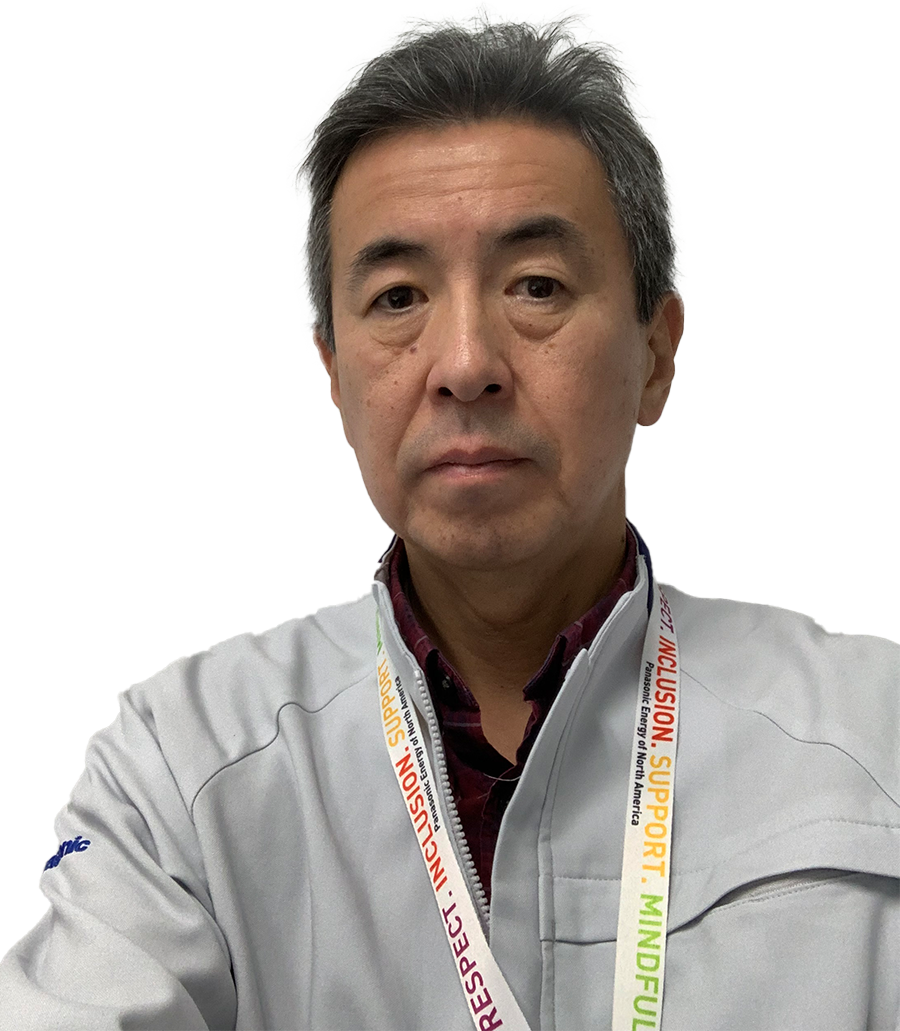
第15期
高橋 幸也
たかはし・こうや
パナソニックエナジー(株)監査役員
Mission
企業経営、管理会計、ファイナンス、国際経済
プロフィールを見る



