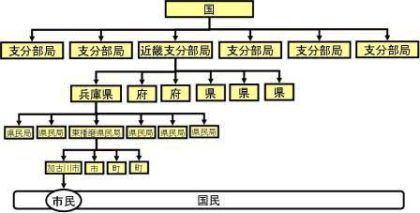Thesis
アジア主義と日本
アジア諸民族が団結していくことによって、欧米列強によるアジアの植民地支配から解放されようとした「アジア主義」。「アジアはアジア人のアジア」というその理想に対し、現実の日本は、「大東亜共栄圏」を掲げて大戦に突入し、敗戦という結末を迎えた。これからの国際社会と日本に向けて、戦前の「アジア主義」について再考する。
1.はじめに
帝国主義の時代、欧米列強がアジアへと植民地化政策を進めていったのに対し、明治維新によって近代国家を建設した大日本帝国は、自衛として、あるいは欧米と肩を並べる大国になるために、国家の強化に尽力し、日清戦争、日露戦争を経ていった。
たとえば、福沢諭吉の「脱亜論」(1885年)、中江兆民「三酔人経綸問答」(1887年)、樽井籐吉の「大東合邦論」(1893年)、宮崎滔天「三十三年の夢」(1902年)、岡倉天心の「東洋の理想」(1903年)といったものにおいて、欧米列強が植民地化政策を進める帝国主義の時代、日本の外交姿勢及び思想は、自由民権に裏づけされた理想主義と、国権の重要性を認識した現実主義の狭間で、揺れ動いていたことが理解できる。
そして、欧米列強に対するアジアの抵抗をアジア主義とするならば、近代日本はまさに明治、大正、昭和と、この欧米への対抗と追従の歴史であり、日本の将来を考える上では、アジア主義というものが、それら外交姿勢、思想の両方において、常に併存していたといえる。
つまり、日本自体の独立、繁栄とともに、日本がどういった思想のもとに、日本以外のアジアと関係を築くかということが、日本が時代を歩んでいく上において、大きな分岐点として存在していたのである。
日本は、日露戦争以降の経済発展によっては、世界三大強国と自負していたわけであるが、列強による植民地化が進んでいくアジア諸国との間で、欧米に追従すればするほど、「欧化と国粋、国権論と民権論、連帯と侵略、共感と蔑視」という相対する様々な感情、主義が増大し、矛盾を抱えていったといえる。
結果として日本は、満州事変、5・15事件、国際連盟脱退、そして政党政治の没落と軍部の膨張という道を進んでいき、「大東亜共栄圏」を掲げて、アジア全域での対米戦争へと突入し、日本が米英とは異なる「大東亜新秩序の建設」を目指していくことになる。
多くの犠牲と原子力爆弾の被爆という耐え難く忍び難い歴史を経て敗戦を迎えた後では、往々にして、日本では、その戦争を帝国主義による侵略戦争とし、隣国への深い謝罪と自国民への反省という形に流れてきている。
その流れにおいては、実に感情的なレベルであるが、一部の国民のなかに「日本の起こした戦争」は多くの残虐な被害を与えて、韓国や中国を侵略していったという「自虐史観」が存在する。
一方、その反動としての言動、侵略戦争の否定やアジア解放戦争であったという意見も見られる。しかし、そういった善悪としての、あるいは種々の主義に捉われた歴史の見方は、あらゆる史実をありのままには認めず、数あるものを一面として捉えることにならざるを得ないといえるであろう。
つまりは、前者は、当時の世界情勢における日本の位置やアジアの近代化に向けた日本の苦悩といった、日本の戦争に至る経緯を深く考察しておらず、現在的価値観での悪事を収集あるいは捏造することが散見される。一方、後者においては、その戦争に至る複雑な経緯のなかで、前者に対抗する為か、日本の選んだ思想がどう普遍的価値や理想と離れ、また当時の国際情勢を現実的に、長期的に判断しきれていなかったということを国家という枠内において目を伏せていると言えるであろう。
ここでは、日本がこれからアジア、世界のなかでどう生きて行くかということに対して、「アジア主義」の変遷にそって日本の歩んだ道を改めて追っていくことにする。そして、世界における欧米、日本、アジアの大きな流れにおける日本とアジアというものについて私なりに考えていきたい。
こうした考察は、当時の状況をより理解するだけでなく、その後の日本の進路を見ていく上でも重要であろう。とりわけ、中国やインドをはじめとして、経済発展の著しいアジアに対し、これからの日本と東アジアのありかたを考えることにもなると思えるのである。
2.アジア主義の理想と「大アジア主義」
アジア主義は、前段に挙げた各書に観られるものにおいても、多種多様な持論と思想形態をもっており定義は困難であるが、趙軍氏によると「アジア諸民族の団結」と「欧米列強のアジア侵略に対する対抗」という二つに絞ることが、アジア主義の変遷を理解することが容易になるとしている。
つまりは、「アジアの連合」、「アジアはアジア人のアジア」ということが、「思想的最大公約数」であり、アジア諸国と日本ともに初期段階として持ち合わせていたものであるといえる。
日本は、19世紀後半から、不平等条約等の他国からの侵略に近い歴史をもっており、中国をはじめとした他のアジア諸国とほぼ同時期に、欧米列強の脅威の下にさらされた。明治国家のもと、国力を向上させることが可能となり、植民地化の危機は脱した日本に対し、当時のアジアは、東南アジア、中国、インドともに、欧米の分割・占領の格好の未開地であり、日本は、そういった時代の流れに対する強い同情心や連帯感を持っていたといえる。
そして、こうしたアジア主義はまた、民権派によっては、アジア諸国、諸民族が平等、自主のもとで幇助し合い、アジアの団結によって欧米勢力をアジアから追放しようとする考えとなっていく。
一方で、民権派に対する国権主義においては、それぞれの方法論によって、日本によるアジアの復興、解放を主体的に行っていこうというものである。しかし、そこには、日本の優位性と、手段としての帝国主義が重なっており、国際社会への地位の向上、「欧米列強と肩を並べる」という日本の基本姿勢を築いていくものであったといえる。
軍部の肥大化を許した後においては、「戦争の大義として、アジア主義を利用した欺瞞としての大東亜共栄圏」といわれる様に、そもそものアジア主義を変質させたものとして帰結されたという疑問点を残すことになった。
こうした国家主義的、時にして軍国主義的なアジア主義を、日本の「大アジア主義」というように区別することもできるが、前段で述べたとおり、当時の状況を鑑みれば、前者と後者を明確に断罪することは出来ないと思える。ただ、結果として「大アジア主義」は後に述べるとおり、アジア諸国にとっての批判の的になるわけである。
さて、明治時代における中江兆民『三酔人経綸問答』には、洋学紳士君、東洋豪傑君、南海先生の三者が、登場し、酒を飲みながら政治思想・哲学について語り合っていくわけであるが、そのようなアジア主義の変遷を一考させるものである。そこには、当時の日本(1889年)が、どういう立場にあって、外交に対する思想・心情をどう考えようとしていったのかが伺える。
洋学紳士君は、軍備の撤廃によって、他国への侵略の意思が無いことを示し、弱小国である日本は、道義外交に徹すべきであるとし、政治的進化の信奉者として、人類が最後に到達する最高の政治形態である民主共和制の採用を主張する。世界平和の実現と各国における民主共和制の採用、国際連盟の提唱をするわけである。すなわち、理想主義である。
これに対し、東洋豪傑君は、軍事大国化と中国割取論を訴え、現実に戦争が存在する以上、軍事大国を目指さなければならないとする。そのためにも、隣国である中国を割取しなければならないというわけである。軍事に対する優位な視点を保有し、現実を追従する立場である。
そして、こうした理想主義、現実追従主義に対し、南海先生は、この双方とも、それぞれの理由で現実にそぐわず、前者はユートピア、後者は過去の戦略であり、より正しい現実主義として、平和的友好関係の樹立への努力を日本が積極的に行うべきとする。
国際社会を弱肉強食の世界として固定化するのではなく、日本への侵略に対しては、国民的総抵抗で対処する、そしてパワーポリティックスや国際法の発展によって軍縮を平行させながら、世界各国との平和友好関係の構築を目指すべきだとするのである。
こうした議論は、その後の日本の進路を予見するものであると同時に、現在においても尚通用する論理であることは、驚かされるばかりである。ともかく、日本が国際社会のなかへ突入していった明治時代においてこそ、こうした国家の進路を決することが、日本の大きな課題であったわけである。
また、こうした議論の存在する時代、大アジア主義者としての有名な運動家である頭山満は、自由民権運動としての向陽塾から、明治20年には、国権主義思想、興亜思想の玄洋社へと転換していく。
頭山満は、自由民権運動から日本の改革運動に関わっていったが、アジアと日本の現状に対する強い認識から、愛国主義者として、生涯をかけて大アジア主義における活動を行っていったのである。金玉均や孫文、ラス・ビハリ・ボース等の革命活動家への援助をおこない、日露戦争の開戦論を唱えるなど、そこには欧米列強の圧力に対する強い対抗心があったことが考えられる。それを示す記述として、以下のようなものがある。
『有色人種として欧米人に対抗するには軍国の設備が必要であり、ことに東洋の新興国として勃興せる我が国が、将来東洋の盟主たらんとの希望を抱蔵する時代において、軍国主義の首唱は最も時を得たり。』
(「大アジア主義と中国」趙軍より引用)
また、この玄洋社の憲則は、以下の通りである。
『第一条皇室を敬戴す可し、第二条 本国を愛重す可し、第三条 人民の権力を固守す可し』
これは、大日本帝国における天皇の存在の大きさを示すとともに、愛国者として、国民として、大アジア主義等の思想と理想を実現していくということの現れであろうと思える。それらは、同時に、天皇を頂点とする皇道楽土、皇道アジアという思想にもつながっていった。それを傀儡政権の樹立と判断することも止む無ければ、革命政党によるアジア全域における近代国家の樹立という夢ということもできるであろう。
つまり、明治時代に、こうした民権と国権の比重、国際社会における平和主義のあり方をどう選ぶかということが、近代化に成功しつつある日本と、停滞し植民地化の進むアジアの中において、日本にはするどい選択が突きつけられており、そしてその選択は、その後の日本の進路を左右するものとなっていったといえるであろう。
3.日清・日露戦争と「大アジア主義」の変遷
1894年には、列強のアジア侵略に対抗して朝鮮への進出をはかる日本と、朝鮮を属国とみなす清とが対立し、朝鮮国内の事大党(清側勢力)と、独立党(日本と連携し近代化をはかろうとする勢力)とが対立していた。朝鮮で農民の反乱である東学党の乱がおこり,朝鮮が清に援軍をもとめると日本も居留民の保護を名目に出兵し,日清戦争が起こった。
近代的な軍隊をもつ日本軍は,朝鮮から満州に進出し勝利をおさめ、1895年下関条約を結んだ。朝鮮の独立と遼東半島、澎湖島、台湾を日本にゆずるという条約であったが、遼東半島については中国の清国の都を脅かすということからフランス、ロシア、ドイツが三国干渉によって中国へ返還することになったわけである。
しかし、中国への欧米諸国の進出は、その後、大きく進んでいく。ロシアは、1896年に東清鉄道の敷設権を、1898年には旅順・大連を租借地とし、東清鉄道をそこまで延長する権利を得た。日本はこうしたロシアに対し、「臥薪嘗胆」というスローガンの下に重税に耐えて働き、「富国強兵」政策を推進していったのである。
この「臥薪嘗胆」は、中国の故事であるが、まさにアジア文化として、さらにそれを昇華させた日本文化が、ロシアという白色人種の大国に対抗するために、国民全体が一団となっていったということを感じる。
また、ここで当時の状況を認識しておかなければならないのは、その他、欧米も中国への進出を進めている。中国の分割が始まったということである。ドイツは、1898年に山東省でドイツ人宣教師が殺害された際に、膠州湾を租借し、山東半島を横断する鉄道の敷設権を得た。そして、フランスは、1895年に雲南方面における鉄道敷設権を得、1899年には広州湾を租借した。また、イギリスは、すでに香港の割譲を受けていたが、1898年に、ロシアの南下に対抗するために山東半島北岸の威海衛を租借し、香港の対岸の九竜半島も租借した。アメリカはフィリピンを獲得した後、1899年に中国に対する門戸開放を提唱していた。
ロシアの満州へ侵攻と占領に際し、様々な経緯を経て始まった日露戦争の結果においては、アジア諸国の喜びや「奮い立った」という反響を受け、アジアの実情に対する日本への期待感があったことを見ることができる。
ここでは、乃木将軍が統率する4次にわたる旅順総攻撃で、自然の要塞といわれた旅順を多くの犠牲とともに開城させた1905年1月2日の翌朝、イギリスのタイムズ紙における記述を記しておく。
『日本人は西洋の学問の成果をすべて集めた。そして、西洋の成果を応用し、組み合わせて使いこなしている。この民族はわれわれの育んだ複雑な文明をわずか一世代あまりのうちに習得したのだ。ロシア軍はロシア人最高の武勇を発揮している。しかし、それを攻撃する日本人はもっと偉大といわざるをえない。ねばり強さ、機転、素晴らしい勇気、厳しい状況への知的な対応、いま、世界中が興奮している。日本人は誇り高い西洋人と並び立つ列強であることを世界に示したのだ。』
日本の「粘り強さ、機転、勇気、厳しい状況への知的な対応」といったものが、世界に示され、それまでロシアにとっては蔑視の対象であった日本が、世界の列強と肩を並べる大国として、認められた時代であったといえる。
一方で、ドイツの皇帝ウィルヘルム2世は、日露戦争後の日本の状況について、以下のように談話を残している。
『世界に人類の運命を決する大きな危機が近づいている。その第一回の戦争は、われら白色人種のロシア人と有色人種日本との間で戦われた。白色人種は不幸にして敗れた。日本は白人を憎んでいる。白人が、悪魔を憎むように憎んでいる。しかし我らにとって、日本そのものが危険なわけではない。統一されたアジアのリーダーに、日本がなることが、危険なのである。日本による中国の統一、それが、世界に脅威を与えるもっとも不吉なことである。』
(NHK 『映像の世紀』より引用)
白色人種にとっての黄色人種は、日本民族という存在によって、それまでの地位を大きく変化させ、蔑視から脅威として認識されたわけである。
また、この当時の世界にとって、日本が朝鮮、そして国内の混乱する中国と統一を果たし、新たに近代化した大国を建設していくということも考えられ、そうした場合の世界地図というものは、大きくそれまでの国際秩序を変化させるものであったということが、想像できる。
つまり、それまでの旧大国中国と日本、白人世界の大国ロシアと日本といった関係から、日本では自身に大きな自負が生まれ、同時にナショナリズムも興隆していき、日本おけるアジア主義という思想も、民権派にあったアジア主義から、国権主義的な大アジア主義へ、そしてさらに拡大・膨張主義的な大アジア主義へと変遷していったと考えられる。
アジアの周辺諸国を平等にみなし、連携して団結し、新たなアジアを作っていこうとする考えから、弱小国としての中国をはじめとするアジアを、日本が盟主となって指導していかなければならないという考えである。大和民族優越論というのも、幸か不幸か、必然的に出没してきたことであろう。
詳細な分析はここでは出来ないが、第一次世界大戦における日英同盟による対独参戦、そしてパリ講和条約によって、中国大陸における青島、威海衛などのドイツ権益の攻略・獲得を進め、山東鉄道の占拠を推進していった。日本においては、1910年日韓併合、1914年の対華二十一か条の要求にもあるように、既に中国や朝鮮との対等な連携は否定し、覇権としての大アジア主義が形成されていったといえる。
4.孫文の「大亜細亜主義」において
では、日本のこうした状況、いわば日本の拡大主義的な大アジア主義者に対して、中国の革命家としてのアジア主義を持っていた「革命の父」、孫文に関して見ていくことにする。
孫文は、中国を日本をモデルに近代化すべきだという考えを持っており、日本における大アジア主義においても、ある時点までは一定の理解を示し、孫文自身は、アジアの連携や連合において、アジア全域でブルジョア革命を成功させるためにも日本には役割があり、そして、その先には、欧米の帝国主義によって植民地化されたアジアのの解放と世界の平等な統治という理想があった。
なかでも、興味深いものに、孫文が、中国と日本が連携したアジア主義が実現した世界の構図に関して述べている内容がある。
『中国と日本がアジア主義によって太平洋以西の豊富な資源を開発し、また、アメリカがそのモンロー主義によって太平洋以東の勢力を統合し、各自それぞれの発達を遂げたなら、百年にわたり衝突の憂いはなくなるのである』
(「中国の存亡問題」『大アジア主義と中国』より引用)
こうした孫文のアジア主義において、日本が中国との緊張関係を強めていく当時の日本の大アジア主義への異議を唱えた有名な講演がある。以下、1924年12月28日の神戸高等女学校における講演の一部分を引用する。
『東方の文化は王道であり、西方の文化は覇道であります。王道は仁義道徳を主張するものであり、覇道は功利強権を主張するものであります。(中略)
我が大アジア主義を実現するには、我々は何を以て基礎としなければならないかと言いますと、それは我が固有の文化を基礎にした道徳を講じ、仁義を説かねばなりません。仁義道徳こそは我が大アジア主義の好個の基礎であります。(中略)
我々が大アジア主義を説き、アジア民族の地位を恢復しようとするには、唯だ仁義道徳を基礎として各地の民族を連合すれば、アジア全体の民族が非常な勢力を有する様になることは自明の理であります。(中略)
我々の主張する不平等廃除の文化は、覇道に背叛する文化であり、又民衆の平等と解放とを求める文化であると言い得るのであります。貴方がた、日本民族は既に一面欧米の覇道の文化を取入れると共に、他面アジアの王道文化の本質をも持って居るのであります。今後日本が世界文化の前途に対し、西洋覇道の鷹犬となるか、或は東洋王道の干城となるか、それは日本国民の詳密な考慮と慎重な採択にかかるものであります。』
ここで、孫文が、「王道」と「覇道」という言葉を使って、日本の進路について指摘しているのは、日本の「近代化」と「拡大」という側面に対し、「拡大」の道を進みはじめた日本に対する批判である。「近代化」は日本、中国ともにアジア諸国も自立していくために、西洋から学んでいかなければならないが、「拡大」という面においては、欧米による占領、植民地化とは異なった方法において、提携や連合をしていくことを期待するということである。
孫文は、欧米列強、白色人種の植民地状態にあるアジア諸国、中国、黄色人種の現状を憂い、民主、民権、民生という三民主義を唱えていた。それらを実現するためにも、近代技術、軍隊、政治制度の比較的進んだ日本に学び、ともに人類の歴史を正そうとしたわけである。その日本は、アジアの文化にある仁義道徳に則って、その近代性から自国を拡大し、支配をする立場ではなく、民主化、独立を支援する役割を果たして欲しいという切実なる願いであったといえる。
しかし、1925年に孫文は死去し、後を継いだ蒋介石は張学良によって拘束、監禁、そして共産党代表周恩来に説得されて、抗日勢力とともに国共合作による反日運動をおこなっていく。日本においても、世界恐慌か、統帥権干犯問題という大日本帝国憲法上の欠陥によるものか、政党政治から軍部の膨張へと変遷していき、満州事変、日中戦争と進んでいってしまうことになる。
こういった時代における軍事行動と政治は、既に日本の中国に対するアジア主義ならず初期の大アジア主義の思想からもかけ離れたものになっているとも考えられる。また、同時に、既に日本がその理想とともにアジア主義を実現する目処は、絶たれていってしまった。
5.『大東亜新秩序の建設』と『反軍演説』
この後、『大東亜新秩序の建設』つまり『大東亜共栄圏』が政府から発表されていき、日本は、国際連盟の脱退、ファシズムが現れた国家であったナチス・ドイツ、ムッソリーニによるイタリア王国との日独伊三国同盟を結び、太平洋戦争に突入していく。このことについて最後に考察をしなければならないであろう。
1938年11月、近衛首相によって、東亜新秩序建設声明が発表された。
『帝国ノ希求スル所ハ、東亜永遠ノ安定ヲ確保スヘキ新秩序ノ建設ニ在り。今次征戦究極ノ目的亦此ニ存ス』
また、1940年8月においては、松岡洋右外相が、大東亜共栄圏という言葉を公式に用いて強調している。
(東京朝日新聞)
『わが国の外交方針は、日満支をその一環とする大東亜共栄圏の確立を図るにある。大東亜共栄圏は、欧米のやってきたように領土を併呑したりその人民を征服したり搾取しようとするのではない。反対に、原住民を帝国主義の圧迫から解放し、彼らを奴隷として取り扱う代りに兄弟として可愛がり彼らと共存共栄の関係を結んでいこうというのである。』
この東亜新秩序が、日独伊、また(それに失敗したが)ロシアを加えたとしても、その4国で英米仏蘭をはじめとした国際連盟の秩序に対抗し、欧米における独伊の、アジアにおける日本の新秩序が、より平和的に、もしくは日本が理想としている共存共栄の姿として、築いていくことができるのかどうかは、極めて疑わしい。
これらは、日本が戦争に至った経緯は様々にあるなかで、結果としての『大東亜共栄圏』という大義であったが、「アジア主義を戦争の欺瞞に利用した」という批評が現在では定着していることであろう。
こうした場合、「アジアの解放のための戦争」という意見に対しては、アジア主義や大アジア主義が描いた日本の役割は、戦争をするということではなかったと言うことができるであろう。「大恐慌において戦争への圧力があったアメリカ」という理由づけをしても、ABCD包囲網によって無謀な戦争を余儀なくされ、海軍による東南アジア、陸軍による中国をはじめアジアの覇権を争い無残な戦争をしていったという解釈には、本土決戦という最終戦に向かえば向かうほど、分が悪いであろう。
しかし、ここにおいて、私が考えたいのは、この双方と断言することに対する日本人としてのある言い表せない思いである。なかでは、日本が、実際に東南アジア諸国への発展や独立を進める形での戦争を行っていったというアジア主義に通ずる事実というものも、それに対する排日軍が結成されていったことと合わせて、忘れないようにしたいわけである。
また、この戦争に至る軍部の膨張を批判した斉藤隆夫のように、こうした戦争に対して、反対する議員も存在していたことを、もう一つの事実として、記憶しておきたい。民政党の斉藤隆夫は、近衛元首相の『東亜新秩序の建設』声明に対して、戦争というものの本質から、理想と現実の矛盾を突き、東亜新秩序の実体を迫ったのである。
これに関しては、まさに全文が光るごとく名文であり、政府の中国における新政府の樹立に対する考えなど、その後の中国との平和的外交に含めて鋭い指摘をしているのだが、ここでは官報速記録より削除された2つのパラグラフにおいて引用する。
まずは、東亜新秩序の実体を迫った部分である。
『事変処理については東亜の新秩序建設ということが繰り返されております。この言葉は昨日以来この議場においてもどれだけ繰り返されているか分らない。元来この言葉は事変の初めにはなかったのでありますが、事変後約一年半の後、即ち一昨年十一月三日近衛内閣の声明によって初めて現われたところの言葉であるのであります。東亜の新秩序建設ということはどういうことであるか。(中略)
政府においてはこういうことを言われるに相違ない。また歴代の政府も言うている。何であるか。このたびの戦争はこれまでの戦争と全く性質が違うのである。このたびの戦争に当っては、政府はあくまでも所謂小乗的見地を離れて、大乗的の見地に立って、大所高所よりこの東亜の形勢を達観している。そうして何ごとも道義的基礎の上に立って国際正義を楯とし、所謂は八紘一宇の精神をもって東洋永遠の平和、ひいて世界の平和を確立するがために戦っているのである故に、眼前の利益などは少しも顧みるところではない。これが即ち聖戦である。 神聖なるところの戦いであるという所以である。(中略)
その言はまことに壮大である。その理想は高遠であります。しかしながらかくのごとき高遠なる理想が、過去現在及び将来国家競争の実際と一致するものであるか否やということについては、退いて考えねばならぬのであります。いやしくも国家の運命を担うて立つところの実際政治家たる者は、ただ徒に理想に囚わるることなく、国家競争の現実に即して国策を立つるにあらざれば、国家の将来を誤ることがあるのであります。』
次に、最後の結びの有名な一節を含むパラグラフであるが、日本の日中戦争に対する展望のなさ、大東亜新秩序のような実体のない理想が、現実においては単なる弱肉強食の戦争に過ぎないことを指摘している。
『彼ら(キリスト教国)は内にあっては十字架の前に頭を下げておりますけれども、ひとたび国際問題に直面致しますと、キリストの信条も慈善博愛も一切蹴散らかしてしまって、弱肉強食の修羅道に向って猛進をする。これが即ち人類の歴史であり、奪うことの出来ない現実であるのであります。
この現実を無視して、ただいたずらに聖戦の美名に隠れて、国民的犠牲を閑却し、曰く国際正義、曰く道義外交、曰く共存共栄、曰く世界の平和、かくのごとき雲を掴むような文字を列べ立てて、そうして千載一遇の機会を逸し、国家百年の大計を誤るようなことかありましたならば、現在の政治家は死してもその罪を滅ぼすことは出来ない。
私はこの考えをもって近衛声明を静かに検討しているのであります。即ちこれを過去数千年の歴史に照し、またこれを国家競争の現実に照して、かの近衛声明なるものが、果して事変を処理するについて最善を尽したるものであるかないか。振古未曽有の犠牲を払いたるこの事変を処理するに適当なるものであるかないか。東亜における日本帝国の大基礎を確立し、日支両国の間の禍根を一掃し、もって将来の安全を保持するについて適当なるものであるかないか。これを疑う者は決して私一人ではない。
いやしくも国家の将来を憂うる者は、必ずや私と感を同じくしているであろうと思う。それ故に近衛声明をもって確乎不動の方針なりと声明し、これをもって事変処理に向わんとする現在の政府は、私が以上述べたる論旨に対し逐一説明を加えて、もって国民の疑惑を一掃する責任があるのであります。』
この演説によって、斉藤隆夫は軍部の圧力によって「聖戦目的の侮辱、10万英霊への冒涜」「非国民」として除名処分に問われるわけであるが、軍部をはじめとする日本の政治が、言論の府である議会を機能させていなかったことを示すものである。そのときの議決は、賛成296票対反対7票であり、棄権が144票あった。この棄権は、日本の良識であったともいえる。
大東亜共栄圏は、アジア主義に始まった大アジア主義の実現が、既に不可能となったときにおいて、政府の大方針として現れ、それは現実とかけ離れた理想に過ぎなくなっていたということが言えるのではないだろうか。
6.インドから見た大日本帝国
こうした日本とアジアについては、イギリスの植民地化に強い抵抗感を持ち、独立へと動いていったインドの各指導者の発言において、確認することができる。日本人として、感慨深いものを得るものであるので、ここでは、いくつかについて、資料等より集めたものを改めて、記載しておきたいと思う。個々の発言内容は、これまで述べた文脈を実感ないし補足させるものであり、ここでは敢えて解説を省略したい。
まず、日露戦争での日本の勝利が、インド全国に、大英帝国をインドから放逐すべきだという独立運動を奮い立たせることになったときのインドの初代首相ジャワハル・ネールの回想である。
(NHK 『映像の世紀』より引用)
『日本の勝利は私を熱狂させた。
私は新しいニュースをみるため、毎日、新聞を待ち焦がれた。
どんなに感激したことか。どんなにたくさんのアジアの少年少女、そして大人が同じ感激を体験したことか。ヨーロッパの強国ロシアはアジアの国、日本に敗れた。
だとすればアジアはヨーロッパを打ち破ることができるはずだ。「アジア人のアジア」という声が沸き立ったのである』
インドの文豪ラビンドラナート・タゴールは、当時の日本への記述を、旧き日本、新しき日本という表現で、日本の進んでいく道に対して次のように、指摘していた。
(『大アジア主義と中国』趙軍より引用)
『私の見るところによれば、日本には二つの日本がある。
一つは旧き日本、一つは新しき日本である。新日本というのは西洋文明をそのまま移植したままのように私には見える。これに反して旧日本には、建国の昔より面影が今にいたるまで生存して伝わっている。
もし今日の若い学生すなわち第二の国民が、旧い日本を忘れたならば日本は必ず亡びるであろう。私が合掌してここに諸君に希うところは、西洋文明と日本固有の文明とを調和し、あくまでも日本古来のものを根底として新しき家屋を建設してもらいたいということである。』
「非暴力闘争」を信条として掲げ、非暴力による独立運動を続けた「偉大なる魂」、ガンディーの言葉がある。1942年7月に発表された「すべての日本人に」と題する手紙のなかの一節である。
『私はあなた方日本人に悪意を持っているわけではありません。
あなた方日本人は「アジア人のアジア」という崇高な希望を持っていました。
しかし今ではそれも帝国主義の野望にすぎません。そして、その野望を実現できずにアジアを解体する張本人となってしまうかもしれません。
世界の列強と肩を並べたいというのがあなた方日本人の野望でした。しかし中国を侵略したり、ドイツやイタリアと同盟を結ぶことによって実現するものではないはずです。あなた方は、いかなる訴えにも耳を傾けようとはなされない。ただ剣にのみ耳を貸す民族だと聞いております。それが大きな誤解でありますように。
あなた方の友ガンジーより。』
最後に、インドの独立のためにも、日本の大東亜共栄圏を利用しようとしたスバス・チャンドラ・ボースの大東亜会議における発言がある。
『大東亜共栄圏の建設は全アジア民族の重大関心事であり、強奪者の連盟に非らずして真の国家共同体への道を拓くものである。』
ボースが率いる国民軍は、1944年の日本軍によるインパール作戦で従軍し、敗北を喫した。そしてボースは、台北から大連へと飛ぶ飛行機での事故死という結末を迎えた。
インドの国会議事堂には、正面にチャンドラ・ボース、右にガンジー、左にジャワハルラール・ネルーの肖像画が掲げられているという。日本のアジアに対する外交、軍事行動というものを、理想主義であれ、現実主義であれ、一側面から語ることは不可能であると痛感する。
7.「小日本主義」と戦後の日本
大アジア主義に対立する、あるいは内包される一つの思想として、石橋湛山の「小日本主義」というものも挙げておきたい。
「領土拡張と保護政策とをもって国利民福を増進」する大日本主義は、「軍国主義、専制主義、国家主義」にならざるを得ず、これに対し、「産業主義、自由主義、個人主儀」に立ち、「主として内治の改善、個人の自由と活動力との増進によって、国利民福を増進」することが小日本主義である。先述した内容においては、大アジア主義は大日本主義と等しくはないが、膨張的大アジア主義は、大アジア主義かつ大日本主義ということがいえるであろう。
石橋湛山の小日本主義は、世界経済が、自由貿易主義、経済合理主義、国際協調主義というものに貫かれていくために、日本も外交努力を積み重ね、先導的にそういった世界を築いていこうというものである。そのためにも、日本は、本州など主要四島でやっていくことで十分であり、それが、戦争をすることよりも極めて経済的だということである。
そういった自由経済思想から、湛山は、日清日露戦争以降、日本のどの政党も国民も「大日本主義」を標榜し、「小日本主義」を掲げる政党がなかったことを「東洋経済新報」で批判し続けてきた。そして、青島占領と中国への21ヶ条の要求という「対華交渉」を、日本が露骨な領土侵略政策を敢行したことを世界に示すことになり、世界が、挙国一致でその政策を遂行する日本に対し、これまで築いてきた日本の立場を転覆させるのではないかと予見し、これを「帝国百年の禍根」と断じている。
また、植民地主義について、石橋湛山は、こう述べている。
『思うに今後は、いかなる国といえども、新たに異民族または異国家を併合し支配するが如きは、とうてい出来ない相談なるは勿論、過去において併合したものも、漸次これを解放し、独立または自治を与うるほかないことになるであろう。』
(『日本リベラルと石橋湛山』田中秀征著より引用)
帝国主義が依然として存在する時代、アジアの植民地も解放されていないなかで、国際社会が、白人支配や植民地支配という先進欧米諸国の特権を放棄する方向へと、そう簡単に進むことはないように思える。しかし、もし欧米列強と肩を並べる大国日本が、使命感を持って、敢えて「小国主義」を実行していくことによって、ひょっとすると、より早くに国際社会に変化をもたらすことが出来たかもしれない、そうとなれば、ある意味での「アジア主義」が理想とした社会を実現できたかもしれないというのは、感慨深い。
大日本主義による拡大的大アジア主義の帰結は、大東亜共栄圏の崩壊と日本をはじめアジア諸国の多くの犠牲を伴う敗戦であった。しかし、その後には、アジアの各国が、その権力の空白化のなかで、独立を遂げていったのである。
太平洋戦争(大東亜戦争)中には日本の占領下にあったベトナム(1945年9月)、フィリピン(1946年)をはじめ、インド(1947年)、ビルマ連邦(1948年)、インドネシア(1949年)と独立が実現されていく。
戦後の日本は、東西冷戦が激化するなか、民主化、経済発展というものに集中し、奇跡的な復興を遂げ、世界有数の経済大国にまでもなった。これによっては、日本がさらに他のアジア諸国との経済格差を作ったと同時に、アジアにおける経済発展の先導的役割を果たし、「雁行型」といわれる産業育成、経済発展の道筋を、独立したアジア諸国に広めていくのである。
8.これからのアジアと世界に向けて
以上、アジア主義、大アジア主義、大東亜共栄圏について、そして小日本主義と戦後の日本の経済発展について概観してきたが、文字数の関係、私自身の能力不足から、荒い議論になったことをお詫びして、結びに移っていきたい。
現在の国際社会においてみれば、第二次世界大戦以降、こうしたアジア主義が語った理想をよそに、植民地は独立していき、また、東西冷戦の終結とともに「アジアの奇跡」といわれる経済発展も実現してきた。無論、アジア諸国における民主化においては、未だ実現していないといえるが、アジアの文化というものも、欧米文化を相互に取り入れあっている状況であるとはいえるであろう。
つまり、大きな点で述べれば、人類においての「自由」や「民主」といった普遍的価値というものを、結果として、アメリカをはじめとする欧米が、アジアに与えていき、アジアは、それに応じて国際社会と共生して、さらには欧米文化にもそのアジア文化の良さ(漠然としたもの、また多様性のあるもので申し訳ないが)を反映させ、より「自由」と「民主」の普遍的意義を深化させていっていると考えられる。
今日においては、『BRICs』といわれるように、ブラジル、ロシア、インド、中国がこれからの50年に最も経済成長を続け、このままの成長が続けば、50年後には中国が世界一の経済大国になるという予想もある。
中国、インドが経済的に大国になる社会にむけては、アジアの連携と世界の秩序の安定というものに、日本は改めて、繁栄と発展、そして民主主義によって貢献していかなければならないであろう。
そのためには、過去における日中の関係とアジアというものの歴史を思い返し、また、激動の近代史を抱えてきた中国の現在の政治や経済状況に対して、その認識を深めた上で、日中関係というものを築いていかなければならない。そのためにも、普遍的な価値観というものを常に追求しながら、様々な外交努力を重ねていくことが重要であるのは述べた通りである。
東アジア共同体という方向性もある。東アジアでの金融や環境、エネルギーをはじめとした危機管理、あるいは地域経済圏としての実情に合わせた自由化というものは進めていく必要はある。しかし、それはEUやアメリカ圏と対立するものではなく、それらにより普遍的な共存する自由と民主を実現していくためのものであるということを述べて筆をおきたい。
参考文献
『大アジア主義と中国』 趙軍 著 亜紀書房 1997年
『20世紀 大東亜共栄圏』 読売新聞20世紀取材班 中公文庫 2001年
『映像の世紀 Japan編』 NHK放送
『映像の世紀 独立の旗の下に編』 NHK放送
(DVDのため、引用における文言には、原文の確認を行う)
『竹内好「日本のアジア主義」精読』 松本健一著 岩波現代文庫 2000年
『三酔人経綸問答』 中江兆民著 岩波文庫 1965年
『世界の名著 78 孫文・毛沢東 』 孫文著 毛沢東著 中公バックス 1980年
『大東亜戦争の実相』 瀬島龍三著 PHP文庫 2000年
『日本の近代 政党から軍部へ 1924~1941』 北岡伸一著 中央公論新社 1999年
『世界の歴史15 ファシズムと第二次世界大戦』 村瀬興雄著 中央公論社 1975年
『新しいアジア ~日本の歴史観試論~』 小野貴樹著 松下政経塾月例レポート 2004年
『回顧七十年』 斉藤隆夫著 中央公論社 1948年
『石橋湛山と小国主義』 井出孫六著 岩波ブックレット 2000年
『日本リベラルと石橋湛山』 田中秀征著 講談社選書メチエ 2004年
前川桂恵三の論考
Thesis
-
生産性の高い政治と効率的な行政へ向けて ~新しい地域と公共の経営~
-
韓国における「オウトピア」と「新しい人間観」
-
アジア主義と日本
-
地域主権型国家日本の実現に向けて
-
靖国神社と日本国の未来
-
公共事業改革と地域の自立
-
日本国憲法「第8章地方自治」と地域主権
-
これからの日本と中国における「新しい人間観」 ~空海入唐1200周年を迎えて~
-
日本の広域自治制度をどう転換すべきか
-
自由民権から戦後改革に観る分権論
-
財政再建に向けた日本の国家観
-
これからの日本文明と「新しい人間観」
-
- 2004/6/28
- 国土・交通
国土政策をどう転換すべきか
-
明治国家に観る『分権論』
-
これからの人類に必要な「新しい人間観」とは
Keizo Maekawa

第24期
前川 桂恵三
まえかわ・けいぞう
前川建設株式会社
Mission
『地域主権型国家日本の実現』