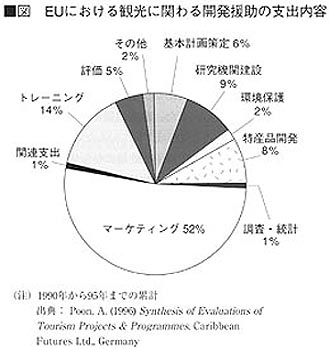Thesis
ポストバブルの企業協賛とメセナ 冨田勲コンサートと全英オープンを通しての一考察
冨田勲の「千年文化 源氏物語」コンサートのプロデュースに参加した詳細は先月の月例報告で紹介したが、その活動を通して一番痛切に感じたことは、スポンサー企業の思惑は各企業の企業理念からイベント協賛動機まで全て異なるわけだから往々にして一致することはなく、そのずれをいかに調整してそれぞれが納得した形に落ち着かせていくかというところにイベントプロデューサーとしての力量が問われるということである。
バブル全盛期を振り返ってみると、各企業とも財政事情に余裕があったため、社会貢献としての企業メセナも積極的に行われていた。また、広告代理店主導でイメージ先行の企業協賛も花盛りだった。日本でも企業メセナ協議会が1990年に発足し、ますます企業メセナ、フィランソロピーは企業の果たすべき義務のように扱われ始めた。
しかし、バブル崩壊後、各企業とも台所事情が悪化し、組織、および社員のリストラを積極的に行わなければならない状況になってからは、確実な宣伝効果の得られない企業メセナは敬遠されるようになってきた。
企業メセナの研究者は、企業は社会によって育てられているものだから、社会に還元しなければならないという理由で、バブル崩壊後の企業がまずメセナの予算を削減している動きを批判している。しかし、絶対に倒産しないといわれていた企業が相次いで倒産し、各企業とも、社員は給料が下がっただけでなく、日常の業務においても鉛筆一本、コピー用紙一枚まで節約するなど、血の滲むような思いでリストラ策を受け入れて働いているなかで、確実な宣伝広告効果の得られない支出が抑えられるのは当然である。
バブル時代にもてはやされた議論で、ジョンソン・エンド・ジョンソンが、
- ① 全ての消費者に対する責任。
- ② 世界中で働く会社員に対する責任。
- ③ 地域社会さらには全世界の共同社会に対する責任。
- ④ 株主に対する責任。
- ① 全ての消費者に対する責任。
を挙げたことや、資生堂が、
- ① お客様とともに
- ② 取引先とともに
- ③ 株主とともに
- ④ 社員とともに
- ⑤ 社会とともに
- ① お客様とともに
を挙げたことが優良企業の企業理念の代表として示されていた。このなかで、見返りを期待しない社会に対する還元を企業理念に謳ったことが評価されていた。しかし、一代でエンターテイメント業界、航空業界にその名を轟かせることに成功したヴァージングループのリチャード・ブランソン会長は、昨年出版された著書の中で、まず、お客様への還元、次に社員への還元、最後に、社会(株主)への還元と、順番をつけている。彼は、いくら社会に貢献しても、社員が喜びを持って仕事に向かわなければ業績は絶対に向上することはなく、業績が悪化すれば、結局社会への貢献は不可能になるとの持論を展開している。
英国にはアメリカに次いで歴史の深い企業メセナの組織、ABSA(芸術支援企業協議会)がある。ABSAの特徴として、今後の企業メセナの方針として、企業が見返りを全く期待しないメセナの形態であるDonation(寄付)や、何らかの見返りは求めるが、営利性が稀薄なPatronage(後援)といった形態からよりマーケティング性の強いSponsorship(協賛)に傾斜した方針を明確に打ち出している。企業メセナの活性化を図るためには芸術が企業に確実な利益をもたらすことを理解してもらうことが必要だとABSAは強く主張しているのである。この方針は企業メセナがより持続的に芸術振興に貢献していくことを現実的に捉えている。
「文化、芸術的視点で国家のアイデンティティを再構築する」のが私の政経塾における研修テーマだが、これは更なる文化、芸術振興のために公的資金投入の必要性を主張する議論では決してない。往々にして文化、芸術分野は利潤追求ではないことを理由に公的補助を期待し、それが満足に得られない場合、企業協賛に頼っているのが現状だが、公的機関、および援助する企業側に文化、芸術的視点がないと、資金援助すべき芸術、援助するに足らない芸術の見分けがつかない。寧ろ私は文化、芸術分野に更なる自助努力を求める。現状、芸術家は何らかの見返りを期待して援助する企業協賛を極力嫌い、出来ることなら公的援助に頼ろうとする傾向がますます強くなっている。しかし、芸術に対する公的援助も今とは比較にならないくらい不充分だった時代にまだ「武者修業」中であった小澤征爾はヨーロッパ各地で行われる指揮者コンクールに参加する資金が足りず、自ら各企業をしらみつぶしに廻って援助を求めた。結局富士重工と契約し、最新型スクーターの無償貸与を受け、それに日の丸の旗を立てて宣伝しながらヨーロッパ各地のコンクールに出向いた。そのエネルギーこそが、世界に通用する芸術を生む原動力となるのである。黙っていたら金が落ちてくる状態は芸術家を堕落させ、ひいては芸術振興に反する。
芸術家が何らかの見返りを期待する企業協賛を極力嫌うのは先ほど述べたが、電通ヨーロッパの一倉隆副社長によれば、企業は益々費用対効果を考えるようになっており、最近は企業も音楽に対する協賛よりもスポーツに対する協賛にシフトしている傾向が顕著になっているとのことである。確かに、観客動員数はクラシックの演奏会で1500-2500人しか集められない中、スポーツでは万単位で集客することが出来る。また、ロゴなどをふんだんに露出することが出来るのも大きい。加えて、ニュースや翌日の新聞など、間接的なパブリシティの露出度の高さも比ではない。
私自身今まで文化・芸術的視点で云々と並べる際、スポーツ協賛という部分は全く視野に入っていなかった。しかし、これは文化芸術を述べる時にも、確実に看過できない分野であることに気づいた。そのことを電通ヨーロッパの一倉副社長と意見交換した際、全英オープンの舞台裏を見る機会を与えてもらった。しかも、18番ホールのスタンド席でも観戦できるということで、一倉副社長とともにカーヌスティ・ゴルフ・リンクスへと向かった。
全英オープン会場、カーヌスティ・ゴルフ・リンクスに到着した。まずコースを廻ってみたが、いたるところに企業のロゴが見られる。旗、掲示板等、目が行くところには全て企業のロゴがある。選手が打つ直前になると「quiet」と書いてある黄色い札を5-6人の係員が出すのだが、それにもちゃんと企業のロゴが付いてある。選手の服にもよく見ると何かしらのロゴがある。タイガーウッズのナイキのマークはあまりにもポピュラーだが、各選手ともスポーツウェアのロゴ以外も数多くつけてプレーしている。加えて、クラブケースには各々クラブメーカーのロゴがでかでかとついてあるし、途中雨に見まわれたが、キャディーが持つ傘にも大きくロゴが描かれてある。しかし、そのロゴ群はデザイン的にスマートなので違和感はあまり感じられなかった。ここに6万人の観客が来て、しかもBBCでは朝から晩までずっと中継しているのである。夜にはニュースでハイライトが放映され、そして翌朝の新聞にはカラーで何枚も写真が掲載される。そして遠く海を渡って、テレビ朝日等、海外の放送局でも放映されているのである。世界中で何人の人が全英オープンを見ただろうか、想像を絶する。ここまでくれば企業もスポーツ協賛にシフトしてくるのは十分過ぎるくらい理解できる。
今回の全英オープンにおける収入の内訳は残念ながら入手できなかった。ここで、ロゴの多さといえばF1が代表的だが、先だってシルバーストーンで行われたF1のブリティッシュグランプリを例にとって見てみると、全ての支出に対し、入場料収入で15%、放映権収入10%、企業協賛で75%を賄うとのことである。今回の全英オープンもこれに近い数字であると思われる。
今回、企業が広告宣伝効果のあいまいな文化・芸術面での寄付、後援を打ちきった分、確実に宣伝効果のあるスポーツ協賛にシフトしているのを目の当たりにできた。文化・芸術分野、特にクラシックのオーケストラ運営においては企業からの資金援助が減少した分、国や地方自治体に資金援助の増額を頼る構図になっており、それが期待できない団体は経営難に陥っている。そして行政に対して文化・芸術面への理解不足を非難するコメントを出したりしている。しかし、援助を受けられない団体は座して死を待つだけでいいのだろうか。
私は経営難に陥っている文化・芸術分野にはむやみに公的資金を投入せず、更なる自助努力を求める。同じ入場料収入では全ての支出を賄うことの出来ないスポーツ興行をもっと見習うべきである。一つの方法として、企業は確実な宣伝効果を期待しているのだから、もっとロゴを露出するべきである。オーケストラのコンサートでいえば、まず入り口に協賛企業の製品を並べるのを認める。そしてホールに入っても、指揮台の下にロゴ、ステージの隅にロゴ、ボックス席にロゴ、演奏者の譜面台にもロゴを入れる。演奏者のステージ衣装にもロゴを入れろとは決して言わないが、ステージの譜面台や楽器の出し入れをする裏方の人々の服には大きくロゴを入れる。
このようなことを主張すれば、楽団側から絶対に反対が出るのは間違いない。そんな景観の悪い中で本当の音楽は出来ないなどと主張されるに違いない。まだまだ芸術に企業色を出すのははしたないとする意見も芸術の世界には根強く残っているのも事実である。
しかし、ものは考えようである。タイガーウッズの服についているナイキのロゴは「カッコいい」。マンチェスターユナイテッドのユニホームにつけば、シャープのロゴも「カッコいい」のである。(今ロンドンの街では、シャープの歩く広告塔が溢れている。)
私がJALにいたころ、JALは清水エスパルスを後援して、前面にJALのロゴが大きく入ったユニホームで選手はプレーしているが、ご承知のとおりJALは財政難に陥った。そこで清水エスパルスに後援の打ち切りを申し出たらしいのだが、清水エスパルス側が、他にも好条件のスポンサーは数多くあったにもかかわらず、前面に出すロゴのイメージでJALに勝る「カッコいい」イメージを出せる企業はないという理由でJALの継続が決まったという経緯があった。
「カッコいい」という言葉は日本語ではいささか時代遅れ的な単語で、時代の最先端的なイメージを表現するのに多少躊躇してしまうが、英国では今「Cool」という言葉でこの「カッコよさ」をうまく表現している。企業ロゴがCoolであれば、景観はロゴがないよりもカッコよくなる。世の中はCoolなデザインを期待している。
では、Coolなデザインとは如何なるものか。来月はデザインとアイデンティティについて考えてみたい。
さて、先月の月例報告で日本におけるインバウンドの観光を振興すべきであるということを述べたが、今回もその認識を新たにした。
予選の前日、全英オープン主催のThe Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A)と日本での放映権を持つテレビ朝日、その仲介役である電通、そして日本人選手達の交歓会に私も参加することが出来た。その中で、カーヌスティのチャンピオンシップコースは市議会が運営するパブリックコースであり、1975年まで全英オープンのローテーションに入っていたのだが、財政難で芝の状態等万全でなく、暫くの間ローテーションから外れていた。しかし、地元の強い要望でゴルフコースだけでなく、道路、橋梁等周辺の社会資本も整え、24年ぶりにローテーションを勝ち得ることが出来たそうである。確かに地元の歓迎ぶりはホスピタリティ溢れるものであった。宿泊施設が不足しているということで街でも空き部屋を持つ大家はテンポラリーのB&B(民宿)を開き、訪問客を歓迎した。 大動脈のハイストリートは交通規制され、ゴルフ関係者でない車は大きく迂回させられたにもかかわらず、不便を強いられているバスを待つ人までが訪問客に対して「次回は君がプレーする番だ。必ず戻っておいで。」と暖かい言葉を掛ける。ここまで気持ちがいいと、ゴルフをするためだけに、ほかに何もないこの村に戻って来たくなる。
私はこのカーヌスティの人々の取り組みを見るとどうも愛知万博の取り組みと対比して見てしまう。
どうも日本では宿泊施設が足りないとなれば大規模ホテルを乱立させる。しかし、ゴルフは数年毎に帰ってくるが万博は一度きりであり、万博終了後は空室が目立ち、それまで健全経営であったホテルまでもが経営難に陥る可能性が高い。
しかも、誘致が地元の人々の総意であるか否かは訪問客がホスピタリティーを感じるかどうか大きな分水嶺になる。どうやら愛知万博は名古屋の交通の大動脈である地下鉄東山線を利用しての交通アクセスを考えているようだが、一層の混雑で地元生活者が不便を強いられたときに訪問客に対して温かいホスピタリティーで迎えるとは到底思えない。余計にいやみの一つでも聞こえるように言うのではないか。そのような扱いをされたら訪問客は二度と名古屋の地を訪れることはない。観光地として成功するか否かは、一度のアピール性の高いイベントを成功させるかどうかではない。いかにリピーターを増やすかの一点だけである。日本はインバウンドの観光について、瞬間風速で測るような効果測定でなく、より持続的な見地で効果を考えなければならない。
島川崇の論考
Thesis
-
- 2001/1/29
- 国土・交通
日韓中文化観光推進協議体構想-政経塾の全過程を終えるにあたって-
-
地域文化資源を生かす観光開発のあり方
-
観光開発プロジェクトの問題点
-
- 2000/11/28
- 思想・哲学
空に太陽がある限り (c)浜口庫之助
-
- 2000/10/29
- 国土・交通
ツーリズムとイメージ
-
- 2000/9/28
- 思想・哲学
リバーダンスと民族のアイデンティティー
-
- 2000/8/29
- 国土・交通
国際観光コンサルタントの役割
-
- 2000/6/28
- 思想・哲学
ツーリズムコンサーンの取り組み(1)
-
- 2000/5/29
- 思想・哲学
心に田沢湖を (たざわこ芸術村・わらび座を再び訪れて)
-
- 2000/4/28
- 思想・哲学
What is Sustainable Tourism?
-
- 2000/3/29
- 国土・交通
サスティナブルツーリズムと韓国観光公社の活動
-
- 2000/2/27
- 国土・交通
MBAカンファレンス
-
- 2000/1/29
- 国土・交通
カジノ導入の功罪
-
インバウンド観光振興作戦!
-
- 1999/12/29
- 国土・交通
Sex Tourism and Hegemony Why is Sex Tourism not abolished and who profits from Sex Tourism?
-
- 1999/11/28
- 国土・交通
日本の観光業界の問題点 ~インバウンド観光振興作戦!(2)~
-
- 1999/10/29
- 歴史・文化・伝統
たざわこ芸術村・わらび座の活動
-
- 1999/9/28
- 国土・交通
日本の観光学序論 ―日本のインバウンド観光振興作戦!(1)―
-
- 1999/8/29
- 国土・交通
英国の住宅政策研究を通して感じたこと
-
- 1999/7/29
- 歴史・文化・伝統
アートリテラシー向上作戦
-
- 1999/6/28
- 歴史・文化・伝統
ポストバブルの企業協賛とメセナ 冨田勲コンサートと全英オープンを通しての一考察
-
- 1999/4/28
- 歴史・文化・伝統
文化・芸術的視点から日本のアイデンティティを考える
Takashi Shimakawa

第19期
島川 崇
しまかわ・たかし
神奈川大学国際日本学部国際文化交流学科観光文化コース教授/日本国際観光学会会長
Mission
観光政策(サステナブル・ツーリズム、インバウンド振興