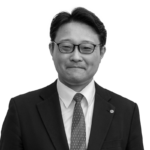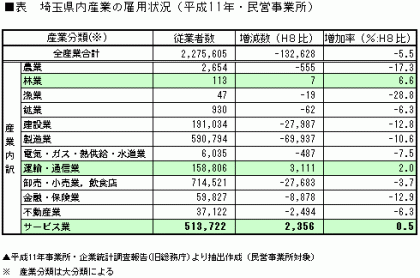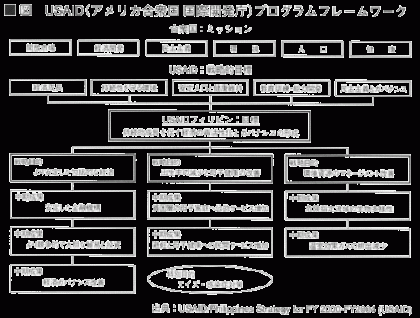Thesis
民主化進むモンゴルのNGO
0. はじめに
サハラ以南の最貧国債務の破棄が約束されたケルン、沖縄サミット、対人地雷禁止条約など、近年の国際的な意志決定には、NGOが大きな影響力を発揮するようになってきた。債務論議をリードしたイギリス、対人地雷のカナダのように、こうしたNGOと良き協力関係を築いている国がある一方で、日本外交は効果的に動けていない。
これには2つの原因があると考える。1つ目は日本国内におけるNGO、ひいては市民の脆弱さ、2つ目は日本政府と相手国の現地NGO、ひいては市民との直接対話の欠如である。
NGOの意思決定への参加というのは、国際会議の場だけに宙に浮いて存在しているわけではない。環境NGOの地球環境問題への積極的な提言の背景には、近所のゴミ拾に始まる国内での地道な市民活動がある。そして大気汚染の規制を求める市民の立法活動があり、それを積極的に受け入れる政府があり、という民主的土壌が国内社会にあるからこそ生まれてくる。この点、日本の国内社会における市民の活動、発言、あるいはそれを支える法制度などは、90年代半ば以降改善されつつあるとはいえ、まだまだこれからだ。
ある国家がNGOと協力関係を築けるかどうかは、その政府が市民とどれだけ対話する能力があるかにかかっている。それが他の国の市民であっても同じである。日本は世界一のODA(政府開発援助)拠出国であるが、相手国の政府を主な援助対象とした道路、橋などの大型公共事業は、その(途上国における)有用性にも関わらず、各国でNGOから激しい非難にさらされてきた。これは現地NGOとの関係作りにおける失敗によるところも大きい。
しかしながら、日本の苦手とする現地NGOとの関係作りは今後の外交上、非常に重要な部分になってくる可能性がある。特に現在、民主化が進むアジア諸国において、各国の政局に大きな影響を与えているのがこうした現地のNGOであるからだ。86年のフィリピン、98年のインドネシアのようにNGOがアジアの独裁政権が倒れる過程やその後の政治に大きな影響を及ぼす場合さえある。
前期研修を通じて、アジア諸国の現地のNGOとそれをめぐる政府、援助財団などのリサーチを行ってきた。本月例報告では9月?10月初頭にかけて行った、モンゴルでの活動を報告する。(7,8月のフィリピンリサーチについては『塾報10月号』参照)
1. モンゴルの民主化
「私達の世代は、失われた世代なのです。」
前国会議員(社会民主党)のナランゲル女史は低く、しっかりとした声で語り出した。「私の父も祖父も、共産政権時代の世代は、70年間も政府を恐れながら暮らしてきたのです。」
1921年の独立以来、モンゴルは長い間旧ソ連の衛星国であり、共産党の一党独裁体制が続いていた。
高校時代の彼女はジャーナリストを夢見る少女だったそうだ。しかし当時、共産政権下のモンゴルの教育システムでは、各校に電気技術者4人、教員6人、配管工5人などの割り当てがあり、校長が生徒を割り振っていくことになっていた。彼女は意に沿わぬロシア語教員になるよう告げられ、語学科の大学に行くことになった。
彼女はこう語る。「人と異なるものの考え方をすることができず、自由に自分の道を自分で決めることができない、そんな体制が良いわけがない。」
しかしそんなモンゴルにも80年代末に東欧を席巻した民主化が波及する。ソ連崩壊後すぐの92年に新憲法を制定、初めて多党制による第一回選挙が行われ、彼女も新しくできたばかりの民主派政党、『社会民主党』のスタッフとして必死に活動した。しかし結果はたったの2議席(76議席中)。結局、共産主義時代から71年間単独政権を続けてきた『人民革命党』が圧倒的な第1党(70議席)を続けることとなった。
彼女はこの結果を受け、まずモンゴルに民主主義の思想を根付かせることを優先しようと思い立つ。NGO『中央アジア開発財団』を設立し、各種の市民教育に関するセミナーや「民主主義をモンゴルの学校へ」を合言葉に中高等学校での民主化教育展開していった。またこの頃から海外で行われる様々な民主化、市民教育に関する会議やトレーニングにも積極的に参加し出した。
こうした地道な活動が実ったのか、96年の第2回総選挙で民主連合(『社会民主党』、『民族民主党』その他)は76議席中50議席を占めて圧勝した。この選挙で彼女も国会議員に選出される。その後、議員としての彼女の主な活動は『NGO法』の制定だ。選挙で選ばれた民主的政府だけでは片手落ち、NGOが育ってこそ真の民主主義だというのが彼女の持論だ。1997年1月に制定にこぎつけ、以来モンゴルのNGOは急激に増加し、法以前は600団体ほどしかなかったものが、現在登録済みの団体だけでも1580団体(2000年4月時点)を数えるまでなった。
その後政局は、民主連合政権の急激な自由化、民営化と福祉カットなどの政策が国民の不満を買い、再び弱者救済を掲げる『人民革命党』優位に戻った。(注1)しかし彼女は「たとえ国会が『人民革命党』一色になったとしてもNGOが声をあげて市民の意思を示せば、民主主義を守れるでしょう。」と語る。
2. 民主化を推進するNGO
モンゴル民主化の推進力の一つとなっているのが市民教育NGOだ。前述の『中央アジア開発財団』は『市民教育センター(Center for Citizenship Education = CCE)』と名前を変え、現在も活発に活動を行っている。『CCE』の作った市民教育テキストは全国の学校に配布され授業に取り入れられている。今年からは、民主主義の大事な要素「How to think」を身につけるよう、生徒たちが自ら問題を発見しどう解決するかをディスカッションする『Problem Solving Finding』コンテストも実施し始めた。また『全米教育者連盟』の協力を得て、全国の社会科学教師などを対象に市民教育トレーナーの養成を行っており、累計参加人数は1699人を数える。国中ほぼ全ての社会科学教師をカバーして、さらに他の科目の教師にも対象を広げている最中だ。
選挙に関する教育もさかんである。『Women’s for Social Progress(WSP)』は1992年に創立された、民主化と女性の平等を掲げたNGOだ。モンゴルのNGO全体を牽引しているのは女性NGOだが、その中には女性の権利問題以外にもこうした市民教育活動も並行して行っているところもあるのが特徴的だ。『WSP』は女性のための職業訓練センターやTV番組の作成以外に、各街で『選挙民教育プロジェクト』と呼ばれる活動を行っている。選挙の際には『WSP』が作った各政党の活動、綱領や立候補者の政策が分かる新聞が無料で配布され、街中に出まわる。それぞれの失業対策、環境などテーマごとに、各政党の政策の比較ができるようになっており、非常に分かりやすい。また今年からウランバートルに市民に広く開放した国会博物館を設立し、常時の国会中継(日本と違いTVで国会中継が行われるわけではない。)と法案等の資料の閲覧ができるようにした。
またこうしたNGOの教育対象は市民にとどまらない。地方政府や国会、政党を対象にしたトレーニングもさかんだ。モンゴルの民主化の歴史は非常に浅いため、まだ制度が固まってないためだ。『International Republican Institute (IRI)』は現在、国会の議会運営委員会とともに、選挙・政党関係の法律整備を行い、議会の手順や立法の仕方、草案作りなどで協力している。『IRI』は96年の選挙で、積極的に民主連合を支援し、地域での草の根組織作いや、資金を集め、選挙公約草案”Contract with Mongolian Voters”の作成などに協力する政党トレーニングを行い、民主連合の大勝に貢献したといわれている。
3. モンゴルNGOを支える海外支援
こうしたモンゴルのNGOを財政、内容の両面で支えているのは国際機関や北米、ヨーロッパ諸国からの援助機関だ。例えば前述の『IRI』モンゴル支部の政党トレーニングでは、本部のあるアメリカ合衆国の共和党から政治家や政党スタッフがボランティアでトレーナーを務める。96年選挙での民主連合の選挙公約草案”Contract with Mongolian Voters”も、アメリカ共和党94年国会選挙”Contract with America”をモデルに作成した。また財源の面でも、現在の活動資金はほぼ全て『USAID』(アメリカ合衆国国際開発庁)の助成金から得ている。
『CCE』の市民教育プログラムは『全米教師連盟』や『CIVITAS International』などの国際NGOが全面的に支援しており、『CCE』が各学校に配布するテキストもこうした団体が全世界向けに作ったテキストをもとにして作った。ナランゲル女史も『全米教師連盟』や『CIVITAS International』の主催する世界各国での会議やトレーニングに参加することで、自分自身も民主主義とは何かを学び、市民教育を行う様々なアイディアやノウハウを得たという。これらの会議やトレーニングプログラムは当時の『USIA』(アメリカ合衆国情報庁)の協賛で、財源を確保していたそうだ。
またモンゴルに現地事務所を持つ民間財団も重要だ。『Open Society Institute』は中東欧、旧ソ連邦などの旧共産圏を中心に活動している財団だ。別名『ソロス財団』という名で呼ばれており、その名の通り、ジョージ・ソロス氏の私財によって運営されている。ここモンゴルでは奨学金、インターネットの学校への普及、英語教育、健康教育などの活動以外に民主化支援もおこなっている。特にディベートやディスカッションの習慣を学校に定着させるための『ディベートプログラム』はユニークだ。また司法改革プログラムでは、モンゴル国立大学の法学部の支援や、裁判官のトレーニング、警察改革などにも参加している。
米国『アジア財団』は1954年の設立以来、アジア各国の法制度改革に取り組んできた。モンゴルではNGOの育成に特に力を入れており、1997年NGO法の際も米国から専門家を呼ぶなどして、その制定に貢献した。また前述の『WSP』の各地方支部と協力して『Participation in Local Decision making』プロジェクトを支援し、地方政府―ビジネス―NGOの3者が対話するCommunity集会を持ち各地で行っている。地方の立法にNGOやビジネスセクターのの意見を取り入れるためだ。特にウベハンガイ県では参加者の提言の半分が県の経済開発計画に採用されるなど、大きな成果をあげた。
この他にも、『カナダ財団』、ドイツの『コーナード・アデラード財団』、EUの『TACIS』などいくつかの財団が存在し、それぞれ活発に活動しているようだ。
4. 日本への示唆
冒頭で述べたように、日本外交の問題点の1つは、相手国のNGOや市民との関係作りが中々進展しないところにあると私は考えている。特にアジア諸国との外交においては民主化に大きな役割を果たす現地のNGOとの関係が非常に重要になる場合もある。現地のNGO、市民との対話を促進する援助戦略のあり方について、今回のリサーチを通じて気づいた点をいくつか述べたい。
まず第1に、北米、ヨーロッパの諸援助機関が行っている民主化支援の方法は日本にとっても非常に参考になると考える。現地で民間財団やNGOがパートナーとなるモンゴルのNGOを選び、積極的に支援していくのは非常に効果的な方法だ。この9月にはモンゴルのNGOの財政経営を支援するためのワークショップが『ピース・ウィンズ・ジャパン』と前述の『アジア財団』『CCE』の共催で開かれた。日本のNGOがこうした民主化、現地NGO支援の分野にも着手した例として特筆できよう。
第2に、現地のNGOを通じた民主化支援を行うには、日本自体の民主主義が脆弱ではないかという懸念についてである。確かにNGOの歴史という観点ではいささか心もとない。しかし逆に学び合う存在として日本と現地が関係を築ければ良いのではないかと考える。例えばモンゴルのNGO法は法人格のみならず、税控除も完備しており、日本のNPO法と比べより完成された形になっている。また選挙民教育などでは日本に取り入れたら良いと思われるアイディアも数多く見かけた。今回の財政経営ワークショップでも、アメリカ、フィリピン、日本の3カ国からの講師が参加したが、モンゴルのNGOから発展段階が似ている日本のNGOの説明が参考になるという意見も聞かれた。
第3に、内政干渉の懸念についてである。モンゴルの民主化では、多政党選挙もNGOもほぼ同時に進行してきたため、両者の人材が入り混じっていることが多い。実際多くのNGOは『民族民主党』『社会民主党』のいわゆる民主連合のいずれかから派生したといわれている。例えば前述の『IRI』も『民族民主党』との関係が深く選挙民教育も行っているにも関わらず、96年選挙では民主連合とのみ協力するなど(注2)、本来あらゆる政治勢力から独立した存在であるはずのNGOが、特定の政党と結びついてしまっていることが多い。こうした状況下でのNGOの支援は、下手をすると直接にその国の政治への介入につながることにもなりかねない。
世界的にNGOの影響力が拡大する中、外交においてこうしたNGOや市民と対話する能力は、今後ますます重要となってくると思われる。最近、日本においてもNGOの重要性がさかんにとなえられるようになったが、なお現在日本が国際社会で占めている位置からするとこの分野での力不足は否めない。日本国内におけるNGOの育成と、相手国のNGOや市民との良好な関係を作る援助体制を早急に整備する必要があろう。以上
| (注1) | 2000年総選挙では76議席中72議席を『人民革命党』が占めるという逆流現象が起こった。しかし『人民革命党』は既に共産主義とは訣別し、欧州流の社会民主主義を掲げる政党として生まれ変わっており、再び共産政権の時代に戻ることはないといわれている。実際『Political Education Academy』が選挙後行った調査によると5年前には60%しかいなかった「民主主義、市場経済に賛成か?」にYESと答えた人が80%に上昇している。 |
| (注2) | 2000年総選挙では『IRI』は政治的中立のため、全ての政党に対してトレーニングを行った。また他のNGOも時間の経過にともない、母体となった政党から独立した関係を保つようになってきている。 |
<資源環境大臣>
Ulambayar Barsbold
<前国会議員(社会民主党)>
R. Narangerel
<在モンゴル日本国大使館>
Fumiaki Tominaga (Consular) Akira Mizuno (Secretary)
<Center for Citizenship Education>
Undral Gombodorj (Executive Director)
<Liberal Women’s Brain Pool>
Uranchimeg B (Executive Director)
<International Republican Academy>
S.Bayar (Executive Director)
<The International Women’s Association of Mongolia>
D. Baljinnyam (Board member)
<Zorig Foundation>
Bulgan Banzragch (Executive Director)
<Mongolian Foundation for Open Society (Soros Foundation)>
Christopher Finch (Executive Director)
<Political Education Academy>
D. Ganbat (Executive Director)
<Women for Social Progress>
Chantsal (Program Officer)
<旧Foreign Loan and Assistance Agency, Prime Minister Office(現在組織変更)>
D. Tsevegdorj (元Japan Director)
<Gobi Regional Economic Growth Initiative>
Jennifer L. Butz (Program Director for Local Governance)
<ACDI VOCA>
Amanda Fine (Farmer to Farmer Veterinary Project Manager)
<Peace Winds Japan>
Yuichi Tanada (Senior Coordinator)
<Union of Mongolian Saving and Credit Cooperatives>
E. Tsoomoo (President)
<The Asia Foundation>
Katherine S. Hunter (Representative)
森岡洋一郎の論考
Thesis
-
- 2002/1/29
- 思想・哲学
日本の市民社会
-
埼玉を人の母港に
-
- 2002/1/29
- 思想・哲学
日本の市民社会
-
- 2001/12/29
- 思想・哲学
『ボランタリーな個』の時代
-
- 2001/11/28
- 思想・哲学
サラダボウルの世界
-
- 2001/10/29
- 国土・交通
『ベッドタウン』は『寝床』じゃない!
-
- 2001/9/28
- 労働・雇用
『やり直しの教育』~失業と職業能力開発~
-
NPO時代をどう迎えるか?
-
- 2001/2/26
- 経済・産業
『NGO』をどう考えるか? ~国際農業交渉における『NGO』~
-
- 2000/12/29
- 思想・哲学
“政治家”をめぐる考察
-
- 2000/10/29
- 外交・安全保障
真に日本に資する援助とは?
-
海外援助に現地NGOの活用を
-
- 2000/8/29
- 外交・安全保障
民主化進むモンゴルのNGO
-
- 2000/7/29
- 外交・安全保障
支援国の市民との対話
-
- 2000/6/28
- 思想・哲学
NGOと民主制
-
- 2000/5/29
- 思想・哲学
カナダ ~多元社会の民主主義から~ その3
-
- 2000/4/28
- 外交・安全保障 ダイバーシティ・ジェンダー
カナダ ~多元社会の民主主義から~ その2
Yoichiro Morioka

第20期
森岡 洋一郎
もりおか・よういちろう
公益財団法人松下幸之助記念志財団 松下政経塾 研修部長