Thesis
「君はスーパーオヤジを見たか?」
日本中で「観光カリスマ」ともてはやされることを殊の外嫌がる清里のスーパーオヤジ舩木上次。これは、その照れ笑いの奥に隠された熱いロマンを、ふた月におよび舩木氏に密着した筆者の目を通して綴った奇跡の人間録である。
真夏というのにもう空は暗い。八ヶ岳南山麓の夜は早いのだ。静寂の中で、正面にうっすらと木立の影がさざめいている。
空にはたくさんの星が見える。今日も晴れてよかった。あんなに昼間は暑かったというのに、さすがは海抜1200mを超える高地だ。気がつけば、なんだか肌寒い。
暗闇の中に、スポットライトが突如浮かび上がる。
主役のダンサーが、静かにゆっくりゆっくりとステップを踏み出しながら、舞台奥からやってくる。静かにモーツァルトの楽曲が流れる。芝生の上の客席からどよめきのような喝采が沸き起こる。
ここは山梨県北杜市高根町清里、萌木の村。この夏で17回目を迎える「フィールドバレエ」の会場だ。その名の示すとおり、「フィールドバレエ」は、野外のバレエ公演。萌木の村株式会社代表取締役社長・舩木上次と、元バレエダンサーで、今もこの萌木の村で八ヶ岳高原の子供たちにバレエを教える妻・洋子、そして、洋子の友人で日本を代表するバレエダンサーの今村博明、川口ゆり子の着想により、17年前に始まったのだ。
今回は、モーツァルトの生誕250周年、さらには前年がアンデルセン生誕200周年ということもあって、バレエ創作の旗手でもある今村博明により、アンデルセンの原作に、モーツァルトの楽曲を乗せたオリジナル作品「おやゆび姫」も演目に入っている。また、舩木の趣味が高じて出来たオルゴール博物館の先駆け「ホール・オブ・ホールズ」の世界屈指のコレクションの中から、モーツァルトが自動オルガンのためだけに作った作品「モーツァルト・自動オルガンのための幻想曲ヘ短調KV608」を演奏する世界にたった一台のアンティーク自動オルガンの演奏に乗せて踊る「バレル」なども演目に加わり、野を越え山越え県境越えやってきた並み居るバレエファンをも唸らせる内容だった・・・、らしい。
その場に居合わせながら、「らしい。」とつけたのは、他でもない。小生が、これまでバレエの「バ」の字も知らなかった、舞台はおろかテレビですらちゃんと(お、綺麗なお姉ちゃんが踊ってるぞ、くらいにしか)見たことのない、ズブの素人だったからだ。
ズブの素人がなぜ「その場」にいるのか?
決して、綺麗なお姉ちゃんを間近に見たかったからではない。いや、その気持ちが全くなかったといえば嘘になるが、少なくとも、それが動機ではなかったし、実際その場は、綺麗なお姉ちゃんに声をかけられるような雰囲気でもないし、小生は、そもそもそんな立場にいなかった。その場所は、まさに神聖な雰囲気に包まれており、バレエダンサーはその中で、男と女とを問わず、みな神々しい光彩に包まれていた。それは本当に美しく、目を奪われ、体の動きまで奪われてしまう、といったものである。
しかし、小生には、体の動きをとめることも、じっと美しいバレエのステップに見とれていることも許されなかった。なぜならば、小生は裏方だからである。しかも、舞台のことをロクにわかっていない使いっ走りのペーペーなのだ。舞台袖で道具の出し入れを手伝ったり、皆で「せり」を上げるのに加わったりと、演技に夢中になっていては舞台を台無しにしかねないのである。いや、ちょっと言い過ぎた。そこまでの危険かつ重要な任務はペーペーには与えられない。とにかく舞台に気を取られていてはいけない。かといって、舞台の進行をちゃんと把握していないと、これはこれでやっかいで、うっかり自分の役目をすっとばしかねない。お掃除をするカエル役のダンサーに、肝心のホウキを渡し忘れたりする。ホウキを忘れて職務ホウキ、である。カエルも顔を真みどりにして怒るに違いない。そうなったら「喧嘩両生類」とか言って逃げカエルしかない。
こんな小生にも、一世一代の出番がやってくる。そう、舞台に立つシーンがあるのだ。天与のスター性が認められたのだ。と言いたい所だが、バレエの世界は、そんなに甘くはない。バレエ団は、言ってみれば芸術界の陸上自衛隊のようなものだ。(詳しくは述べない。)小生の出番というのは、大道具と小道具の中間くらいのいわば中道具の中に、池を浮遊するハスの葉っぱ(ベニヤ合板製、キャスター付、手作り)というのがあるのだが、腰をかがめて客席から体の見えぬようにしながら、そいつをゆっくりと動かしていくというものだ。つまり、小生であってもなくても、まったく舞台には影響しないし、客席の誰一人として、どのハスの葉っぱが小生であるかは判別することができない。それでも、この舞台に立ち(座り、か)一瞬でも作品の一部になりえたのだ、という思いは、小生の中にこの上ない歓喜と感動と誇りを呼び起こした。
それが何故か、そして、なぜ小生がホウキを気にしたり、ハスになって漂ったりしているのか、ということについて、そろそろ言及せねばなるまい。
清里の舩木上次は、既述の通り萌木の村株式会社社長、57歳(当時)。妻一人息子二人。清里で生まれ育ち、清里を愛し、講演で全国を飛び回りながらも、清里をベースとして決して離れようとはしない生粋の清里人だ。
清里といえば軽井沢とならぶ避暑地。白亜のペンションやファンシーなお土産物屋の立ち並ぶ一大リゾートを想像する方も多いのではないだろうか?
6月、ある方の紹介により、舩木氏のもとを訪れることになった小生も、正直そんなイメージを抱いていた。「日本は、放っておいても東京からお金を運んでくれるようなそんな恵まれた土地ばかりではないのだ。」という引っかかりを心の隅に隠して、列車を乗り継ぎ、乗り継ぐたびに大気の温度が下がって行くのを感じながら、清里へと足を急いだ。清里駅に降り立ち、まずあることに気づいた。駅周辺のイメージが、想像と少し、いやかなり違うのである。まだ昼間というのに、人影がまばらで、シャッターを下ろした店も少なくない。開いている店も、「もう流行っちゃって、流行っちゃって。」と店主の笑みがこぼれるのが見えてきそうなものは一つもないといってよい。まだシーズンには早いウィークデーであることを思いながら、出迎えの車に乗って、萌木の村へと向かった。そして、いよいよ舩木上次と初対面することになる。舩木氏は、スーパーマンのTシャツを着て現れた。後になって、この胸に大きなS字のシャツが、氏のトレードマークだと知る(なんせ色違いを何枚も持っていて毎日着てくるのだから)のだが、とにかくこの対面の瞬間より、それまで小生の心に引っかかっていた煮え切らない思いはどこかへ吹き飛んでいき、この「スーパーオヤジ(コスチュームも中身も!)」の熱狂的なファンへと化していくのである。
舩木氏の魅力は数多い。会えば誰でも惹かれるものに、その類まれなる愛嬌がある。始終相好を崩したその笑顔は、微塵の屈託をも感じさせぬ。数分も話をすれば、その表情にたがわぬ心のぬくもりを感じることになる。仕事の話をさせれば、絶えずゆるませたその口元から次々とアイデアが飛び出してくる。日常のなんでもない出来事も、氏にかかれば魔法のように面白くなってしまう。氏の周りに沢山の人間が集まってくる大いなる所以であろう。
小生は、氏に付いて、氏がアドバイザリーをつとめる地域イベントの協議会やフィールドバレエの協力要請、萌木の村の会議や早朝の芝植えなどにお供をしながら、氏と対話を重ね、前述「心のぬくもり」のわけが、単に舩木氏の持ち合わせた天分に負うところばかりではなさそうだ、ということに気づいた。と同時に、すっかり忘れていた清里という土地に対する自分のイメージの間違いに気づかされることにもなる。
スーパーオヤジ舩木上次は、57年前にこの萌木の村のある清里の地に生を受ける。父は清里を開拓した開拓団の中心人物。舩木の父をふくむ開拓団は、80数年前、東京都の水瓶としてダムの底に沈むことになった村から追い立てられるようにこの地にやって来た。清里という土地は八ヶ岳南山麓の寒冷地で、岩場が多く、わずかな耕作可能地も痩せに痩せている。こんな土地には蕎麦しか育たない、と舩木の父親たちは蕎麦を育て始めるのだが、その蕎麦すらろくに実らない。そんな過酷な状況下の中で、彼らの共同体意識は、日増しに強くなったことであろう。彼らは、最初の年に一つの穂に三粒の実しかならなかったこの蕎麦を前にして「一粒を来年の種とし、一粒を自分たちの糧とし、いま一粒は人をもてなすことに使おう」と決めたという。
そこに救世主のごとく現れるのが「清里の父」ポール・ラッシュ博士である。ラッシュは、米国聖徒アンデレ同胞会の宣教師として来日し、立教大学などで教鞭をとっていたが、アンデレ会の活動の一環として日本に指導者訓練のためのキャンプ場をつくれという指令を受け、候補地の一つとして清里の地を視察に訪れた時、八ヶ岳南麓の壮大な景色を目の当たりにして胸を震わせた。この地に「キリスト教精神に基づく農村コミュニティ」を創設するのだと決心したラッシュは、本国へ何千通もの書状をしたためて、ついには帰米して人々を説いて回り、苦心惨憺の末、「清泉寮」を作るのである。しかし、ほどなく日米が砲火を交え、その影響は日本にいる一宣教師にも及ぶことになる。ラッシュは、帰国を余儀なくされ、必ず戻ってくることを約して清里を去る。
戦争が終わりを告げ、GHQの一員として、約束どおり再び日本の地に降り立ったラッシュは、焼け野原になった日本に衝撃を受ける。日本の復興に貢献したいと考えた彼は、退役後清里に舞い戻ってくる。清泉寮を中心に、清里農村センター「キープ協会」を創設し、『食糧』、『保健』、『信仰』、『青年の教育』という4本の柱を掲げて実践的な農村コミュニティのモデルを目指したのだ。これは、戦争で荒廃した日本の町や村に希望を与え、民主主義を農家に定着させる試みでもあった。その後、ラッシュは、米国やカナダの市民に支援を求めながら、教会、高冷地実験農場、農村病院、農村図書館、保育園、農業学校などを次々と完成させていくことになるのである。清里の開拓民は、初めて見るジャージー牛にとまどいながら、ラッシュの指導の下、酪農を中心に、寒冷地に適した農業を学んでいくと同時に、ラッシュによる精神、文化、学問の薫陶を受けることになる。
幼き日の舩木少年は、ラッシュのもとに毎日のように通い、身の回りの世話を手伝いながら、言葉はわからないながらも、ラッシュが人々を導く姿や、父を初め住民たちの奮闘、成果を得て喜びを分かち合う光景から、ラッシュの伝えようとするものが何であるかを体で感じながら育ったのだ。
時は流れ、舩木青年が、東京の大学を中途に切り上げて、八ヶ岳をのぞむこの地に戻ってきた日から、今日「観光カリスマ」と、全国の地域おこしを志す人々から推戴される舩木上次の躍進が始まる。
自分の生まれ育ったこの土地には、自分と同じようにエネルギーを持った若者たちがその有り余るエネルギーを発散できる場所がない。そう感じた舩木は、ないのならば自分で作ってしまえと奮起し、1971年、山小屋風の喫茶店「ロック」を開業して、そこで様々なイベントを開催した。観光施設などではなく仲間作りの拠点だったという「ロック」は、やがて、東京から著名なアーティストたちがふらりとやってくるような若者たちの聖地となっていった。夢とアイデアの尽きない舩木は、「ロック」の成功に飽き足らず、78年、ドイツの山荘を模した「ホテル・ハットウォールデン」を開業する。舩木の志向するところは、都市文明の発展の中で一早く自然との共生を訴えた19世紀の哲人H・D・ソローの小屋にちなむそのホテル名に表れている。ホテルの開業と時を同じくして、それまでほとんど注目という注目もされなかった清里に、雑誌の特集をきっかけとして、空前のブームが巻き起こる。森や農地、牧草地が次々に開発され、別荘やペンションや土産物屋となっていく。たくさんの観光客がやってくる。当然、舩木もその恩恵に預かることになる。
しかし、住民たちの狂喜する声を背に、舩木は一人違和感を抱いていた。
「こんなのは、どこかの真似事に過ぎない。駅前を見ろ。ミニ原宿が出来ている。客はどんどん来るが、ポール先生の愛した、そして親父たちを受け入れ、俺たちを育ててくれた森はどんどん失われていく。ポール先生は、清里がこんな形で繁栄していくことを望んだだろうか。」
ブームはブームでしかない、と感じとった舩木は、ブームに惑わされることのない、清里の風土を活かした清里に長く根付く文化づくり、地域づくりを志すようになっていった。ラッシュの遺志が、舩木の体に乗り移ったといってよい。
こうして、新生"ポール"舩木は、父親が息子の牧場用にと遺してくれた土地に、清里の自然を活かし、手作りの仕事が根付いていく場所を作り始める。「萌木の村」である。
現在までに、陶芸の窯元や、木工の店、数々の表彰の栄誉を受ける地ビールのブリュワリーに、前述のオルゴール博物館と、併設する手作りオルガン工房など数多の工房・店舗を擁し、さながら、一線級の職人を集めた、自然の中の職人テーマパークの様相を呈している。
しかし、いいことばかりではなかった。「むしろ、悪いことのほうが多かったかもしれないよ。」スーパーオヤジが、スーパー笑顔をさらに崩して小生に告白する。
バブル経済は、ラッシュがその生涯を捧げた清里を、一層の濫開発と投機の対象に仕立て上げていったが、萌木の村もその波から免れることは出来なかった。萌木の村の目指す姿とは対極にあるような性格の遊興施設や飲食店の開業計画が、隣接する土地に次々と持ち上がった。その度に、舩木は反対運動を起こしたが、いくら声を荒げても、今や日本人の心を捉えて離さぬ市場主義の魔力には到底抗うことなどできず、結局、舩木はその度に多額の借金をして、計画の土地を買い戻していったのだ。こうして、意図せずして萌木の村の面積は大きくなったが、借金の額はそれ以上に大きくなっていった。それでもまだバブル景気の続いている間は客足が絶えず、借金返済のメドがたった。
ところが、である。そのバブル経済の泡が、膨らみに膨らんだ泡が、ある日突然弾け飛んだ。「ブームは長続きしない」と警鐘を鳴らし、ブームとは異なる道を探らんとし、その道を多額の負債を抱えてまで守らんとしたその男の予言どおり、ブームは掻き消えた。予言者の前には、多額の負債だけが残された。ブームが去っても生きられる力を地域にもたらそうとしたその男の取り組みに、運命の女神は微笑まず、その代わりとして、皮肉な、としか表現しようのない試練を与えた。
「俺は経営のセンスがねえんだよ、先生。」「『先生』はやめてください、先生。」
この清里のオヤジは自分に課された過酷な境遇を、まるで冗談でも話すかのように、大笑いしながら小生に語るのである。小生は、その笑い声に、何ともいえぬ哀愁を嗅ぎ取りながら、ますます人間・舩木上次を好きになっていくのを感じた。
清里は、それまでのブームが嘘だったとでも言うかのように、客足が途絶えた。舩木の幼なじみをはじめ、清里でブームに浸った仲間たちが、全てを失って生まれ育ったこの土地から逃げるように出て行くのを舩木は悲痛な思いで見ていた。悔しかった。
現在もその状況は変わっていない。小生が清里駅に降り立った時のあの何とも心細いような印象は、決して勘違いなどではなかったのである。小生がここに来る前に抱いていた一大リゾートのイメージなどは、もう20年も過去の姿なのだ。そして、世の中の大半の人が、小生と同じ20年前のイメージを、いまだにこの土地の名の持つ響きに抱いているに相違ないであろう。
舩木は、バブル崩壊の爪あと、というよりも、皆が浮かれたバブルにひとり抵抗した爪あとから立ち直るために、必死に戦った。
萌木の村の従業員を守るために、萌木の村を死地から救い出すために、ポール・ラッシュの火を消し去らないために、そしていずれは、この土地を出て行った仲間たちを呼び戻すために、舩木は踏ん張った。
それまでの方向性を少し修正して、萌木の村にテナントを受け入れ、収益を上げる努力をした。しかし、そのことを後悔しているのだと舩木は言う。「清里にしかないものを作る」はずが、「どこかで見たことのあるものを売る」場所に変わっていった、と言うのだ。「もっとも、生きていくためにそれしか方法がないと、その時は思えたんだがね。」とも付け加えた。廃れる一方の清里の中で、一見、一人気を吐くように見えた萌木の村と笑顔を絶やさぬ舩木に、羨望とやっかみの声が囁かれたが、内実は決してそんな甘いものではなかったのだ。
今なお、舩木と萌木の村の抱える負債は決して小額ではないが(※このことは本人が公然と言っているので、名誉毀損や業務妨害にはあたらない、と思う。)、様々な努力、トライアルが実を結び、年々業績は改善している。辛く苦しい時期を(今もそうだと本人は言うが)乗り越えられたのは、ラッシュと開拓民が自分に刻み付けてくれたマインド、そして、仲間があったからある。
家族、地域の住民、萌木の村の従業員、仕事の仲間・・・、数え切れない仲間たちが、舩木の周りに集い、舩木に支えられ、舩木を支えてきた。
そして、たくさんの仲間の思いが一つになるのが、年に一度の一大イベント、冒頭に掲げた「フィールドバレエ」である。当初は、3日間で数百人(バレリーナ目当ての地元のお父さんたち)しか集まらなかったイベントも、回を重ねるごとに講演、観客動員とも規模を大きくし、今回は、13日間の公演に1万人を越える有料入場者が押しかけた。
しかし、これだけ成長したのだから舩木の事業が潤うのかというと、決してそうではない。フィールドバレエは、どこからも助成を受けず、全て持ち出し。それどころか、このためにただでさえ負債に悩む舩木が新たな借り入れを行う。
なぜ、そこまでして続けるのか?
しかも、舞台は全て手作り。何もない芝生の広場に、毎年、地元の大工を中心に、沢山の職人たちが集まり、一月かけて見事な舞台を組み上げ、公演が終わればまた解体する。舞台づくりのノウハウは年々高まってくるが、バレエという極度にデリケートな舞踏をダンサーが安全に演じるに堪える舞台を毎年作っては解体していくというのは、コスト的視点から見れば、議論の俎上にすら上らない物である。さらに、この舞台には、屋根がない。舞台の水はけのこともさることながら、雨天では、公演が出来ないのだ。もちろん、その日に見込んだ入場客はゼロに帰す。だからいって、東京からやって来たダンサーたちを含め、期間内にかかる費用は固定で、一日分とてゼロにはなってくれない。
なぜ、そこまでして野外バレエにこだわるのか?
これら当然とも思われる疑問に対し、舩木は、平然と、一点の曇りもない眼差しでこう答える。
「劇場でやるバレエは、安心・安全のバレエだ。常に100のものを見せられる。フィールドバレエは、雨が降って0になるリスクもあるけどさ。雨が降んなきゃ、満天の星空やら、涼しい風やら、澄んだ空気の演出効果が出て、その魅力は、150にも200にもなる。こんな面白えものはねえら?清里は、せいぜい80年そこそこの歴史と文化しかねえんだよ。もともとあった伝統なんてえのは残念ながらねえんだよ。そしたら新しく作るしかねえら?でも、いくら新しくっつっても、借りもんじゃだめなんだよな。清里の風土に合うものじゃねえと、意味ねえんだ。根付かねえんだよ。清里には伝統芸能も祭りもなかったが、ラッキーなことに八ヶ岳のでっかい自然があった。森や水や空や空気があったんだよ。ここには森の精が住んでいるんだ。今村先生が最初にここに来たときに、ここから八ヶ岳を見て、ここで野外バレエをやりたいって言い出したときは、俺はこれだと思ったね。まさに清里の空気にピッタリな文化だ。フィールドバレエは、森の精を讃える祭りさ。この土地にきっと根付いていく、って思ったから、こりゃ、何が何でもやんなきゃ、って思ったんだよ。」
それでも、舩木のそんな思いはなかなか通じず、住民の中には「儲け主義の独りよがり」だと中傷したりするものもおり、せいぜい「変わり者の舩木がまた変なことをはじめた」くらいにしか見られていなかったと思われる。ところが、舩木の志すところは「儲け主義の独りよがり」とは対極の「地域の文化的支柱作り」にあったのである。
もっともフィールドバレエは、経済的にも、むしろ地域に還元できるものとなってきている。清里の地盤沈下の中、2005年は、開催期間中に4000人の観光客が地元に宿泊したという。
「フィールドバレエは、おれっちの事業としては赤字かもしれねえけどさ。地域全体から見れば黒字になんだよ。その意義は大きいぜ。」
と、むしろ自分のほうが得をしたかのように、舩木は笑みを浮かべて話す。
「短期的に見れば、自分の事業が大切かもしれねえけどさ。長期の視点で見りゃ、地域の活性化が必要なんだって。」
それが、このイベントを存続せしめる一つの大きな動機付けになっている。
そんな舩木の思いに、まず舞台づくりを担う地元の大工たちが、感染した。毎年時期が来ると、その他の仕事をそっちのけで舞台づくりに精を出す。公演期間中は、舞台を作った同じ大工たちが、ほぼボランティアで裏方を仕切る。舩木の思いに触れ、そして、言葉以上に、実際に八ヶ岳の空気とバレエダンサーが織り成す荘厳なる光景を見せつけられた彼らは、この仕事に携わることに誇りを感じると異口同音に語る。
地元の学生や、舩木を信奉する若者たちもまた、フィールドバレエの舞台づくりに、いや舩木と清里の夢の舞台づくりに、一役買いたいとボランティアでやってくる。かくいう小生もまたその一人である。
今村博明と川口ゆり子率いる日本屈指のバレエ団「シャンブル・ウエスト」の面々もまた舩木と清里とこのすばらしいイベントの虜になった。経費もままならぬギャランティーも関わらず、どのダンサーも口をそろえて、この舞台に立つことが楽しみだ、と言うのだ。
舞台の上のダンサーと、影で支えるスタッフ、そして主催者の強い思いは、客席に伝播するのであろう。幕が下りた後も(実際には野外ステージなので幕はないのだが)、何ともいえない余韻の中で、満ち足りた表情を浮かべながら、名残惜しげに会場を後にする。ほとんどの客が「また来たい。」と言う。事実、リピーターは年々増えているのだ。どころか、フィールドバレエを永久に襲い続けるであろう不幸な「雨天中止」に出くわした客ですら、「この(公演の行われない)舞台を見られただけで、なんだか嬉しいです。来年必ずまた来ます。」と言って帰っていったそうだ。
また舩木が、財政的理由からイベントの将来について悩みを抱え、「正直ちょっと疲れちゃったな。そろそろいいかな。」という考えが頭をよぎったときに、叱咤となったのもまた一人の観客の言葉だったという。
その女性の客が、公演終了後、舩木に近寄って語った言葉は、舩木の胸を音を立てて貫いた。
「私は末期癌患者です。今日このフィールドバレエを見て、癌を患ってから初めて生きていて良かったと感じる事ができました。あと数ヶ月の命と思っておりましたが、来年もう一度このバレエを見たいので頑張ります。本当に有難うございます。」
笑い顔の舩木の頬を涙がつたった。「本当の限界になるまでは、やめちゃいけねえ。」と感じたという。
舞台と舞台裏と観客席。三位一体となって、八ヶ岳山麓の清涼な空気、満天の星空、森の精の宿る木々のさざめきたちと協奏し、世にも美しい幻燈を浮かび上がらせる。
この充足感に溢れた時間と空間は、人を呼び、そして人がまた人を増やしていった。最初は訝る様な目で遠巻きに見ていた地域の人々も、関係者や観客の幸せな表情や、実益として地域に落として行く来場者による経済効果に、徐々に態度を軟化させてきた。そして、「フィールドバレエ」を当て込んだペンションの宿泊プランなども登場してきたという。
「なんだ、散々文句言っといて。都合のいいときだけ、利用しやがって。」とは、舩木上次は言わない。なぜならば、「フィールドバレエ」が地域のイベントとして根付き、地域がそれによって息づくことが舩木の望みだからだ。利用されることはむしろ舩木の喜びなのである。舩木がもっとも待ち望んでいた地域がようやく振り向き始めた。
「バレエなんざ、しゃらくせえ。そんな西洋の文化が日本の土地に根付くはずはねえ。」
というあなた。だまされたと思って、来年(2007年)の夏、清里に行ってごらんなさい。きっと、再来年もまた足を運んでますヨ。
それほど、この土地と空気に、このまだヨチヨチ歩きを始めたばかりの文化は、マッチしている。そして、徐々に、本当に少しづつではあるが、着実に、地域の文化として根付き始めている。
この夏は、それまで棟梁の下で、手足として舞台づくりを担ってきた清里育ちの若い職人・奥野直樹氏が、舞台づくりの総監督を自ら買って出た。奥野は言う。
「俺たちの世代が担っていかないと、駄目だと思うんだよね。」
小生は、笑みを禁じえなかった。舩木オヤジのDNAが、ポール・ラッシュの魂が、ここにも受け継がれている。
最後に、ポール・ラッシュの遺した言葉を引用してこの稿を締めくくりたい。
"Do your best, and it must be first class. "
この言葉は、「最善を尽くせ、しかも一流であれ。」という訳とともに、清里のそこここで目にする。
しかし、小生の耳には、なぜだかどうしても「最善を尽くせば、必ず一流たりうる。」というように響いてならない。その方が、ポール・ラッシュのたどった足跡や、開拓者たちの汗のにおいが、ありありと浮かんでくるのだ。
そう、ちょうどスーパーオヤジ舩木上次の、地域の文化の支柱作りが、そうであるように。
私もまた最善を尽くす一人でありたいと思う。
兼頭一司の論考
Thesis
Kazushi Kaneto
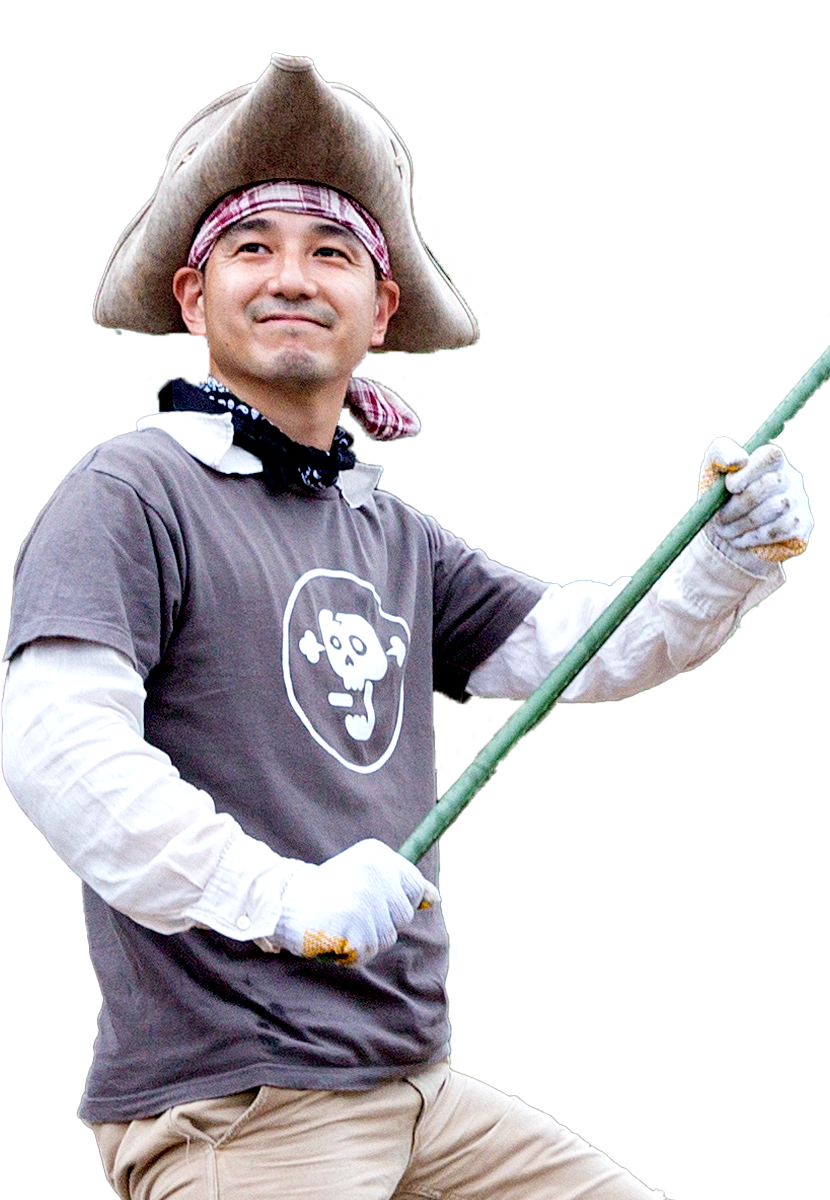
第26期
兼頭 一司
かねとう・かずし
株式会社空と海 代表取締役/海賊の学校 キャプテン



