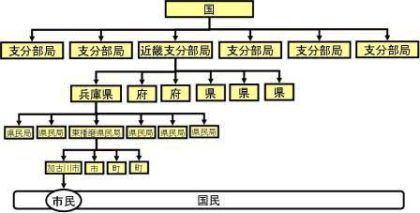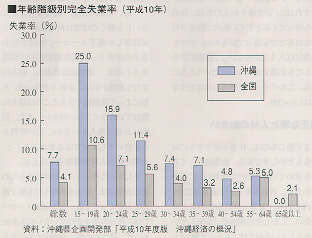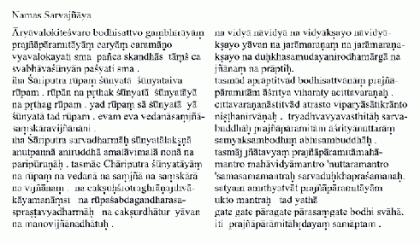Thesis
55年体制・失われた10年・その次に来るもの
戦後の日本を支えてきた「55年体制」は、1993年総選挙で自民党の大幅な過半数割れによって一応の終止符を打った。しかし、その後数年を経た現在も、日本の政治は変わりそうで変わらない。 ここで、日本の政治に大きな影響を与えた「55年体制」とはどのようなものであったのかを歴史的な観点から振り返り、今後、日本がどのような改革をすべきかを考えたい。
「55年体制」が機能した時代(~1970年代)
何かと否定的に語られることの多い「55年体制」だが、このシステムは1970年代までは日本の成長に極めて有効に機能した。自民党と社会党による激しい対立が繰り広げられた1955年~70年代は、日本の政治シーンに競争的な政党政治が展開された時期である。そのため、池田内閣以後の自民党内閣は、支持基盤固めの最も有効な方法として経済発展を至上目標とする吉田茂の路線を踏襲した。その戦略はあたり、自民党の打ち出した様々な政策は経済発展を促し、自民党の基盤を広げることに成功した。一方、優秀な人材を抱えた大蔵省や通産省などを中心とする行政も、合理的な産業政策を絶えず実行することによって産業構造の向上を図り、経済の急速な発展に貢献した。
このことを、創価大学教授の綿貫譲治氏は「1955年から60年の間、一方では政府(ことに通産省当局)の誘導――基盤産業としての鉄鋼、電力、輸送(ことに海運産業)に対して引き続きなされた便宜の供与、新規重要産業に対する育成――、他方では、それに呼応する私企業の旺盛な設備投資とにより、重化学工業は急速に進展していた」(注1)と指摘している。
加えて、「55年体制」下の政・官・財の象徴的な関係として、政と官の経済計画や、官と財の産業政策がある。国際的な大製造業を中心とする財界は、莫大な政治資金や人脈を駆使して、主に与党を通じて政策決定過程(特に経済政策の決定過程)に強い影響力をふるった。このことを最も象徴するのが、1962年に通産省が提出した「特定産業の振興に関する臨時措置法」であろう。同法案は、行政が企業に対し統制経済的な力を持つことを意図したものだが、財界が市場経済の維持と自由な発展を求め、その成立を阻止した。これによって日本企業は国際的な強い競争力を持つことになり、現在の日本を支える巨大企業へと成長することができた。
55年体制の変質と弊害(1970年代~)
70年代以前には有効に機能していた「55年体制」も、70年代以降はむしろ発展の阻害要因となった。日本が西側諸国で2番目の経済大国になった70年代以降、政府は本来ならば民間の活動を活発にするために行政の役割を弱めるべきであった。ところが実際に政府が採ったのは、行政の役割を強化する方向であった。
この時期の政・官・財の関係を見てみよう。政策決定過程で発言力を強めた与党自民党は、獲得した利益誘導システムを維持するために行政の力を弱めなかった。さらに、農業・流通・建築などの利益集団も、その既得権益を守るためにこの方針を積極的に支持した。こうして自民党・行政・財界は強固な協力関係である「政官財の鉄のトライアングル」を構成すると公共事業のばら撒きを行い、経済発展に負の影響を及ぼし始めた。具体的には、金融・流通・建築などの各業界を手厚く保護をしたために、生産性が上がらず、国際競争力が低いまま温存されることになった。それはまた、閉鎖的な国内市場を創り出すことになり、貿易摩擦や内需不足の原因となった。
さらに、55年体制の負の側面は、日本にとっての戦略産業である情報産業にも及んだ。コンピューター産業は通産省の主導のもとで大きな発展を遂げていたが、コンピューターと通信を結びつける情報産業の主導権を巡り、通産省と郵政省が激しい争いを演じた。その結果、「大樹会」(退職した特定郵便局長の団体)のような有力な政治圧力団体を抱える郵政省が、1985年施行の「電気通信事業法」によって戦略産業としての情報産業の主導権を獲得した。これにより情報産業は郵政省の支配下におかれ、産業構造の向上と発展が抑制されることになった。それが、NTT改革の停滞、さらにはIT革命への乗り遅れとなり、今日の長期不況の原因の一つとなっている。
その後80年代に入っても、日本はレーガン政権やサッチャー内閣が行ったような根本的な改革ができなかった。そのため必要な政治体制・経済体制・社会構造などの改革が遅れ、1990年代を「失われた10年」にしてしまった。
日本がなすべき改革とは
以上の分析から、今後日本の政治が採るべき手段を二つ指摘したい。
第一に、中央政府はその経済統制的な役割を徹底的に弱める。周知のように、現在の世界は情報革命に基づくグローバリゼーション時代に入っている。このような状況の中では伝統的な政府の果たせる役割は急速に減少しており、経済活動の主体は民間へとシフトしている。また、ヒト・モノ・カネは自由に国境を超えている。これまで日本が取ってきた護送船団方式の保護行政では、こうした急速な変化に対応できない。その象徴が1990年代の金融危機である。したがって、中央政府はその経済統制的な役割を弱めなければならない。それには、行政改革(中央省庁再編、規制緩和、特殊法人の整理、行政の透明化、国家公務員の削減など)の実行が不可欠である。
第二に、国政の主導権を「官僚主導」から「政治主導」へ転換し、新しいタイプの国会議員を誕生させる。新しいタイプの国会議員には、これまでの国会議員にはなかったいくつかの能力が求められる。その一つは、政策や主張を率直に表明し、政策や主張によって有権者の支持を得る力である。それによって主張や政策に基づく政党を結成し、競争的な政党政治を実現する。「55年体制」の終焉以後、多くの政治家が理念のためではなく、当選するために政党に参加している。政治理念が全く違う政治家が同じ政党に所属することは理解できない。また、政党が政策実現のためではなく、与党になるために連立政権を作っている点も見過せない。このような政党の行動が、政治が変わらない状況を作り出している。
次に、新しいタイプの国会議員は、国内意識と国際意識のバランスが取れなければならない。これまでの政治家は国内向けの発言が多い。例えば歴史問題や政府開発援助(ODA)について、ともすれば国内有権者のみを意識して言動する傾向が見られる。有力な閣僚が「南京大虐殺は捏造だ」、「対中戦争は侵略戦争ではない」、「対中ODAは三分の一を減らすべき」と発言したり、「中国脅威論」を展開することがある。一連の発言は、中国国民の感情を深く傷つけている。両国の良好な関係を築くためにも、このような発言はしない方が良い。国内意識と国際意識のバランスを維持するためには、国政のリーダーの意識が国際化していることが欠かせない。世界経済一体化の前提は、地域経済の一体化である。日本が東アジア経済圏の形成を志向するならば、日本の政治家は日本周辺諸国の存在を意識した言動をとる必要がある。
さらに、新しいタイプの国会議員は、転職の能力とノウハウを備えなければならない。歴史的に見ると、真の改革者は最終的には困難な状況におかれる傾向にある。今の日本の財政状況では、増税は不可避であるにもかかわらず、政党も政治家もそれを口に出そうとしない。落選を恐れるあまり、不人気な政策を訴えることができないでいる。戦前は、言論軽視の風潮の中でも、斎藤隆夫氏のように、血を吐くほどの情念で「粛軍演説」や「反軍演説」を行い、聴衆を説得しようとする政治家がいた(注2)。政治家はまず自分自身の政治理念を持たなければならない。そして、たとえ落選してもそれを貫き通す決然とした勇気がいる。それには、当選できなくともやっていけるだけの能力、例えば弁護士や大学の教官、企業のリーダーとして活躍できるようなノウハウを身につけておく必要がある。政治家が当選することを最大の目標にしている限り、日本の政治は変わらないであろう。
(注1)綿貫譲治「高度成長と経済大国化の政治過程」日本政治学会編『年報政治学1977年度 55年体制の形成と崩壊』岩波書店
(注2)加藤紘一『いま政治は何をすべきか』講談社 1999年
 | 王新生(ワン シンシェン) | |
| 北京大学歴史学部教授。1956年中国山東省済南生まれ。北京師範大学大学院修士課程修了。北京大学大学院博士課程修了。歴史学博士。1988年~2000年まで中国社会科学院日本研究所主任研究員。1997年特別塾生として松下政経塾で研修。2001年2月より現職。 |
関連性の高い論考
Thesis