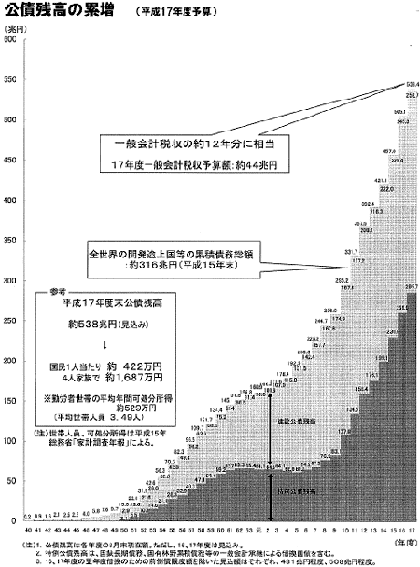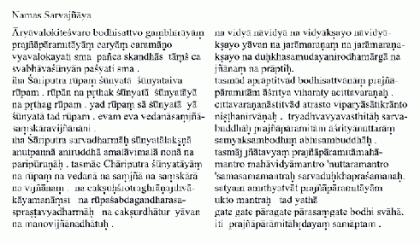Thesis
人間と幸之助哲学と仏教観 -般若心経と真言密教の間で-
宗教や精神世界に触れる機会が少ない世情に生きている。価値観が唯物に対し偏重し、見えないものの価値を軽んずる傾向にある今、人間の哲学的思索の蓄積である東洋思想から学ぶべき事は多い。幸之助塾主の哲学と、仏教の世界観から今一度人間の存在を考えたい。これは、人間を考える、一つの挑戦である。
(導入・「欲と不安と苦」)
米国に発した世界金融不安は、今や遠く離れた一国家の財政をも破綻させ、世界の大多数の国々の経済に影響を与え、潜む将来不安に陥る結果となっている。経済の原動力、それこそが人間の限りない欲望であるとするならば、欲望こそが不安の元凶であるとも感じられる。金(money)、という商品の交換ツール・代替物・価値の尺度を絶対視する中で、金こそが価値観の全てになっている状況は、人間自身にある良識を奪う脅威となるのではないか、との思いがする。金融の自由化で金融機関の役割が変容している。従来の「知恵とノウハウ・人のつながりで顧客にアドバイスする業務」から、「自ら投資家というプレーヤーとして、自らが最大利益を上げる」機関になっている。つまりは、価値の提供を基に経済の創造を増大させるはずの業界が、顧客から利益を鞘抜くための商品開発で実態の価値から遠く離れたところで業務が成り立つ。かつて日本もその主役を演じた。
1980年代から90年代にかけての土地バブルである。価値を実態以上に膨張させるのは、所有者と非所有者、そしてその推移を見守っている第三者の価値への欲望が根底にあり、実態を離れた推移を先導した。現在、ドル売り円買いにより、円高ドル安傾向は顕著だが、同時に日本の株自体も下がっている。為替相場において、円を買うとはつまり、円を貨幣として媒介する日本国家の価値や日本経済の信用度・期待度を評価して、他通貨との相対的な評価が決まる。しかしプラザ合意以降、これまでの涙ぐましい経営努力によって商品力をつけ、他国に対抗してきた日本の主要産業は、これほどまでに急激に円が高騰すると大打撃を受ける。円を媒介とするだけで、損害を生むのである。
人の欲望が絡む“見える価値”の変動は、実態実物の等身大の価値と大きく乖離することがある。誰もが価値を共有するために数値化し、逆に数という尺度が絶対視され始めると、その数が一人歩きを始める。もはや、物と評価が別物になっている。その別物を使って、実態評価との差が生じ、そこで儲ける欲望が生じる。誰もそこに疑念を持たずに進行すると、ある時初めて、空洞化した洞窟が崩壊するように、膨れ上がった“偽価値”が自然に本来の価値程度に戻る動きをする。その度人間は打撃を受け、不安に陥る。欲望の需給関係が失敗する盲点である。欲が欲を生み、同時に不安に陥り、しかしながら、いずれそこに苦を感じる人間がある。私利の追求、に汲々とする人間の姿が垣間見られる。
人間の天分とは、何なのか。ただひたすらに、時間をおいて失敗を繰り返すのが人間のはかなさなのか。
数千年の太古より、人類は欲と苦に向き合ってきた。現代社会に生きる我々は、そうした歴史の先に生きている。人類の叡智を汲まない社会であっては、歴史のその先に発展的な姿を生むことは出来ないであろう。現実社会に生きながらも、社会の捉え方、生きることの捉え方を、考えてみたい。
(幸之助塾主の向き合った、何か)
私自身が、人間の営みの末に今生かされている人間であることはいうまでもない。
欲と苦にまみれて生をつないできた人間に生まれたことは、生まれながらにして苦を背負った宿命があるのか。生きていることは、無常にも消え去る灯のように、大宇宙の長久な時間の流れの中で、一瞬にして存在している、もしくは一瞬しか存在しえない物体なのか。
人間の存在する意義とは、その程度のものとは思わない。しかしまだ、直感でしかない。人間とは何か、いわば、他の動物ではない人間を支える何か、という足がかりでもいい。今求める必要がある。
「『天地自然の理』は『宇宙の真理』であるという。それは『宇宙根源の力』によって成り立ち、『宇宙の法則』に従うものである。それが『宇宙の秩序』と『調和』を育むものである。」
幸之助塾主の宇宙観を念頭に置き、私はまず、その根本の考えを紐解くことにした。
京都市南区にあるPHP研究所。京都駅から見えるそのビルの中に、研究所創始者である松下幸之助の思想の根源を凝縮した社がある。その名も、「根源の社」。中には“根源”と書された木札が一枚あるという。これは、ある特定の宗教をお祀りするものではない。没後20年が過ぎようとする現代においても、未だに“経営の神様”として世界から注目される経営者である幸之助は、その思想普及活動であるPHP運動(PEACE and HAPPINES through PROSPERITY)の拠点に、昭和21年、自らと天を結ぶ場を設けた。「物心両面の調和ある豊かさによって平和と幸福をもたらそう」という意味の上記英字頭文字をとって名づけられたPHP研究所。当時はまさに第二次大戦直後であり、日本は日々の生活にも窮する事態であった。
幸之助は、
「人間が疲弊している状況下、鳥でさえ飢え苦しむことなく空を舞っている。万物の霊長たる人間は本来、物心共に豊かで、平和に幸せに生きていくことが出来るはずである」
との思いで、そのための方策研究を始めた。同様のお社は、大阪府門真市にある、Panasonic本社にもある。幸之助は生前、高さ幅ともに2メートル程度のお社を前に石畳に座し、根源の力を感じ、時には諸事様々の悩みをその社に向かって打ち明け、素直な自分になることに自己を同一化したという。時には数十分、数時間に及ぶこともあったという。
幸之助の祀る「根源」とはどういったものであろうか。
「宇宙の根源力ということは説明して説明のつくものではないと思うね。いわば神とはなんぞやということと一緒やからね。だから根源力という一つの基本的な力があって、こういうもので宇宙が出来ていると考える。宇宙の大神としてもいい―。」
(大宇宙に対峙する、存在)
ここでいう神とは、GODではない、と解釈する。つまりは、宇宙根源の力というものがこの宇宙全体をつくり動かしている。この動かし方が真理というものである。ひいて考えれば、人間自身も宇宙という大きなものの動きの中で存在があり、その真理の一部を活用することで、繁栄を導いている。つまりは存在しているという、状態。繁栄しているという、状態。それぞれの作用の動きの中には、真理が働いている。こういった諸々を含む力の総体、それこそが、いわゆる「天」であり「根源」と置き換えてもいいのかも知れない。
「天」を述べるためには、もう少しその概念を掘り下げなければならない。易の観点から述べるとするならば、宇宙を営む偉大な力が波動、活動しつつ、相互転換性を表しているものだという。前段の「波動、活動しつつ」という部分は、根源の解釈で見られた意義付けであろう。つまりは、大宇宙の偉大なる力のようなもの、とでも言うべきだろうか。しかしながら、そこに相互転換性を見出すことは、宇宙の根源の力に日々対峙する幸之助の行動背景に潜む原理ではないかと考えるのである。宇宙に向かう心を、幸之助は次のように述べている。
「宇宙の恵みに感謝する人は、永遠の生命を知る人である。」
次いで、
「宇宙に瀰漫する力を信じ感謝の心を深めて行くところに明確な人生観を打ち立てられ、自然の恵みはいよいよ働きを増し、繁栄・平和・幸福の道を進むことが出来る」
と言うのだ。
恵みを受け、大宇宙に対峙する人間の存在。科学的な観点から見れば、完全なる主と従であろう。人間という個は、宇宙から比すればちっぽけな“属する”存在である。しかし、あくまでも対等な意味付けにて対峙するとは、どのような概念で説明すれば良いのだろうか。
宇宙、ここで言う概念は、COSMOSと言い換えることが出来るかもしれない。古代ギリシア語とも言われるその語源には、「秩序」や「美」という意味も含まれるという。当時の人々は星や太陽の運行を見て、整然たる秩序体系を感じ、調和する宇宙という概念には、何か神秘的で壮大な動き(つまりは真理)があると感じたのであろう。実測できる星の周期を越えて、星の周期の原動力ともなり得べき目に見えない大きな力を知った。このCOSMOSの概念は、macro cosmos(大宇宙)とmicro cosmos(小宇宙)とに整理できる。科学技術が益々深まる昨今は、理論物理学や電子の世界、素粒子の世界といった超微細な世界の探求に及んでいる。しかもその中に、宇宙の根幹をつくり上げる現実エネルギーが含まれているという。モノの極限、つまりこれは、micro cosmosの世界である。その原子の世界をどこまでも研究し突き詰めて行くと、今日の研究成果の段階でも、それより小さな存在がないとされた素粒子にも、陽子・中性子等と二十種類も発見されているという。これは翻って考えると、macro cosmosの対極であるmicro cosmosではあるが、微細な原物質にこそ、宇宙を作るエネルギーが含まれるとするならば、microの中にこそ、macroが存在するとも言えよう。つまり、人間自身の中にも既に宇宙的素養が詰まっており、その偉大なる力を見出す能力を有することこそ、人間が万物の王者としての存在を、自ら積極的に自認しなければいけないとも考えさせてくれる。
幸之助の向き合う姿は、社の中にある「根源」の木札一枚ではあるが、木札という一物質に願を込めるものではなく、まさに、全宇宙に対する力に畏敬を示し、自らの中に宇宙を見出し、その偉大なる力を活用させて頂く、そのための準備作業であったのかもしれない。
microの集合体というならば、自分という存在はあるのか、ないのか。
あるとするならば、あると感じる自分の実態とは何なのか。
(根源思想の、根源)
幸之助を動かした思想を深めるためには、仏教の世界を覗かなくてはならない。
つまり私は今、根源思想に対し、東洋思想学的な観点で迫ろうとしている。ならば、根源思想を生み出した背景に踏み込まねばならないと考える。それは、日本人の根底に流れる仏教観についてである。
紀伊水道に面する和歌山県には、偉大な宗教家が残した拠点が存在する。
その宗教家とは、日本に真言密教を開祖した、弘法大師空海である。讃岐国多度郡屏風浦(現在の香川県善通寺市)に生まれた空海が入定(にゅうじょう)した地、それこそが、和歌山県にある真言宗の総本山の寺院、高野山金剛峰寺である。
根源、という得体の知れない大きな何か、に包まれることを知覚した今、遠い昔、幸之助の生まれた土地に一人の天才が人々に残した、“仏教の世界観”について触れたい。
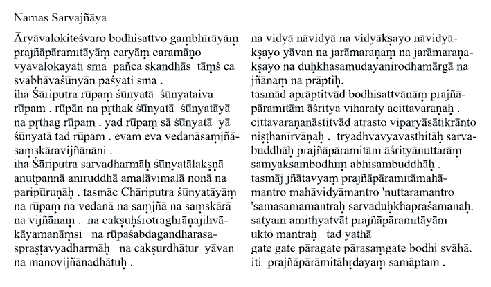 |
【上:サンスクリット原文、下:般若心経原文】
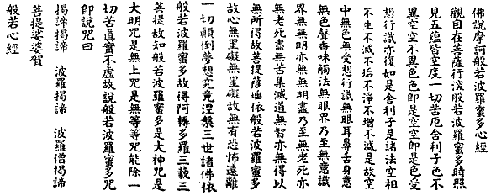 |
曼荼羅(梵語、maṇḍala)―。それはまさに、仏教においての聖域、仏の悟りの境地、世界観などを仏像、シンボル、文字などを用いて視覚的・象徴的に表わしたものである。この幾何学的なその文様に表現される世界観は、古代インドに起源をもち、中央アジア、中国、朝鮮半島、日本へと伝わった。古代より、世界各地のアミニズムにおいても、円は神秘的な意味を持つが、まさにこの言葉には、完全や円満の意味を含むという。同時に、「本質、真髄、エッセンス」を表現する。密教の曼荼羅は、幾何学的な構成をもち、すべての像は正面向きに表わされ、素人目には手の込んだ絵画のようにも見えるが、古代ギリシア人が星空を見て感じたように、複数の要素が、ある秩序のもとに組み合わされ、全体として何らかの宗教的世界観を表わしたものであると解釈できるという。
曼荼羅には、金剛界曼荼羅と胎蔵曼荼羅がある。実際はまだまだ様々な曼荼羅があるが、この二つに集約されていったと言えるという。金剛界曼荼羅が、陽の原理、ひいては空間的世界の発展の所相を示すのに対し、胎蔵曼荼羅が陰の原理、つまり、時間的世界の秩序を示すという。その空間的時間的世界観を、この二つの曼荼羅で示した。総じて言うならば、曼荼羅こそ、仏教世界の模式図であり、総体ともいえるであろう。
この中心に位置するのが、大日如来という永遠不滅な仏である。
空海の残した密教は、この大日如来が全てのものを包み込む世界を示す。そして全てのものは、この永遠不滅な大日如来のあらわれに過ぎない。この大日如来の永遠の生命を「密」という。密というのは二つの意味があり、その一つが秘密の密、つまり万物の奥に隠れている意味である。そしてもう一つが密度の密、いわば、いっぱいものが詰まっているという意味がある。つまり、存在が詰まっており、全てのものの存在の根源を成すものをいう。いわば文字言葉で表せない、教えの奥義なのである。その世界観で言えば、我々人間の中にも密が宿っている。密教的観点では、我々の中に宿る密は三種類あり、身密・語密・意密である。身・語・意とはつまり、からだ・言葉・心を示す。我々の身体はすなわち大日如来、つまり宇宙そのものであり、我々の言葉もまた大日如来、そして心も既に大日如来そのものになることが出来ると、密教は解く。ここで、密教が他の仏教の中でも特異なのは、人間の身体に密が宿るという、身体を全面的に肯定していることである。精神的涅槃を謳う仏教的教えの中での身体の肯定は、つまるところ感覚の肯定であり、すなわち人間に備わる欲望の肯定を意味する。この教えこそ、密教で説かれる即身成仏という教えである。仏教では普通、仏になるのは死後とされるが、現世において仏になれるばかりか、この肉体を持ったまま仏になれるというわけである。
(仏教の根本)
しかし、密教もまた仏教である。そこで、仏教とはいかなるものか、今一度整理をしたい。
仏教の興りは紀元前五世紀に遡る。今から2500年もの昔、釈迦という人物が開祖したのは周知の通りである。我々には、おぼろげにもその姿が想像しづらいが、この世に実在した人物が、ある種の新説的世界観を示した。彼は人間の世界を苦の世界として捉え、その苦の原因を欲においた。欲があるから苦がある、それゆえ、欲の火を消せば苦悩はおさまり、人間は静かな悟りを得ることができる、という教えを説いた。そして、釈迦の弟子たちはこういう教えを守って、好んで町から離れ、山林でたいへん慎ましい清潔な生活を送ったが、紀元前一世紀頃、このような伝統的な仏教に対する大きな批判が起こる。それは、このような静かな悟りの仏教で人間が救えるか、本能である欲を殺してしまっては人間の活動は失われる、もっと人間は自由になる必要があるというものである。それには、欲の捉われからも自由になり、禁欲の捉われからも自由にならなければならない。こういう欲の肯定にも否定にも捉われない「空」の論理を説いたのが、龍樹である。この龍樹の弟子たちは、自分たちの立場を大きな乗り物、つまり大乗とし、伝統的な仏教の立場を小さな乗り物、つまり小乗とし、立場の優越を主張した。
大乗仏教は、このように伝統的な釈迦仏教と違って、どちらかといえば欲望に対して肯定的な立場をとる。たとえば、大乗仏教の翻訳者である鳩摩羅什は、若いときに快楽におぼれた。昼は精力的に経典の翻訳をしたが、夜は欲望のままに過ごした。しかし、破戒を犯しつつ、彼は人生の無常を知って仏道を求めたのだといわれている。密教の中心経典であり、今でも真言僧がもっとも日常的に唱える「理趣経」は、そういう愛欲肯定の教えを実に大胆に説いている。こういう教えは、バラモン教に存在する考え方であるが、仏教は最後の発展段階である密教において、バラモン教への先祖帰りというものを、欲望肯定した形で行っているのである。
密教は、大日如来の教えが龍樹に伝わり、それが龍智、金剛智、善無畏、一行、不空、恵果と伝わる系譜をつくる。その後、恵果がその命が今尽きようとする時に唐に渡ったのが、遣唐使一団に随行した留学生・空海である。延暦二十三(八〇四)年、歳三十一の空海は、二十年という在唐期間を義務付けられていったにも関わらず、こうした天命的な恵果との出会いにより、僅か二年で仏教を学び、玄宗の護持僧として令名の高かった不空の弟子・恵果から密教の秘法を全て授けられた。
長安で空海が恵果に会ったのは、延暦二十四年五月であったが、あたかも恵果は空海の来訪を待ちかねていたかのように、わずか三ヶ月で未知の遥か大海の先より渡ってきた空海に、師・不空から伝えられた密教の秘法をことごとく空海に授け、そのことを任務としていたかのように、その年の十二月に亡くなった。その辺の逸話は本文から外れるために割愛するが、こうして密教の大きな流れは、日本に伝法されるのである。
(「空」の論理に紐解く、人間観)
これまでの仏教観概論から、その伝法によって人々から煩悩を去り、悟りをひらき、涅槃に赴くこと、それが仏教自体の究極の目標であるといえる。その鍵が、欲望からも禁欲からも全くの捉われのない心、つまり「空」を悟ること、これこそが仏教理解の必要不可欠な要素であるといえよう。
空は、これまで高僧や大哲学者でさえ理解困難な思想であり、空さえ体得できれば、すぐにでも仏になれるとまで言われている。
(空とはなにか)
空とは、クウであり、カラである。無、ではない。空と無は大きく違う。それは、水、をモチーフに考えたい。
コップの中に水は、あるのか、ないのか。たとえば、空気中に存在する水蒸気が凝結すれば、水になる。水が蒸発すれば、水はない。水が冷却されれば、氷になる。氷は水ではない。しかし氷も、状態が変化すれば水になる。したがって、コップの中身を問われれば、空の状態があるだけであって、水という物質が変化する以上、コップに水がない、とは言い切れない。水の存在は、水の外部要因による環境によって「水」と定義されるものの存在が有無どちらともいえるのである。
しかし、水は実在しているといえる。この宇宙の中に、環境が整うことで、有ったり、無かったり、するのである。そういった意味においては、空(非実在)は実在を生み出し、別の要因で実在しなくなる。
水、を水と捉えているのは、人間なのである。人間といっても様々で、ミズ、といって通じるのは日本人だけであり、「Water(英語)」「수(韓国語)」「Eau(仏語)」「Wasser(独語)」「Acqua(伊語)」「Agua(西語)」「Água(葡語)」、様々である。これが音声や知覚・臭覚・味覚の世界になると、もっと多様に捉えられるし、更には人間以外の動植物にとっても、水は不可欠な存在であるが、捉え方、言い方を変えれば感知の仕方は、まさに万差億別といっても過言ではない。時間軸で喩えをするならば、「夢」も同様である。見ている夢のその時点では、見ている人は実在を感じる。しかし、醒めたとたんに夢となり、寝汗や歯軋りが、実在の無いものに対する反応となる。
そういった意味からは、実は、実在というものは実在しないということから捉え直さなくてはならない。
上記した龍樹の言葉を借りるならば、全ての存在は、本当は仮にそう考えておくだけであって、実態は一刹那に実在して、一刹那に消えるとした。一刹那とは、仏教の世界では指を弾き音がなる、その時間が六四刹那という説や、一昼夜が六四八万刹那といわれるくらいだから、一日二十四時間として計算すると、一刹那は約〇.〇一三三秒ということになる。瞬間瞬間で、実在がなくなるということなのだ。考えてみると、先ほどの水の例にも通じるが、人間の身体は、成人で55~60%は水で出来ていることは科学で解明されているが、分子生物学によると、六ヵ月で完全に細胞が入れ替わるというのだ。日々必要水分量が2リットルとすれば、65キロの成人であれば、30日少々で別の水分と入れ替わっていることにもなる。いずれにしろ、この身体を構成する細胞レベル、分子レベルでは、常に個々の生死を経て入れ替わっているのだ。自己の身体に実態としての身体は存在せず、あわせて自我も存在しないということは、人間の心身が空であることを説いている。これが仏教世界でいう、唯識である。
しかし、それがあたかも連続して続いている状態、つまり水が状態を変えながらも存在する環境作用、これが縁起である。因縁とも言われる作用が、瞬間瞬間にて変化する人間の何かを継続させ、一細胞が繋がることで、過去を内在的に蓄積しながら次の生命が生まれる。しかし、全く同じものは存在しえない。
仏教は、善因楽果、悪因苦果という因果律を徹底している。つまり、よいことをすればよい報いを受け、悪いことをすれば悪い報いを受ける。全て作用による結果が、そこについて回る。しかし我々は、全てが同時に進行しているのであり、単純的に、A→Bへと因果しているわけではない。菩提樹の下で釈迦が悟ったのは十二因縁であるが、それは単純連鎖の因縁といわれる。無明(無知)→行(形成力)→識(心作用)→名色(精神と肉体)→六入(眼・耳・鼻・舌・身・意)→蝕(心が対象と接すること)→受(感受作用)→愛(愛欲)→取(執着)→有(生存)→生(生まれていること)→老死(老いて死ぬ)が生ずるというサイクルである。しかし同時に、時間的な関係性があり、同時に進行する空間がある。つまりは、植物が有るためには種があり、種の生育のためには、水やら温度やら、日光やら…無数の環境が同時進行的に整って初めて、成長するというものである。これも仏教的「中論」思想なのである。一切の法は、相互依存関係によって成立していると解く。
一刹那毎に変化を遂げる全てのものは、互いに相依って、その依存関係がまた新たな変化を生む。その変化が変化を生み、それがまた変化を生むこの世界。果てしなく広がるその過程では、原因が結果となり、結果が原因となって、常に関係し合っている。
空の根幹は、有る、無いといった一現象の特定に限らず、全てのものを含む相互依存と同義といえる。だからこそ、万物は日に新た(=発展的変化)であり、全てのものは常に生成し、絶えず発展しているといえるのである。
(素直な心と、空)
空のあり方は、つまりは心のあり方であるといえるのではないだろうか。人間を考える上で、無知から自己を確立し、しかしながら、自己に捉われない心を養う。結局人は原物質の集まりでもあると。しかし、原物質と自分は別物であるという枠組み自体が、自己に執着させている。実態の属性を離れたところに無我の境地があり、ありながら空にしている状態が空である、ともいえる。つまり、自己がありながら捉われのない心、それは言い換えればすなわち、素直な心、といえるのではないか。
素直な心の意義として、幸之助塾主は次のように述べる。
「素直な心とは、私心なくくもりのない心というか、一つのことにとらわれずに、物事をあるがままに見ようとする心といえる。つまりは、真理をつかむ働きのある心であり、物事の真実さを見きわめて、それに適応していく心」
だという。
素直な心を持つことで、強く正しく聡明になる。それは人間が賢くなるということであり、神のような叡智を持つことが出来るようになる、ともいうのだ。
素直さとは、単に人に逆らわず従順という意味ではなく、結局は宇宙の真理に向き合う心と言うことが出来るだろう。
そして、それを実践するための『素直な心になるための十か条』として、最初に挙げられているものが、「強く願うこと」である。強く願い望むことで、熱心に研究し人々から吸収し、工夫しようとする。そのために強く願うことが必要だというのである。
真言密教において特に重要視されるのが、行、という行動であることは、空と素直を考える時に、特筆すべきことであると考える。空海の持ち帰った数多くの経典を、最澄は次々に借り出すことに成功するが、根本経典である『理趣釈経』の借用申し込みを空海は断った。行という、自らが願い私を滅却してその教えに自らを一体化させることなく、書面上経典を読んでも理解が出来ない、というものである。頭で理解をしても、生き様そのものに生かされないようでは、本物の体得者とは言えない。
空とは、何も無いことを示すのではない。
事の実相を把握するための心の持ちようが、素直な心を持つことであり、万物の価値、生かし方を見る方法であるといえるのではないか。
(即身成仏と物心一如)
もう少し、塾主の考えと密教における人間観を比較したい。
それは、即身成仏の観点より物心一如の真義を探りたいと思うのである。人間だけがほかの動物に無い成しうる偉大なわざ、それが「物心一如の調和ある繁栄を招来することが出来る」と幸之助は言うのである。
我々は、密の概念を通じて、大日如来と一体になる、つまりこの大宇宙の真理と、自己の心身を一体化させることで、そのまま成仏できるという解釈を進めてきた。空海が解説するに、それはまさに密教の中心経典である「金剛頂経」及び「大日教」に記されているという。つまり、「金剛頂教」には、「この三昧を修する者は、現に仏菩提を証す」とあり、大日如来と一体になるという境地で行を修する者は、現に、そのまま仏になることが出来るという。また「大日教」には「この身捨てずして神境通を逮得し、大空位に遊歩して、しかも身秘密を成ず」とある。つまり、「今の身のままで何ものにも捉われない自由な境地を得て大空位に遊ぶことが出来る」と言う。この遊ぶとは、自由な、まさに「空」の境地を楽しんでおり、また「身秘密を成ず」、密教の最高の悟りと一体になる深い悟りに入ることが出来るという。さらに空海は即身成仏というものを、偈(解釈文)を通じ解説を加えている。「六大無碍にして常に喩伽なり」である。この六大とは、地・水・火・風・空および識である。つまり、前五つは世界を成り立たせる物質的原理であり、それに加え、最後の識、つまり心という精神的原理を加えて六大と呼んでいる。裏を返せば、識もまた物質的原理である五大を持っていると言える。地が全てのものの支えとなり、水が清める。火が全ての欲望を焼き尽くし、風が全ての対立を吹き払う。五大はそれぞれ象徴的な意味を保有すると同様に、識はそれ自身の中に宿っている。仏も衆生も皆すべて六大が入り混じって成り立っているというものである。全てが元々持っているもの。だからこそ、それぞれのものは相通じ合い、総体として一如である。だからこそ、物心の一如の姿を受入れ、それぞれの姿を生かすことが、万物の原理を生かしめることになるということが、弘法大師空海の主張なのである。精神的な繁栄をもたらした密教の招来と共に、書はもちろんのこと、灌漑事業や絵画や彫刻といった物質的な繁栄をももたらした功績は、以後の日本の歴史の変遷を見ても、極めて有効なものである。空海に言わせると、「小我に拘らず、空空漠々たる大日如来の心を己の心とすれば、何事も成しえないことはない」ということだとも言えるだろう。つまりは、逆説的に捉えると、物心一如とは、元々別のものの双方をそれぞれ繁栄させるのではなく、元々は一つであるそのありのままを受入れ、その性質を生かす作業、であるといえるのではないかと考えるのである。
(幸之助哲学と仏教の相関性)
これまで、仏教や真言密教のエッセンスを幸之助哲学と比較をしながら、宇宙の中の人間の存在を考察してきた。それらの思想につき益々深め、探求していく必要性を感じている。と同時に、スタートの区切りとも言うべき、今回の思索のまとめとして、一つの捉え方をお示ししたい。それは、「観」という一字に集約できる。
人間の観点をどこに置き、誰とも同一視できない自分を含む世界観をどういった観点で生きるか。それに尽きるのではないか、と感じる。
仏教世界において、人間の意識レベルを4段階に考えることがある。人間の成長と併せて考えるならば、幼児期である【無意識】のレベル、知や体験を通じて、自己の確立を進めることで世間的なレベルである【自己形成】期に到達する。しかし、自分というもの『自我』が確立された上で、自分を細分化していくと、自分とは何かという分類が考えられる。それこそが【無我】のレベルになる。感覚や身体自体に自分の本質はない、と。痛いこと自体は、自分ではない。逆に、痛いと感じている自分の手の部分が切断されてなくなっても、自分という存在はある、ということだ。感覚や肉体の区切りは、まさに人間の枠組みでしか過ぎず、枠組みの捉われの中で生きるからこそ、自己への執着が生まれ、我欲の巣となるのである。自が他との境の内側にあるために、自の欲望が最大化されることを求めるのである。全てのものは在って、ないもの、であり、全ての捉われは無意味に帰す。そうした心情に達することで、物事の実相が見え、事の本質が見えるというものである。それが【空】のレベルである。「諸法無我」といい、「諸法空相」といっても、諸法も自己も消滅したわけではない。問題は自己自身を、ひいては諸法諸物をどう観るか、その観点こそが重要であるといえる。
そうした自己の執着を離れた観点を養う必要があるのは何故か。それは、自分の枠組みの中だけで生きているようでは、全てが思い通りにいかないからである。起こったことをありのままに捉えられない心は、宇宙の大きな動きの中で本質を衝かず、結局は、自らの内の中で苦を感じることになる。だからこそ、等身大の自分を受け入れ、同様に違いのある他人をも受け入れる、そして起こる事実に向き合い受容していく精神が必要なのである。
私はこの考察を通じて、単に慈愛の精神を持つことが、現実社会に起こる苦厄から逃れられる方法であるとは思わない。しかし結局のところ、自分の意識レベルを上げる、今まさに直面している悩みや苦しみを、大空高くから地上にある自分を見つめなおしてみよう、という作業であると捉え直したい。自分という枠に捉われず、自分がどういったもので構成されているか、という捉われからも離脱する。自分という存在を見つめつつも、心の通気性を良くすること。それこそが、自分をも生かし、他人をも生かし、同時に事の実相を知り万物を生かすことに繋がるのではないかと、結論付けたい。
そうした人間の視点を上げる大きな動機付けとして、塾主の「人間は万物の王者である」という世界観を与えられたのではないかと感じる。自己という枠組みを離れ、王者であることの自覚から、人間個々の観点を上げさせることで、自己も、そして他者をも幸せに出来る道筋がある。その事を伝えたかったのではないかと感じる。同時に、その事を自覚することが出来るのも人間だけであるし、実際積極的な意味づけをし行動できるのも人間だけなのである。だからこそ塾主は、多くの人に、その使命感を与えたかった違いないと考えるのである。
「この世で最大の不幸は、戦争や貧困などではありません。人から見放され、“自分は誰からも必要とされていない”と感じることなのです。」
とマザー・テレサは残している。
自分という人間を知りつつ、天に与えられたる自分の生きる使命感を持つ。これこそが、人間に強い動機付けを与え、力強い営みを行う原動力となると考える。
自分を考え、人を考える。
物事のありようを知り、生かし方を知る。
その上で、自分の果たすべき役割を知り、その使命に基づいて生きる。
そうすることで、小事に惑わされることなく、天地宇宙の大きな動きに順応しつつ、その力を生かした力強い取組み、人類の営みができるのではないか、と感じるのである。
(人間観を支える宇宙観)
我々はここまで、塾主の遺した言葉の中から、人間観を包む宇宙観の検証と、東洋学的な観点のほんの一部を活用し、その思想の根源を探ろうとしてきた。そしてその過程で、人間観の根底にあるものを検討しようとした。それこそがまさに宇宙観にある、と集約できると結論付けるのである。生成発展の理法の中で、存在が認められている人間こそが、宇宙の本質を自覚し、生かし活用すること(物心一如)が出来る。だからこそ、この天命を果たさねばならないと自覚するのである。偉大さを悟り、天命を自覚することこそ、人間が真に受け止めなければならない姿勢である。そしてそれを知った以上は、実践をするしかないのである。
古今東西の先哲諸聖をはじめ、幾多の人々が残し、また築いてこられた知恵は偉大なものがある。
社会に蔓延する表層現象の悲観に捉われることなく、前向きに次の一歩を考える、そういった姿勢を貫きたい。
もう一度、どこからともなく、しかし全ての因縁によって起こる風を感じよう。
今、自分自身がある、神秘を感じよう。
今在るという自らの、生きる使命を果たすことこそ、人間の存在意義である。
【参考文献】
平成6年度政治セミナー 『松下幸之助塾主政治理念研究会』資料 財団法人松下政経塾
日本人のための宗教原論 徳間書店 小室直樹
空海の思想について 講談社学術文庫 梅原猛
生命の海<空海> 角川ソフィア文庫 宮坂宥勝・梅原猛
現代語訳般若心経 ちくま新書 玄侑宗久
空海 三教指帰 中公クラシックス 福永光司訳
空の論理<中観> 角川ソフィア文庫 梶山雄一・上山春平
人間を考える PHP文庫 松下幸之助
素直な心になるために PHP文庫 松下幸之助
密教21フォーラム資料『般若心経』梵文和訳・サンスクリット原文
中西祐介の論考
Thesis
Yusuke Nakanishi

第28期
中西 祐介
なかにし・ゆうすけ
参議院議員/徳島・高知選挙区/自民党