Thesis
食から見える北海道フロンティア精神
ジンギスカン、スープカレー、定番では乳製品、じゃがいも、たまねぎ、海産物などなど…。全国の皆さんに愛される北海道の食。そのおいしさには、開拓時代の苦労や秘密がたくさん隠されていた。道産子に身近な食べ物の歴史を振り返ることで、現代にも引き継がれている北海道フロンティア精神を探る。
Ⅰ はじめに:ホッカイドウと言えば「食」でしょ?!
私は、30歳になるまで、北海道から一歩も離れて暮らしたことが無い、生粋の道産子である。小中高はもちろん、大学も道外に進学しようとは全く思わず、就職も北海道庁という、これまた超ド級の道産子的職場を選択した。北海道で生きることに何の疑問も持っていなかったし、あえて出る必要性も感じたことが無かった。
しかし、その頑なな姿勢は崩れることになる。志実現に向けて松下政経塾に入塾するため、初めて本州で生活することになったのだ。
札幌在住の頃、全国を飛び回る転勤族の方から、色々な地域に住むと独特の文化があり驚くことがあると聞いていた。私は、政経塾のある茅ヶ崎市に住んで、特段、これはビックリしたという文化の違いを感じたことは無いが、1つだけ、本州で生活してみて、しみじみ感じていることがある。
それは「北海道は食べ物がおいしいんだ。」ということである。
ここで前もって言っておくが、北海道以外の地域の食べ物がまずいと言っているのではない。どこにでもおいしい食べ物はある。しかし、それを差し引いても、やはり北海道の食べ物はおいしいと感じるのである。
北海道で生き続けた30年間、道外の人が、何故、大挙して北海道に観光でやってくるのか、私には正直、わからなかった。グルメ番組がどうして北海道ばかりを取り上げるのかもわからなかった。北海道産の食べ物を食べることが当然であった私は、そのありがたさに全く気付いていなかったのである。
しかし、本州で暮らしてみて、寿司を食べても、ラーメンを食べても、カレーを食べても、野菜を食べても、牛乳を飲んでも、ジュースを飲んでも、水を飲んでも、とにかく、北海道の食べ物の方がおいしいと感じてしまう自分に気が付いた。そして、北海道の食文化に改めて感謝するとともに、色々と調べてみたくなったのである。
以上が、このレポートを書くに至った背景である。調査当初は、そのおいしさの秘密を解き明かそうというのが目的であった。
しかし、北海道の食文化を調べているうちに、私はあることに気が付いた。それは、北海道の食べ物のおいしさや独特の文化には、北海道の自然・風土だけでなく、開拓の歴史が大きくかかわっているということである。私が、毎日、当たり前に食べていた食べ物には、北海道で生きた先人達の思いがたくさん詰まっていた。当たり前のおいしさは、当たり前にできたものではなかったのだ。
よって、このレポートでは、北海道の食文化を象徴するおいしい食べ物をいくつか取り上げ、それらの背景にある歴史を通じ、北海道開拓時代に、先人達がどういう思いでその食べ物を作ったのかを探る。そして、そこに脈々と流れてる北海道フロンティア精神を掘りおこす。
北海道フロンティア精神などというと、そんな大袈裟なものを今の北海道民は持ち合わせていないし、そんな精神があるのなら、今の北海道はこんなに衰退していないと指摘する人も多いと思う。しかし、私たち北海道民の最も身近な「食」に、その精神は確実に、無意識に受け継がれているのである。
このレポートを読んで、読者が今後北海道の食べ物を食べるとき、ふとそのことを思い出してくれることを期待するとともに、北海道民がフロンティア精神に目覚め、北海道が元気になる一助となることを願い、本題へと移りたい。
Ⅱ 「少年よ。大志を抱け!」クラーク博士とラーメンの関係
北海道の食を語る上で、切っても切れない国がある。それは「アメリカ」である。
現在の北海道の食文化は、本州・四国・九州では考えられない程、確実にアメリカ文化の影響を受けている。それは何故かというと、北海道開拓使が農業分野を中心に、アメリカの技術に支えられていたからだ。
明治31年6月26日に刊行された『札幌農学校』という冊子の「第二章 札幌農学校の過去」、「第一節 明治維新と北海道の開拓」によると、明治二年に北海道開拓次官となった黒田清隆は、その後すぐ官命により渡米し、北海道開拓の策を画したそうだ。その際、耳目を一洗して、アメリカを北海道拓殖の模範とすると決め、アメリカ政府に請い、当時の農務局長ケプロン外3名を北海道に招くことになった。これが事の発端である。
その後、北海道開拓使では、お雇い外国人として多数のアメリカ人を雇うことになる。表1は、当時日本で働いていたお雇い外国人を国籍別・省庁別に表したものだが、開拓使にいた外国人の半数がアメリカ人であったことがわかる。
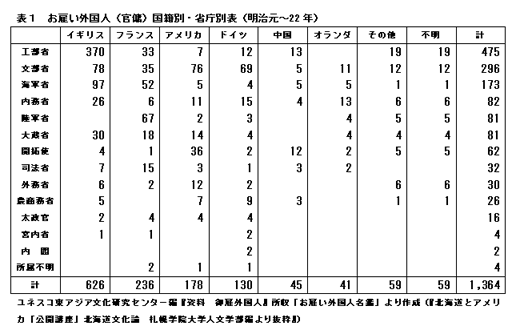 |
さらには、これらお雇いアメリカ人は、農業分野に限らず、開拓に係る様々な分野に進出する。汽船乗組員、鉄道建設、測量・土木、地質・鉱物、革なめし、機械・工作、缶詰製造、医師等だ。そして、特に多数のアメリカ人が進出した分野が教育であった。
開拓使顧問となったケプロンは、開拓使用の人材を育成するため、農業大学校の設立を黒田に求め、その準備のために、マサチューセッツ州アマスト農業大学で校長をしていたウィリアム・スミス・クラークを召集した。彼こそが「少年よ。大志を抱け。」で有名なクラーク博士である。クラークは2名の部下を従え来道し、日本で最初の国立大学である札幌農学校(現北海道大学)を札幌に設立した。明治9年8月のことである。その後、明治14年までの間、開拓使には学校教師として11名のお雇いアメリカ人が在籍していた。
こうして、北海道は札幌を中心に、アメリカ文化の影響を受けるようになる。開拓使は、寒冷且つ未墾で広大な北海道の大地は、稲作に適さないとして、欧米型の畑作牧畜中心の農業を推進した。これに伴い、北方生活にはパン及び肉を主体とする洋食が適しているとし、これらの食物を自給し、他府県へ供給することを開拓の基本と定めたのである。この基本により、北海道では洋食の奨励が国策として進められる。その中心となったのが、札幌農学校であった。
札幌農学校では、夕食に必ず洋食が提供された。その際の食材は、開拓の基本を実行すべく、全て北海道内で作られた小麦やバター、肉を使用していた。しかし、この洋食給食は、学生達にすこぶる評判が悪かったようだ。当時の記録によると、学生達は洋食給食を食べずに、多くが外食をしていたようである。
このような有様であったから、当時、一般移住民への洋食の普及はもちろんままならなかった。さらには、明治15年に開拓使が廃止されると、この洋食奨励は中断される。
ところが、その後も札幌を中心に洋食文化は少しずつ脈々と継続することになる。北海道開拓50周年を迎えた大正時代には、都市部を中心に洋食店も増加し、バター・チーズ・アイスクリーム等の酪農製品が売られるようになり、道民の口もようやく洋食に馴染み始めた。この頃になると、コロッケ、カレーライス、ハヤシライス等が定着し、牛乳、バター、ソース、ケチャップが札幌の一般家庭等に普及していった。
以上のように、北海道での洋食普及の歴史を見ていると、2つのことがわかる。
1つは、現在、北海道で北海道民に愛され、慕われている料理の多くが、明治政府の開拓方針により、意図的に奨励・導入されたという点である。最近、東京周辺でも流行し始めたスープカレー1つを例にとっても、じゃがいもやにんじん、たまねぎに肉というように、欧米型の畑作・牧畜普及が根底にあるのだ。遠いアメリカからたくさんの技術者が来道し、その技術移転に伴い、開拓民が日々苦労し、品種改良や技術革新等の不断の努力を行い、それまでの日本型とは全く違う新しい畑作や牧畜を確立し安定させていった賜物を、私たち北海道民は日々食しているのである。生きていくための命がけの選択から生まれた洋食文化。そう思うと、ただのカレーライスも、また格別においしく感じるのではないだろうか。
そして、もう1つは、農業技術と共にアメリカナイズされた感性が北海道民に移植されたという点である。これは歴史を紐解くだけでは気が付き難い。
Ⅲ 道産子はお砂糖が大好き?
道外に住む人たちは驚くかもしれないが、北海道には砂糖をこよなく愛する食文化が根付いている。最近は、北海道スイーツが全国的に有名になってきたので、なるほどと思われる読者もいるだろう。しかし、私が言いたいことはそういうことではない。洋菓子の中に砂糖を使用するのとは別に、北海道では、日常の食事に砂糖を多用する例が多く見られるのだ。
たとえば、納豆に砂糖を入れて食べる道産子はたくさんいる(私も実家で時々食す)。また、トマトに砂糖をつけて食べる道産子もたくさんいる。さらには、道東圏では、アメリカンドック(フレンチドック)に砂糖をまぶして食べているし、道央圏を中心として、北海道の多くの世帯の赤飯には、砂糖がまぶされた甘納豆が入っている。
これは、道産子の私にとって当然のことであり、とてもおいしいのであるが、本州に住んでみて、他の地域ではあまり行われていない食べ方であることを知った。そこで、どうしてこのような食べ方をするのか、調べてみることにした。
まず、調査のとっかかりとして、北海道の砂糖の消費量を調査してみた。総務省統計局が実施している家計調査によると、平成18年北海道内調査対象世帯1世帯当たりの年間砂糖購入数量は平均8,213gである。これは多いのかと思いきや、東北では9,301gであることがわかり、格別多いとは言えない。つまり、北海道民は砂糖をたくさん食している訳ではなく、他の地域があまり使用していない部分にも使用しているということがわかった。
それは何故か。歴史を調べていると、ある一つの仮説が私の脳裏に浮かんできた。これもやはり、開拓時代に大いに関係するのだ。
現在の日本国内で、北海道は砂糖の原料となるてん菜の一大産地である。平成14年時の北海道内全作付け面積のうち、実に16%をてん菜が占めている。何故かというと、1種類だけの作物を作り続けると畑は痩せてしまうことから輪作を行うのだが、北海道ではこの輪作作物として、てん菜が普及しているからである。
北海道における本格的なてん菜栽培の推進は、明治11年、開拓使が札幌農学校にてん菜の試作を依頼したことに始まる。当時のアメリカで、てん菜栽培がすでに盛んであったためである。洋食普及の背景同様、欧米型農業の移植の1つとして、てん菜栽培が始まったのだ。同年、松方正義が内務省勧農局長としてパリ万博に行った際、てん菜糖業の隆盛を目の当たりにし、フランスから製糖機械を購入し、勧農局直営のてん菜糖工場を北海道内に建設した。しかし、この工場の経営は上手くいかず、明治29年には解散。その後、てん菜糖業はしばらく中断していたが、大正期になり、北海道に適した栽培方法等が確立され、道産農産品として定着していった。
以上の歴史を見てわかるとおり、開拓期の北海道にとって、砂糖はかなりの貴重品であったことがわかる。その昔、砂糖は北前船により樽詰めにされて、本州から運んでこなければ食せないものであり、特に、農村では、今では想像もつかないほど交通事情が悪く、入植したばかりの開拓農民の手元に砂糖が届くことはほぼ無かった。北海道では、それだけ砂糖が珍重されていた歴史があるのだ。その苦難を努力で克服した結果が、現在のてん菜王国北海道なのである。
つまり、現在の北海道民の砂糖好きの背景には、このような開拓の歴史が存在しているのである。砂糖入り納豆は、開拓期の入植者から見れば、この上ない贅沢であり、彼らを含め先人達が長年に渡り努力して、てん菜を北海道の主力作物に育てた結果得られる、最高の味であることがわかった。もし読者が北海道に来て、おかしなものに砂糖を入れて食べている北海道民を見ても、気持ち悪がってはいけない。それこそが、北海道フロンティア精神の一部なのである。
Ⅳ 赤色102号
赤色102号とは何か。これは一般的に食紅と言われる食品添加物の種類を表す。
私が本州に住んで、客観的に北海道を見たときに気付いたことがある。それは、北海道の食品には、着色されたものが多いということである。前述の砂糖の章で、甘納豆入りの赤飯を紹介した。この赤飯、実は北海道では食紅で着色するのが普通である。
 |
上の写真は、私の実家でいつも炊かれている赤飯である。道外の地域で作られる赤飯は、小豆の戻し汁でもち米に色を付けるようであるが、北海道の一般的な赤飯は、写真のとおり、食紅効果でかなりピンク色である。北海道ではこのような赤飯が、大手スーパーの惣菜コーナーで普通に販売されている。
さらに北海道の食品を見てみると、ラーメンの具としておなじみの「なると」も、外周がピンクで覆われている。道外で一般的な周囲が白いなるとを「つと」と呼び、ピンクの「なると」と区別している人もたくさんいる。魚の身を原料に作られる「桜でんぶ」を料理に多く用いるのも北海道の特徴だ。
また、飲み物を見ても、着色されたものを好む傾向が見受けられる。
北海道内でほぼ限定生産されているガラナ飲料、サッポロビールが道内で限定発売しているリボンナポリン。どちらも着色されているが、北海道内では不動の人気を誇っている。
今、日本は食の安全に非常に敏感である。それは北海道でも変わらないし、農業王国北海道では、むしろ他の地域以上に敏感かもしれない。にかかわらず、どうしてこのような食品が未だ北海道民に好まれているのか。
それは、北海道の開拓時代の料理を見ると納得できる。この時代の特に冬場の料理を見ると、色がとても暗いことがわかる。今でこそ冬の北海道で暮らしていて、新鮮な野菜をたくさん食べられることは当然のことである。冬の間、雪が積もる北海道では農業はできないが、九州などの暖かい地域から、どんどん野菜が輸送されてくるからである。
しかし、開拓時代の北海道で、冬期間の食料の確保は大きな仕事の一つであった。そのための技術として発展したのが、保存食である。
昔の北海道で冬期間生きていく上で一番困ることが、野菜不足によるビタミン欠乏である。この問題を解決するため、先人たちは、秋に収穫した大根やにんじん、じゃがいもを、土の中に埋めて保管し、積雪のあとに掘り出して食べていた。また、このように保存できない野菜は、漬物にして貯蔵し食べていた。その他にも、魚や肉を塩に漬ける保存方法や、乾燥による保存方法も盛んに行われていた。
このような保存食の特徴として、色が悪くなることが挙げられる。どうしても鮮やかな色は飛んでしまい、黒や茶色のものが多くなる。栄養価に問題は無いものの、恐らく、当時の人たちにとって、色彩的には寂しいものがあったに違いない。
それは単に冬期間の食べ物だけに言えることではない。冬の北海道は、降雪が多く、天気が晴れないことも多い。つまり、冬の北海道は、全体的に暗い傾向にある。
読者もわかると思うが、天気も悪く、出される料理も色彩が暗くては、お世辞にも楽しい気分とは言えない。故に、北海道民は、着色料を適度に使用し、料理の席を華やかに飾ったのではないかと私は考えた。お弁当箱に入れられる、プチトマトの役割である。
それでなくても非常に辛い北海道開拓の歴史である。無意識であっても、先人から続く、せめて色彩くらいは明るくしたいと思う北海道民の気持ちが、私にはとても愛しく感じるのである。
Ⅴ 何気ない食べ物に開拓者の思い
最後に…
これまで私たちが、何気なく食べていた北海道の食べ物。その背後には、今の私たちには想像できない、たくさんの先人たちの努力の歴史が存在していることを、このレポートを通じて理解することができた。開拓期以降の北海道民が、これだけ頑張って作ったきた北海道の食べ物がおいしいのは当然であろう。これからも、私たち現在を生きる北海道民は、胸を張って、北海道の食べ物を日本中、世界中に広めていくべきである。
昨今、競争原理が国際社会にも浸透し、日本においても、各国とのEPAやFTAが推進される時代にある。日本の食べ物の生産者にとって、このことは深刻な問題であり、北海道もその例外ではない。私たち北海道民1人1人が、このレポートで書いたような食の歴史をさらに認識することで、地産地消の促進にも繋がるのではないだろうか。
毎日当たり前に食べている食べ物。今一度、そのありがたさを再認識する時代にきているのかもしれない。
参考文献等
『北海道とアメリカ「公開講座」北海道文化論』 札幌学院大学人文学部編 札幌学院大学人分学会発行1993年
『伝承写真館 日本の食文化①北海道・東北1』 農文協編 2006年
『北海道の食』 村元直人 幻洋社 2000年
『北の生活文庫5 北海道の衣食と住まい』 北の生活文庫企画編集会議編 非売品 1997年
『さっぽろ文庫31 札幌食物誌』 札幌市教育委員会編 北海道新聞社 1984年
『覆刻 札幌農学校』高倉新一郎解題 北海道大学図書刊行会発行 2005年
総務省統計局家計調査結果
北海道農政部食の安全推進局農産振興課ホームページ
石井あゆ子の論考
Thesis
Ayuko Ishii

第27期
石井 あゆ子
いしい・あゆこ
衆議院議員政策担当秘書
Mission
真の住民自治の確立、北海道振興、地域再生


