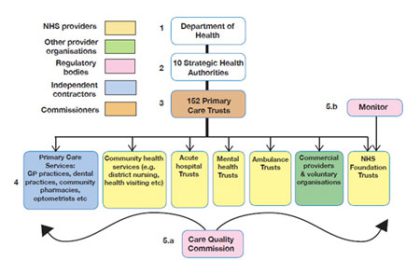Thesis
松下幸之助と私と人間の本質
あの心の奥深いところでもがくような形容し難い苦しさはどこからやってくるのだろう。松下幸之助と私との繋がり、それは私にとってこの塾での最大の収穫であったと言ってもいい。
【目次】
1.オーストラリアの酒場から
2.人間の本質とは
3.塾主研究の一端を
4.塾主と私と生と死と
5.その日を迎えるまで
1.オーストラリアの酒場から
10月中旬から研修のために訪れたシドニーの街並みは、オーストラリアの他の街にも特有のある種の明るさに加え、経済の中心地として同国を支えてきた一種のプライドのようなものも感じられる。街角に軒を連ねるアジアンフードショップから声を上げる店員や、タウンホールの階段近くに腰をかけ、どうやらソフトクリームを食べ終えたばかりの若い女性も、春を迎えたためかどこか陽気な街の表情の一部としては落ち着きがいい。多様な文化を受入れた街、豪州経済の牽引車。ハーバーブリッジとオペラハウスの織りなす街の代名詞と化したsceneryと共に、この街を表現するのに相応しい言葉である。
私が豪州を訪れた理由は他でもなく、医療制度の現地調査のためである。渡豪後、様々な方々との出会いや協力のお陰で、想像以上に充実した研修を送ることができている。そしてさらに多様な国々から集まった人々を通して「人間を学ぶ」という意味でも、意義深い日々を送ることができている。
ユースホステルの同部屋のスウェーデン人は建築学科を出ながらヘリコプターのパイロットを目指し、ライセンス取得のための学校を探しにオーストラリアに来ている。10代の時に徴兵制で軍に出向いた際、試運転したヘリコプターが忘れられず、遂にその道を本気で進むようになったという。30歳になってからの決断は大きな勇気が必要であっただろうと推測する。何か自分と通じるものを感じたこともあって彼とはすっかり親しくなり、お互い異国の地ということも手伝ってことある毎に誘いあっている。
その日も大学教授へのヒアリングの帰り道、彼から私の携帯にコールが入った。
「今飲みに出てるんだけど、今から来ないか?ぜひ来てほしいんだ!」
お酒は飲めないが、楽しそうな人々のいる雰囲気は嫌いではない。今日の研修成果をまとめる仕事量とそのための時間とを頭の中で秤に掛けているうちに、活きのいい彼の調子についに押し切られてしまった。
呼び出された3階建てのパブではその日から同部屋に入ってきたスコットランド人とイングランド人とが彼と共に笑顔で私を迎えてくれた。他にも多くの着飾った男女で溢れており、その3階の一部はホールになっていてバンドの生演奏とそれに合わせて踊る人達とで賑わっている。気丈に声をかけようとする男性達、声をかけられるのを待ち続ける女性達、隅の方でグラスを傾けながら真剣に語りあう男女の群れ、時に聞こえる言い争い。ある者は笑い、ある者は泣く。どこの国の酒場でも見られるのと同じような光景である。
そしてそのような光景をみていると、陽気にその場の空気を楽しめる私がいる一方で、決まってある特殊な感情が私の中に湧きおこってくるのである。表面の賑やかさとは裏腹に、敢えて言うならばどこか心の奥深いところでもがくような形容し難い苦しさ。それは彼らへの嫉妬とも私の若さへの焦燥とも言い難い。きっと私自身の心のもがきであり、そして彼らの心のもがきでもある。
その苦しみはどこから来るのであろうか。果たして癒されない心の病なのか―――答えを導き出すために、私はまず人間の本質について論じるところから始めたい。
2.人間の本質とは
政経塾に入塾して1年半が経過した。振り返ればこれまで多くの方々とお会いし、学ばせて頂いたものだ。その様々な出会いはむしろ私が医師であった時以上に、私にとっての命の価値というものを高めてくれている。
政経塾の研修では「徳」「知」「体」という三つのカテゴリーでひとりの塾生を捉え、その人としての成長を評価する試みを行っている。「知」とは知識や知力、「体」とは身体の練磨や健康、そして「徳」とは―――当初はこの徳というものがいまひとつピンと来なかったが―――今の私の理解では、徳とは心の成長と言えよう。心の成長とは時に辛く苦しい様々な経験から、そして時に先哲諸聖の残した言葉からひとつずつ悟ることをもって得られると理解している。それゆえに政経塾の研修の中には講義や運動の他にも100km行軍や参禅合宿など敢えて苦境に立たせるような行事もある。心の成長とは決して楽な道ではなく、だからこそ価値があるとも言えるのだろう。また古典学習など先哲の教えを学ぶことにも多くの時間が割かれている。頭が良いだけでも体が丈夫なだけでも人として成熟しているとは言えない。徳知体すべてを備えてこそ真のリーダーであるというのである。人間とは徳知体の三つから成り立っている。それもひとつの人間の本質であると言えよう。
しかし、人間の本質とは当然ひと言で言い表せるものではあるまい。「人間は考える葦である」とはフランスの思想家パスカルの言葉であるが、他にも古代中国の性善性悪説などこれまで多くの学者や思想家達が研究し、それぞれの立場から様々な定義を述べてきた訳である。だから私は敢えて難しいもの言いは避けよう。むしろ有史以来変わらない人間の姿とは何であるか、ごく単純に考えることに重きをおいてみる。
有史以来変わらない人間の本質―――飲み、食べ、眠り、欲望に従うこと。時に笑い、時に泣き、時に怒ること。女性が子供を産むこと。人によってその内容は違えども、幸せを求めること。
髪の色、目の色、肌の色、口から出る言葉、その表面は全ての人が見事に異なっている。しかしその本質は全ての人が一様に同じであり続け、そしてこれから何万年という時を経てもその本質が変わることはない。もちろん直感ではあるが、そう言い切ることができる。そして最後に忘れてはならない人間の本質がもうひとつだけある―――誰もが一度だけ死を迎えること。
死というものの中に、あの形容し難い苦しみも様々な問いの答えも見つかるような気がしている。人間は死にどう向かい、何を得てきたのだろうか。
3.塾主研究の一端を
論を進めるために、ここで塾主・松下幸之助について触れておく。
松下幸之助は当然、Panasonicの創業者であり、松下政経塾の創設者である。実は私は入塾まで恥ずかしながら松下幸之助のことをその程度しか知らなかった。当然、松下政経塾生としては許される筈もない。私のような「不届き者」が入塾してくることを慮ってか、入塾後すぐに塾主研究と題された松下幸之助について学ぶ期間が塾生には設けられている。
正直なところ当時の私には幸之助という人物があまりにも遠過ぎて、私にとってどのような存在であり、これからどのような関係を結ぶことができるのか、塾生として期待された幸之助に向かう「あるべき到達点」にまで達する自信を持てなかったこともあり、当初は大いに困惑していた。そんな私にとって入塾後まもなく始まった塾主研究は、ひとつの試練であり、またチャンスでもあった。PHP総研の佐藤悌二郎先生から数度にわたるご講義を頂き、最後に総まとめとして幸之助ゆかりの地を訪問するために関西を巡った。幸之助の作った庭園・真々庵の空気を吸い、幸之助のお墓に水をかけ、Panasonic創業の地を歩いていると、遠かったはずの塾主のその思いに魂が感じ入り、最後には私と幸之助の確たる繋がりが得られたように思っている。
幸之助について学ぶ中で、私が最も興味を引かれたものが幸之助と宗教との関係である。物心一如という言葉を頻繁に用いたあたりからも分かるように、幸之助は経営者としては比類なく目に見えない要素にも価値をおいていた。そして生涯に渡って様々な宗教と関係をもち、広く深い付き合いを続けたのである。その様子が端的に分かるように、簡単に年表にまとめてみる。
1894年(0歳) 浄土真宗の家に生まれる.長屋には白龍大明神が祀られていた.
1918年(23歳) 創業時、白龍大明神を祀る.
1926年(31歳) 高野山初訪問.以降も五代音吉に誘われ、度々訪問する.
1930年(35歳) 真言宗の僧侶・加藤大観氏を相談相手にする.
1932年(37歳) 天理教本部を訪問.水道哲学を悟り、社の創業命知元年とする.
1937年(43歳) 加藤大観氏を家に招き、朝夕勤行を受け始める.
1938年(43歳) 高野山に松下電器従業員の慰霊塔建立.以降毎年9月に慰霊法要.
1939年(44歳) 光雲荘完成の際に天祖大神という神様を自ら考えて祀る.
1962年(67歳) 会長職就任を機にPHP運動再開.真々庵に「根源の社」を建立.
1967年(72歳) 京都PHP本社建設の際に「根源の社」を建立.
1981年(86歳) Panasonicの創業の森に「根源の社」を建立.
その他にもキリスト教、創価学会、立正佼成会等々との付き合いもあり、実に様々な宗教と生涯関わっている。なぜ多様な宗教との関わりを持ち続けたのだろうか。
幸之助は自らの提唱したPHP(繁栄を通して平和と幸福を)の運動を進めるにあたって宗教の繁栄を大いに期待し、次のような言葉を残している。「経済を中心とした物的生活、宗教を中心とした精神的生活が人間生活の両輪で、宗教の興隆がなければ真の繁栄もない」「PHP運動の狙いは宗教の復興である」幸之助の中には常に物心一如の繁栄こそが真の繁栄であるという思いがあったことが読み取れる。そんな幸之助も晩年には自らが創造した「根源の社」に辿りつく。根源の社の前に静かに坐し、感謝と素直とを求めて熱心に祈り続けた姿は多くの人達の記憶に残っている。
私が幸之助の宗教観に興味をひかれるのは次の二点が特異的であると思うからだ。一点目は自ら神を創造し拝み続けたという点。そして二点目は宗教に対して極めて客観的であると同時に「根源」に対しては極めて主観的であったという点である。
幸之助の次の言葉からはその一端がみてとれる。「人間は自分の発想で神様を創造し、そこから知恵を授かって自分達が成長する。そうしながら更に具足の神様を創造し、知恵を授かろうとする。自由自在に神様を創っているのが人間です。」そう表現しながらも自ら神様を創り、誰より熱心に拝み続けたのは幸之助自身である。神を求める強い信仰心と同時に、あくまで客観的に宗教を捉えようとする冷静さが併存しているといえる。そして幸之助は誰にも自らの神を勧めることをしなかった。多様性を受容しようとする多神教と異なり一神教では基本的に人に神を勧めることをよしとし、極端な場合は他を排除しようとする傾向が強い。「根源」が一神教であるとは到底言えまいが、大いなる宇宙の意志と表現されるその性質はむしろ一神教に近い。その自らの神への強い信仰を誰にも勧めることなくひとり黙々と保ち続け、そうしながら神を創造した自らも客観視しているところに幸之助の宗教観の熱く冷たい特異性を感じるのである。
なぜ幸之助はそのような特異な宗教観をもつに至ったのだろうか。恐らくひとつの理由は、経営者としての中立が必要であったからであろう。ある時PHP研究会で、幸之助は所員に得意先の大野氏についての話を教訓として伝えている。幸之助が商売を初めて10年程経った頃の得意先であったが、途中から宗教に熱を入れ過ぎて幸之助はじめ取引先にまで強引に勧め、取引先を失って最後には倒産してしまった。幸之助も様々な宗教から勧めを受けているが、多くの従業員を抱えるひとつの企業を背負う立場である以上は、特定の既存宗教に没頭できなかっただろうし、また自らの信仰を人に強く勧めることもできなかったであろう。次に幸之助は無税国家論、新国土創成論、観光立国論など様々な提言を出しており、しばしば理想主義的現実主義者であると表現されるが、そのことも宗教観に現れていると言えよう。熱を入れて理想を掲げる一方で現実を見据える視点を失わない冷静さ。それが幸之助の特筆すべき性質のひとつであり、宗教観にも色濃く反映されている。
幸之助の宗教観を説明する最後の理由として幸之助と死との関係が挙げられる。その点については次の項で説明する。
4.塾主と私と生と死と
幸之助が生まれ育った明治期と現代とでは疾病構造が大きく異なっている。医療水準はもちろん、上下水道や道路などの公衆衛生もまだ未整備であった当時の日本では、現代の発展途上国同様に感染症が猛威を振るっていた。特に当時の国民病であった結核の影響は深刻で、戦後有効な抗生剤が出回るまでは死因の第一位であり続けた。幸之助の家族も次々と病に倒れ、父親と兄弟5人は幸之助が11歳までにこの世を去り、残された母と二人の姉も遂には病魔に襲われ、幸之助は26歳で天涯孤独の身となるのである。当時の低い医療水準もあって具体的な病名は定かになっていないが、時代背景も考慮するとこれだけの集団感染は結核が原因であったということは容易に想像ができる。そして幸之助自身も幼少期から病弱であったと回想しているが、その結核のために常に振り子の様に病勢に左右される生活を余儀なくされた。酷い時は数ヶ月も病床に伏していたほどである。長い病床での生活で、果たしてどのようなことを考え続けたのであろうか。
目の前で多くの死を目の当たりにした家庭環境といつ死を迎えてもおかしくなかった持病のため、幸之助は幼少期より常に死を意識せざるを得なかったと言うことができよう。このことは幸之助の思想を理解する上で、とても重要なことであると私は思う。そして当然、死後の世界への恐れや備えもあり、幸之助自身熱心に宗教を求める必要があったと考察される。そこに幸之助の宗教観のひとつの理由がある。
そのように私が考える理由は私にも似たような体験があったからである。私は6歳の時に、最も近い家族であった父を突然亡くした。また幼稚園の頃からキリスト教や仏教などの宗教に触れる機会が多く、さらに医師として就職した後にも、多くの人の死を看取る中で宗教というものの必要性を感じてきた。死を前にした患者には宗教から得た言葉が時に救いとなる。そして、それしか救いとならないことも多々ある。
ここで一度、私の宗教観を述べておく必要を感じた。私は元々宗教を学問的に捉えるつもりはあまりない。往々にしてそのような学問からは、医学部生なら誰もが一度は経験する人体解剖の実習に似て「血が通っていない」感覚を受けるからである。私も宗教というナマモノをできるだけありのままに捉える挑戦を今まで繰り返してきた。その挑戦から獲られた戦利品の一部を以下に紹介する。
- 宗教がなくても人は生きていけるが自分に合った宗教を選べばよりよく生きていける.
- 宗教には色彩があり、またその真理には差がある.自分に合う色彩を選ぶべきであり、その中でもより深みのある真理を選ぶべきである.
- 宗教は人に揺るぎない軸を築いてくれる.時に宗教は参考となり、また時に宗教そのものがその人の軸ともなりうる.
- 人は年をとるほど宗教に目を開く傾向にあるが、年をとってからでは宗教の恩恵を最大に享受できないことがある.
- 宗教の目的は全人類を幸せにすることであり、排他的で時に争いを起こすような宗教は本来の目的を失っている.
- 歴史上、宗教が犯した過ちの多くはこの最大の目的を失っているためである.
私と幸之助との繋がりとは何か。私も父を早くに亡くしたために「生きること」について、それなりに真面目に考えてきたという自負だけはある。そのひとつの結果として私の宗教観をもつことができたと思っている。そしてそれは相矛盾するようだが主観性と客観性の塊のようなものである。それゆえ既成宗教の興隆を期待しながら、当人は独自の宗教を持つという幸之助の特異な宗教観も一方ではとても頷けるのである。象と蟻のような違いはあるが、私が感じた幸之助との繋がりは一言でいえば同じ人間としての生と死への思いとそこから生み出された宗教観と言えるであろう。
さらに進んで幸之助の『新しい人間観の提唱』について触れたい。幸之助は同提唱を次のような言葉で締め括っている。
「まことに人間は崇高にして偉大な存在である。
お互いにこの人間の偉大さを悟り、その天命を自覚し、衆知を高めつつ生成発展の大業を営まなければならない。
長久なる人間の使命は、この天命を自覚実践することにある。
この使命の意義を明らかにし、その達成を期せんがため、ここに新しい人間観を提唱するものである」
この提唱は、人間の使命を明確に述べているという点でとても力強く感じられる。その一方、その使命とは科学的な事実を基にしている訳でも、確かな根拠があるという訳でもない。むしろ全体として幸之助の直観に基づく部分が大きく、いわば幸之助の願いであり、別の言い方をすれば祈りであるとも言えよう。(そういう意味では宗教的な色彩も帯びるのかも知れない。)しかしながら利害得失などとはかけ離れたところにある人類に対する純粋な願いだからこそ、否定することも難しく、また多くの賛同を得られるのであろう。経営者でありながら幸之助がこのように利害得失を離れ、人類の繁栄幸福を純粋に願うことができたのはなぜだろうか。恐らく「死」というあまりにも大き過ぎる人間に与えられた本質に囚われながら生きる人生の儚さ、人間の無力さを病床の中で思わずにはいられなかったからではなかろうか。
己の心臓ひとつ自由にすることもできない。己のがん細胞ひとつ除去することもできない。すべてを奪い取られる死を迎えなければならない。それでも人間だからこそ、真実なるものに気付くこともできるし、使命を担いうることもできるのだ、と。
死を招く環境が生み出したもの。死があるからこそ生まれたもの。それは生に対する欲望であり、また別の言葉で言えば祈りである。死があるからこそ、幸せでありたい。誰もが死を迎えるからこそ、幸せであってほしい。わずかな人生を満喫してほしい。全ての人が幸せになることはできないのであろうか。そのためには―――その答えのない問いに私のあの苦しみの答えもあるように思う。
5.その日を迎えるまで
「死もまた生成発展である」
この幸之助の言葉の意味は、何も植物が枯れて土中の栄養分に変わるように、動物が死んで他の動物の食料と化すように、人間も死を迎えた後、世の中に貢献ができるという意味だけではなかろう。今生きている人間にも終わりがあるからこそ、今を輝くことができるのだ。
春を迎えたシドニーの陽射しは、日本のそれとは比較にならない程に鮮やかで、シドニー湾に落としたハーバーブリッジの色濃い影をその傍らでオペラハウスがじっと見つめている。今日から新しく部屋に入ったまだ若いニュージーランド人は、ピカピカのカメラで撮ったそのシドニーの風景写真を高い鼻をさらに高くしながら同じvisitor仲間である私にも見せてくれた。
私は医師という身分を離れて、今は松下政経塾生。そしてこの地では日本からのただのvisitorとしか周りには映らない。33歳の誕生日を異国の地で迎え、さすがに身体の能力はピークを越えたと昔を振り返ることもある。もちろんこれからますます身体は衰え、知恵もやがては廃れていくのであろう。だからこそ心だけはいつまでも成長し続けたいとじっと願いつつ、その日を迎えるまでこれからも日々を満喫していきたいと思う。
(参考文献)
松下幸之助『人間を考える』PHP文庫
谷口全平「南無根源!-松下幸之助の宗教観」PHP研究所
冨岡慎一の論考
Thesis
-
- 2010/12/29
- 医療・福祉・介護
入塾の経緯から卒塾に向けての思い
-
日本の近代医療史を振り返る
-
- 2010/2/27
- 医療・福祉・介護
海外の医療現場からの学び part2 英国の医療制度
-
- 2010/2/26
- 医療・福祉・介護
海外の医療現場からの学び part1 豪州の医療制度
-
松下幸之助と私と人間の本質
-
- 2009/6/28
- 医療・福祉・介護
高齢者が生き甲斐と役割をもって生きる社会の実現に向けて
-
- 2009/4/28
- 国家観
現場を重視し個々を生かす国家へ
-
波間に漂泊する「弱者」
-
生きる根拠
Shinichi Tomioka

第29期
冨岡 慎一
とみおか・しんいち
WHOコンサルタント・広島大学 客員准教授/ことのはコラボレーションクリニック 代表(医師)
Mission
次世代に繋がる地域密着型医療の提供