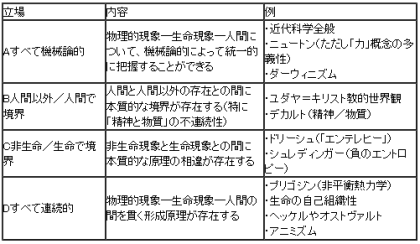Thesis
政治からアメリカ経済を読む
日興リサーチセンターワシントン事務所長を務める植木博士塾員(松下政経塾第3期生)は、アメリカの首都で日々、生のアメリカ政治に接している。その植木塾員に、政治が経済に及ぼす影響とわずかな言動からことの本質を見抜く眼について語ってもらった。
■政治が相場を動かす
一般に証券会社の研究所はマーケットの傍にあるというのが常識です。つまり、アメリカならニューヨークにあるのが普通ということになります。もちろん私の勤務する会社もニューヨークに事務所を持っています。しかし、私自身が勤めているのはニューヨークではなく、アメリカの政治の中心地ワシントンの事務所です。私の主な業務は日本の機関投資家に現実の一歩先を行った正確な情報を送ることですが、そのためにはニューヨークではなくワシントンに居る必要があります。それはニューヨークでは手に入らない情報が手に入るからです。
ウォールストリートの有名エコノミストたちは、経済の基礎的条件を見ながらそれぞれ独自のモデルに基づいてマーケットの行方を予測します。これに対して私がやっているのは、FRB(連邦準備制度理事会:日本の日銀にあたる中央銀行システム)や大蔵省に相当する財務省などの主要な職員に会って話を聞き、表に現れない政策の機微を掴み、そこから先行きを予測することです。
たとえば、FOMC(Federal Open Market Committee;連邦公開市場委員会)という、日本でいえば日銀の政策会議に当たる重要なミーティングがあります。これには12人の投票権を持ったメンバーが参加しますが、そのうち積極的に発言するのは3、4人です。そこで議論をリードしそうなこれらのメンバーをつかまえて話を聞くと金融政策の方向性が読めてきます。政策担当者に直接接していると、発表された数字を眺めているだけではわからない部分が見えるのです。
クリントン政権が1993年1月に発足して、円高ドル安誘導的な政策を取ったことがあります。当時、日米のエコノミストの大半はまさか1ドル=80円台の超円高までは予測しませんでした。しかし、ワシントンで直接、財務省の高官に接していた私には、「これはかなり意図的に、相当な円高に持って行こうとしているな」という感触がありました。これなどは、経済の基礎的条件を見ていただけでは予測のつかない、政治が相場を動かした例です。
また、94年2月から翌年2月にかけて、FRBが金利を3%から6%に上げました。本来、金利はインフレになってから上げるのが経済学の常道ですが、この場合はそれを破って予防的に上げました。その結果インフレの芽を摘むことが出来て、現在8年目に入る戦後最長といわれる景気拡大に繋がっています。これもそれまでのFRBの行動を分析するだけではわかりませんが、ワシントンで政策を決める人々と接触する中で「今回は早めに思い切って動きそうだな」と感じられたものです。
■日米関係を見る3つのポイント
第2次クリントン政権の経済チームは、個別利益の追求に走りがちなミクロ派よりも、日本が良くなればアメリカも良くなるというマクロ的なアプローチをとる人々が主流を占めています。面白いことに、アメリカは日本の混迷を日本ほど悲観視していません。それは同じ道を自分たちも経験してきたからです。具体的には、まずGDP比2%程度、10兆円程度の減税パッケージが必要で、2兆円減税くらいではまだまだ足りないと考えているようです。アメリカは、日本の現在の混乱を日本が「まともな国」になるための産みの苦しみと受けとめています。
しかし、対日批判はくすぶっています。私は日米関係を見るとき、3つの指標を目安にしています。日米間の貿易収支、為替レート、それにアメリカ国内の失業率。現在、貿易収支はアメリカの赤字が史上最高に膨らもうとしており、為替は円安傾向です。失業率は4%半ばで、これが5%半ばを越えると危険水域だというのが私の経験則です。となると失業率以外は危険な状態にあるということになります。
また、アメリカ議会の動向も気がかりです。80年代の終わりに冷戦が終結して、内向きの傾向が強くなってきています。現在、冷戦時に議員経験のない議員が全体の8割近くいます。彼らは身の回りのことに関心が高く、非常に内向きです。このことは今後、円滑に政策を進める上で問題になってくると思われます。
今年は中間選挙の年ですが、ここでの州知事選を見れば、今後のアメリカ政治の流れが読めてきます。各州のポストは連邦政府と同じようにトップはポリティカル・アポインティー、つまり共和党が勝つか民主党が勝つかによって、州政府の組織がごっそり入れ替わってしまう仕組みです。当然、勝った方は州政府を党の組織のように利用することも可能です。しかも、その州を押さえたということは、もともとそれだけの地盤があるという証明です。その意味で注目すべきはカリフォルニア、ニューヨーク、フロリダ、イリノイの4州ですが、これは4つとも混戦模様です。この大票田の行方を見れば、大統領選挙の行方もかなり正確に占うことができます。
■ワシントンは面白い!
私は塾生時代、84年9月から2年間ワシントンにある民主党系シンクタンクのブルッキングス研究所で研修しました。とはいえ、机に座って長大な論文を書くのは苦手だったので、もっぱら出かけてばかりでした。ブルッキングス研究所の名刺を持っていると政府の高官でもほとんどの人が会ってくれるので、いろいろな人に会いました。実際に政策を動かしている各省庁の次官補や次官補代理、日本で言えば役所の課長か局次長に当る人たちにも簡単に会うことができました。しかも、公務員の規律が厳しく、日本のように物や食事で接待するというような必要はありません。しかし、それ故にと言うべきか、気の効いた話ができるかどうかということは重要です。個性的というか、独自の情報のギブ・アンド・テイクが要求されました。「日本はこうだ」「日本経済はこうなっている」とか「これはこう考える」などという程度のことで構いませんが、新しい視点を提供できなければ、次の機会はありません。つまりその人個人の考え、見方が重視されました。
ここがワシントンの面白さ、アメリカのオープンなところだと思います。政策情報の収集が非常にやりやすい。一方、日本ではどうでしょう。霞ヶ関の官僚や日銀の担当者が、外国人のエコノミストに気軽に会ってくれるでしょうか。現状では難しいでしょう。
しかし、いずれ日本も変わると期待しています。政策決定の透明度が高まり、日本にもマーケットに近い立場から政策に提言できる人が現れるようになるでしょう。こうした人は絶対に必要です。官僚だけに政策をやらせることから腐敗が生まれる。同じ人が一生やり続けるところから「お上」意識が芽生える。部分的に、アメリカのようにポリティカル・アポインティーを採用すべきです。
また、政治家はスペシャリティーをもつことが必要です。アメリカを見るとロバート・ルービン財務長官はウォール街での経験が長く26年に渡り大手金融機関のゴールドマン・サックス社で活躍していました。FRBのアラン・グリーンスパン議長もフォード政権下の大統領経済諮問委員長(1974~77年)を経て、87年以来FRB議長の職にあります。彼らはマーケットのことを知り尽くしています。ところが、日本の政治家を見ると「経済もマーケットもわかっていない」と思える人が少なくありません。中にはマーケットを潰すような発言を平気でする政治家もいます。彼らは、景気対策を望んでいるときに「景気対策は絶対やりません」などと言わずもがなの発言をしてさらに事態を悪化させています。
今、日本では金融システム改革が叫ばれてます。腐敗の防止や金融システム安定の問題はもちろん重要です。しかし、官と民でアクティブな情報交換が行われ、金・接待を伴わない自由なディスカッションが行われることはもっと重要です。その点でアメリカに学ぶことはまだまだあると思います。
関連性の高い論考
Thesis