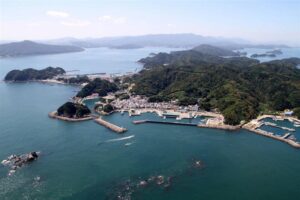Activity Archives
家族「を」経営することに関する諸考察
家族や特定の親族が中心となって会社を経営することを家族(同族)経営という。日本では、全体の会社数のうち90%が家族経営といわれるなど、諸外国と比べても経済全体において占めるファミリービジネス割合は極めて大きい[1]。トヨタ自動車、サントリー、キッコーマン、キャノン、そしてパナソニックというような日本経済を牽引してきた大企業だけでなく、2020年度では上場企業3749社のうち、1848社(49.3%)が同族経営企業であり、東証1部に限っても44.9%を占めた[2]。昨今、家族「で」経営する日本の企業に海外から注目が集まっている。しかし、家族「を」経営することについてはこれまで考えられてきただろうか。
企業を経営することに失敗するということは、企業が廃業や倒産に追い込まれることを意味する。ならば、家族を経営することに失敗するということは、家族解体や家族崩壊、機能不全家族という語に代表されるように、様々な要因により、家族機能に障害が発生し、家族としての統合を維持することが困難になることを指すように思われる。その要因の一つには、マイクロソフトを創業したビル・ゲイツ氏も「人生最大の失敗[3]」と明かした離婚が挙げられるだろう。筆者も、研修で携わった離婚を経験した夫婦と子どもとの面会交流の現場において、「離婚は結婚や家族生活の失敗」とする当事者たちや社会の風潮を感じる場面にしばしば遭遇する。
日本で令和5年に離婚をした夫婦のうち、約10%の夫婦は話し合いが成立せず、調停委員を間に入れた話し合いによって離婚している[4]。そうした紛争性の高い離婚に直面した夫婦は、過度に感情的で、相手への不満が多く、また調停委員への自分の味方であるとの期待とそうではない現状への失望、子どもも同じ考えのはずだという思い込みによって、子どもにとって本当に大切なことを見落としがちである。むしろ、「有利な条件で離婚したい」「あとになってから離婚のことで後悔したくない」「結婚で損したのに、せめて離婚では損したくない」という感情と感情のぶつかり合いを筆者もよく見聞きしたように、目先の損得で意思決定がなされているのではないかと危惧してしまう。
そしてそれは、離婚のうち全体の約60%を占める未成年の子どもがいる場合において、調停離婚に限らず、夫婦の話し合いのみで離婚をする約90%もの協議離婚においても当てはまり得る[5]。なぜなら、未成年の子どもがいる場合であっても、日本では離婚届の「面会交流ついて取決めをしている」「養育費の分担について取決めをしている」欄にチェックをして役所に提出するだけで離婚が成立するからである[6]。だが、実際に面会交流の取決めをしていたのは、母子世帯の母で30.3%、父子世帯の父で31.4%というのが実態である[7]。養育費についても、継続して受け取っていない母子家庭は、約70%に上るにも関わらず[8]、その半数以上が何も働きかけをしていないとのデータもある[9]。背景には、「相手と関わりたくない」「子どもとの面会を強要されるのが嫌だったから」というものが挙げられる[10]。
こうした意思決定は、離婚に端を発するような家族「を」経営することに失敗した際に表出するものに過ぎないのだろうか。そうではない。昨今、世間を賑わせている「年収の壁」は、配偶者の扶養に入りパートなどで働く人が一定の年収額を超えると扶養を外れて年金や医療の社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減ることから、税や社会保険料負担を避けるために年収を抑える就労調整を行なっているというものだ。一方は103万円から150万円だか178万円だかに上げると主張し、もう一方からは本質的な壁は130万円だという主張が飛び交っている。だが、世間を見るとそもそも「壁」があること自体を問う声が少ない。一般人にとって関心があるのは、目先の手取りがどれだけ増えるかであり、そもそも誰かに扶養される、誰かを扶養するライフスタイルやライフコースとそれを推進する制度についてはどうでもいいのである。
こうしてみると、日本人は家族「を」本当の意味で経営していると言えるのだろうか。そもそも経営していないのであれば、離婚を失敗と評価することは到底できないだろう。松下幸之助塾主は、経営について、
ひと口に経営といっても、これにはいろいろあると思う。たとえば、今日のわが国には、大小さまざまな数多くの企業があるが、これらの企業の運営というものも、一つの経営である。また大きく考えるならば、さらに考えるならば、個々人の人生をいかに進めていくかということも、一つの経営だと考えてもよいと思うのである。
辞書によれば、経営とはもともと建築上の言葉で、「土地を測量し、土台を据えて建築すること」だという。そしてそれが転じて、「ある目標を立て、これを達成するために、規模を定め基礎を固めて、物事を治め営んでいくこと」という意味に用いられるようになったという。その定義に従えば、人間が計画を立てて行なう活動なり営みは、すべてこれ経営ということになるであろう[11]。
と述べ、人間の本質がいつの時代においても変わらないものである以上、「この会社は何のために存在するのか。この経営をどういう目的で、またどのようなやり方で行っていくのか」に関して、正しい経営理念を確立できたならば、それもまた基本的に不変であると考えた。その上で、
その経営理念を現実の経営の上に表わすその時々の方針なり方策というものは、これは決して一定不変のものではない。というよりも、その時代時代によって変わっていくのでなければならない。いいかえれば”日に新た”でなくてはならない。この社会はあらゆる面で絶えず変化し、移り変わっていく。だから、その中で発展していくには、企業も社会の変化に適応し、むしろ一歩先んじていかなくてはならない。
それには、きのうよりきょう、きょうよりあすと、常によりよきものを生み出していくことである。きのうは是とされたことが、きょうそのままで通用するかどうかは分からない。情勢の変化によって、それはもう好ましくないということが往々にしてあるわけである[12]。
と述べた。
こうした視点で日本の家族とそれを取り巻く環境を見ていると、社会がこれほどまでに変化しているにも関わらず、社会が前提とする家族のあり方はことごとく変化していないことがわかる。高度経済成長期のような家族をつくれないという未婚者は多く、今の時代にあった「家族」のあり方もそれを支える社会的な仕組みも少ない。こうして、日本では、家族「を」経営するための理念も方策も個人の選択の問題となってしまった。「家族」は何のために存在するのか、またどのようなやり方で行なっていくのか、改めて考えたい。
註
[1] 読売新聞「上場企業の約半数は「同族経営」、世界が注目する理由とは」2023。(2025年2月6日閲覧)
https://www.yomiuri.co.jp/column/economy03/20230417-OYT8T50108/
[2] 読売新聞・前掲注1
[3] ビル・ゲイツ『ビル・ゲイツ自伝/ソースコード:私の原点』Knopf、2025。
[4] 厚生労働省「離婚の種類別にみた年次別離婚件数及び百分率」『人口動態調査(令和5年)』2023。
[5] 厚生労働省・前掲注4
[6] 一方で、米国では、日本のように役所に届け出ることで離婚が成立することはなく、離婚する夫婦に養育計画書の提出や親教育プログラムの受講を義務付けている州もある。
[7] 厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」2022。
[8] 厚生労働省・前掲注7
[9] 株式会社アシロ「【離婚後、親権を持った女性300人に聞いた!】養育費の受け取り実態調査」2024。(2025年2月6日閲覧)
https://ricon-pro.com/columns/683/
[10] 株式会社アシロ・前掲注9
[11] 松下幸之助『松下幸之助発言集 18』PHP研究所、1991。
[12] 松下幸之助『実践経営哲学/経営のコツここなりと気づいた価値は百万両』PHP研究所、2014。
三藤壮史の活動報告
Activity Archives
-
「機能する家族」の条件に関する諸考察
- 2025/7/1
-
家族「を」経営することに関する諸考察
- 2025/5/12
-
コミュニケーションと空間に関する諸考察
- 2024/8/5
-
地域と強力なつながりを築くまで:
コミュニティづくりのデザインとその実践(後編)- 2024/7/11
-
地域と強力なつながりを築くまで:
コミュニティづくりのデザインとその実践(前編)- 2024/7/11
-
入塾式~自己紹介 (三藤壮史)
- 2022/4/9
- 基礎課程(集合研修)
Masashi Mito

第43期生
三藤 壮史
みとう・まさし
Mission
多様化する家族観を包摂する社会の探究