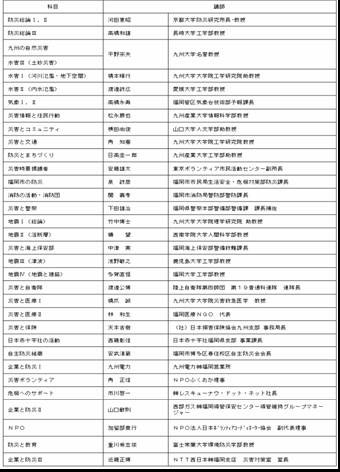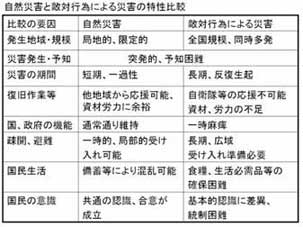Thesis
大東亜戦争の根本的原因を考察する
結果論として大東亜戦争を「愚かな戦争」と断罪することはたやすい。しかし、幾万の犠牲や命をかけて戦った人々のことを考えれば、もっと冷静に眺めてみる必要があるのではないか。敢えて、大東亜戦争の意義を問い直す歴史観レポート第3弾
1 はじめに
大東亜戦争を「無謀な戦争」「愚かな戦争」と決めつけるのはいかがなものかと、私は考えている。大きな犠牲を払ったことは確かである。軍事的には徹底的に敗北した。しかし、敗北したからとて、「侵略戦争だったから」「大義名分なき戦争だったから」とはなるまい。そもそも戦争というものは「善」とか「悪」で区分できるものではないのである。また、戦争だって相手あってのものである。大東亜戦争は未だに、日本が独りで始めたもののように思われているがそうではない。アメリカという国が、日露戦争以後、いかに日本を意識し、戦争の方向へ誘致導引していったか。それこそが、まさに欧米流の「戦略」なのだが、それを知れば、もっと冷静に、客観的に大東亜戦争を眺めることができるだろう。
2 ハリマン計画とアメリカの人種差別政策
アメリカは、日露戦争の講和に際しては仲介を努めてくれたのであるが、これ以降急速に、排日的な政策を打ち出すようになる。
第一にはアジア方面で利害が衝突するようになったことである。東海岸の13州で建国したアメリカは、「マニフェスト・デスティニー(明白なる運命)」を掲げて、先住民族を殺戮しながら西へと膨張を続け、1890年には西海岸に達し、フロンティアの消滅を宣言するが、ハワイ併合(1897)・米西戦争(1898)によるフィリピン領有、門戸開放宣言(1899)にみれば明らかなように、西進は止まることを知らず、ついには支那大陸の分割競争に参入する企図を露わにしている。しかし、実際に大陸にアメリカが参入する余地はなかった。しかし、ロシアの南下政策が日本の勝利によって挫折したことは、アメリカにとって支那進出、特に満州への進出の好機となった。
日露戦争集結前、アメリカの鉄道王E・H・ハリマンは、明治38年(1905)8月ポーツマス講和会議開始と共に来日し、やがて日本が獲得するであろう南満州鉄道を日米で共同管理する案を朝野有力者に説き、大方の賛同を得、10月12日には、桂首相との間に満鉄共同管理に関する予備協定を取り交わし、帰国したが、すれ違いにポーツマス会議から帰朝した小村寿太郎外相は、ハリマン協定に驚き、その破棄を説いて回った。小村の論は、満鉄移譲について清国の承諾を得る以前にかかる協定を交わすことは不当であり、また10万の同胞の命と20億円の戦費を犠牲にして得た満鉄を結局はアメリカに売却し、南満の権益を放棄するのはポーツマス条約の真髄に反するというにあった。結局、小村の主張は通り、予備協定は破棄されることになった。
アメリカからみれば、大陸の門戸開放を理念とする極東政策が、日本によって阻止されたことになる。日米の大陸政策のせめぎ合いが、日露戦争直後から始まっていたのである。
第二に日本を軍事的な脅威として認識し始めたことが挙げられる。日本がバルチック艦隊をほぼ全滅させうるほどの艦隊を持っていたのに、当時のアメリカには太平洋艦隊はなかった。また、フィリピンを領有したアメリカは台湾を領有する日本と領土が近接していた。
第三には、日本移民が農業の白人労働者に対する競争者として警戒されたこと。日本人移民は、勤勉で、総体的に教育水準も高かったため、良地を開拓し、農園を所有するところとなったためである。
以上のように、日露戦争後に大陸政策の食い違い、そして日本または日本人に対して恐れと憎悪が生まれ、日本への追いつめが始まった。それが、排日移民法という形で現れた始めたのである。年代順に列挙すると、
1906 サンフランシスコ市教育委員会、日本人・コリア人学童の隔離教育を決定
1907 サンフランシスコで反日暴動
1908 日米紳士協定(日本が移民を自粛する代わりに、排日的移民法を作らないことをアメリカが約束)
1913 カリフォルニア州で排日土地法成立
1924 絶対的排日移民法
以上のようになる。当初は主として西海岸で、州単位での立法であったし、守られなかったが日米紳士協定を結ぶ余地はあったのだ。しかしながら、24年の絶対的排日移民法は連邦法で、これは別名「帰化不能外人移民法」ともいい、日本移民は禁止されたのである。これが何を意味するだろうか。まず、アメリカ社会の根底に日本人に対する差別があったことであろう。確かに、移民の受け入れについては、各国の自由に任せられるべきだが、ヨーロッパからの移民は受け入れるが、非白色人種の移民は受け入れないということは、どう解釈しても人種差別である。経済の面からみると、日本にとっては労働力の供給先を失ったということである。そのため労働力が過剰になり、新たな移民できるような場所を大陸に求めざるをえなくなったのである。アメリカがホーリー・スムート法によって関税障壁を設け、世界恐慌を誘発したのが1930年で、日本が満州事変を起こしたのが1931年ということを考えればわかりやすい。大恐慌とそれにより発生した失業者をどう解決するかという問題を抱えた日本が満州に目を向けたことには、こういった背景もあったのである。付言すると、ワシントン条約(1922)によって、日英同盟が破棄されたこともアメリカの圧力によるものである。日本は「国際協調」を信じて、日英同盟にかわる四カ国条約を結んだが、これは全く機能しなかった。このことは、アジアにおいて、ロシア革命(1917)によって誕生し、拡大しつつあったソ連や中国共産党などの共産主義勢力に日本一国で対処しなければならないということを意味する。ソ連との間に緩衝地帯を作り、共産主義に対する防衛の前縁を少しでも本土から離したところに設定したいという誘惑に日本が駆られたとしても無理はない。
これらの観点があれば、日本が満州事変から日中戦争、そして大東亜戦争に至ったことを単に「愚かな指導者が無謀な戦争に突入した」と斬ってすてることはできないように思われるが、どうだろうか。
3 マッカーサーが認めた自衛戦争
「日本は八千万に近い厖大な人口を抱え、それが四つの島の中にひしめいているのだということを理解していただかなくてはなりません。その半分近くが農業人口で、あとの半分が工業生産に従事していました。
潜在的に、日本の擁する労働力は量的にも質的にも、私がこれまでに接したいづれにも劣らぬ優秀なものです。歴史上どの時点においてか、日本の労働者は、人間は怠けている時よりも、働き、生産している時のほうがより幸福なのだということ、つまり労働の尊厳と呼んでよいようなものを発見していたのです。
これほど巨大な労働能力を持っていたということは、彼らには何か働くための材料が必要だということを意味します。彼らは工場を建設し、労働力を有していました。しかし彼らは手を加えるべき原料を得ることができませんでした。
日本は絹産業以外には、固有の産物はほとんど何もないのです。彼らは綿がない、羊毛がない、石油の産出がない、錫がない、ゴムがない。その他実に多くの原料が欠如している。そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。
もしこれらの原料の供給を絶ち切られたら、一千万から一千二百万の失業者が発生するであろうことを彼らは恐れていました。したがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです。」
この証言は、日本人のものではない。1951年5月3日、アメリカ合衆国議会上院軍事・外交委員会におけるD・マッカーサーの証言である。東京裁判で日本を裁いた張本人が、大東亜戦争は日本にとって自衛戦争だったと証言しているのである。
この証言は、マッカーサーが朝鮮戦争(1950)において、共産主義勢力と対峙し、満州の 爆撃及び経済封鎖戦略を採ろうとしてトルーマン大統領と対立して解任された後のものであるから、なぜ日本が大陸で共産主義の浸透を防ぐために満州を抑えざるをえなかったかを理解しているものと推測できる。
アメリカは、人種差別的排日移民法、保護貿易によるブロック化、日英同盟の解体と、徹底的に日本を追いつめようとしていたとしか考えられない。それが極みに達したのが、石油・くず鉄等の禁輸を含むABCD包囲網の構成である。日支事変に入っていた当時、経済的に支那を支援するアメリカとイギリスはともかくとしても、直接的には利害の衝突はないはずのオランダまで抱き込んで、経済封鎖をしたのである。アメリカが日本への石油禁輸をした直接のきっかけは南部仏印進駐(1940)であるけれども、これはフランス政府との協定に基づいている平和裡な進駐であって、国際法違法ではない。にもかかわらず、アメリカは在米日本資産の凍結、石油の全面禁輸をおこなって、報復したのである。
当時の日本の経済産業構造は大雑把にいうと、生糸などを売って外貨を稼ぎ、そのカネで買った原材料で安い雑貨類を作って海外に輸出するということで生計をたてていたのであって、その日本に対して、原材料及びエネルギーを手に入れられなくするということは、戦争を誘発することに他ならないことは明らかで、アメリカがこれを理解できないとは考えられない。もはや意図的に戦争を誘発したとしか考えられないのである。
人間にたとえてみれば、首を絞められて朦朧としているときに、その相手と握手をしようという人間はいない。何とか助かろうと思って、意識があるうちに一撃を食らわしてやろうというのが自然な感情ではないだろうか。
4 戦い抜いた意義とは
以上のように、日本が大東亜戦争に突入せざるをえなかった動機は大きく考えれば二つである。日露戦争以後の、大陸政策の食い違いにより生じた日米の蹉跌、そして防共である。従って、自存自衛のための戦いだったといいうる。開戦の詔書にも「帝国は今や自存自衛のため、蹶然起つて一切の障礙を破砕するの他なきなり」とある。少なくとも、当事者たる当時の人々の意識からすればアメリカによって脅かされた自国の独立を守るため、開戦せざるをえなかったのである。
ただ、だからとて、すべてが仕方なかったのだ、というつもりはない。万やむを得ず、戦争という手段に訴えるからには、いかにしてこの戦争を終わらせるかという「終戦構想」があって然るべきであった。日露戦争が、三国干渉の屈辱から、臥薪嘗胆し、十年準備した上に、終戦の構想まで考えての戦争であったのと極めて対照的である。理由として考えられるのは、陸軍と海軍の戦略思想の違いである。海軍はともかくとして、陸軍はアメリカを相手に戦うようには訓練されていなかった。陸軍の仮想敵国はあくまで、アメリカと抜き差しならなくなるまではソ連だった。追いつめられ、やむを得ず、南方作戦をやる羽目になったのだから、もとより単独でどうアメリカと戦うかという構想などあるはずがない。そのため、欧州におけるドイツの勝利と英国の屈服、ソ連の崩壊を前提としてアメリカの継戦意志を挫くシナリオしか描けず、その前提が崩れてしまえば為す術がなくなってしまったのである。他力本願な情勢見積もりは厳禁であることを我々は教訓としなければならない。
とはいえ、日本の開戦劈頭の大勝利は白人万能の世界史の潮流を完全に変えたのである。大東亜戦争の緒戦において、日本は東南アジア地域から欧米列強の勢力を駆逐した。「百聞は一見に如かず」という。日露戦争はいわば「聞」だった。日本が勝ったという情報が伝わったにすぎなかったが、大東亜戦争においては、実際に抑圧され続けていた植民地の人々は、非白人であっても白色人種と対等に渡り合えることを目の当たりにしたのである。終戦後、イギリスやオランダ、フランスは東南アジアの再植民地化を企図したが、現地住民の抵抗に会って、ことごとく挫折していることからも明らかである。
日本が歩んできた近現代の歴史は、「白色人種の歴史=世界史」という流れを地球上のすべての国家・民族が参画する、真の世界史へと導いた壮大な偉業といいうるだろう。その企図が明確であったかどうかという点ではまた別に検証が必要となろう。
だが、結果論的に敗れた戦争を裁断するのではなく、戦争に至った明治以来の歴史の流れを、当時の人々の心をわが心として振り返るとき、大東亜戦争を「愚かな戦争」と冷笑することは出来ない。それは、歴史を担った人々に対する冒涜のように思われる。「破滅への道」を願った日本人など一人もいなかったはずである。誤算を不誠実と混同してはならない。この態度抜きにしては、大東亜戦争という複雑で巨大な歴史から教訓をうることなど永久に叶わないだろう。
<参考文献>
●中村粲著『大東亜戦争への道』展転社
●半藤一利、保坂正康、中西輝政、福田和也、加藤陽子、戸高一成
『日本敗れたり-あの戦争になぜまけたのか-』
●渡部昇一著『昭和史』WAC文庫
●渡部昇一著『日本史快読』WAC文庫
●陸戦学会『近代戦争史概説』
日下部晃志の論考
Thesis
Koji Kusakabe

第25期
日下部 晃志
くさかべ・こうじ
(公財)松下幸之助記念志財団 松下政経塾 研修局 人財開発部部長
Mission
日本の「主座」を保つ ~安全保障・危機管理、教育の観点から~