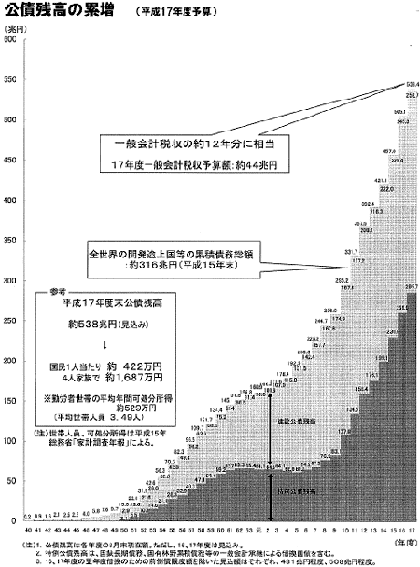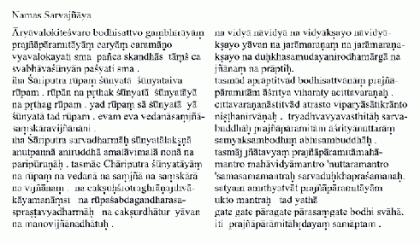Thesis
日本における水事情(1)世界に迫り来る“水危機”の観点から
水は生命の根幹である。今、世界各地で水に関する被害が拡大している。そして、日本も決して例外ではない。各地の研修で感じた水事情と、将来における水と住民の共存スタイルを考えたい。水レポート第一弾。水危機の諸問題を洗い出す。
(古代から現代へ、水と人間)
「かの女にとっては、《うしろは振り返ってはいけません》という神のことばを、むしろ忘れたままでいたほうがよかったかもしれない。想いだしたがゆえに、そのことばをふりかえるように、うしろを見てしまったといえる。
突如、この世ならぬ大音が、女の鼓膜をつらぬき、巨大な怪獣のように膨らんだ水が、にごった波の牙で、いま頭上から襲ってこようとしている。
かの女はこの世の終焉を見た。それがまさに自らの終生でもあった。神のいましめを破ったかの女は、このとき、
―――化して空桑と為る。(『呂氏春秋』)
とあるように、わが児を抱いたまま桑の樹に化けたともいわれるが、おそらく水に溺れかけたとき、わが児をとっさに桑の樹の空洞にかくして、水底で自失したことであろう。
水は桑園を根こそぎ破壊した。母親のかわりに嬰児を抱いた桑の大樹は、水面を浮かびあがり、一種の舟となって流漂した。」
これは古代中国・商の湯王を輔け、夏王朝から商王朝への革命を成功にみちびいた稀代の名宰相・伊尹(イイン)の生涯と、古代中国の歴史の流れを生き生きと描いた小説、『天空の舟 小説伊尹伝』(宮城谷昌光著)の冒頭である。紀元前千六百年頃の題材というから、今から三千六百年も前である。しかしこれを読みながらすぐ思い返されるのが、平成20年5月12日に発生した、中国四川省での大地震である。被災者1000万人以上、死傷者は10万人を超え、多くの命を奪う大惨事となった。毎日のように流れたニュース画像の中でも、地震により川の水路が堰き止められ、土砂の混ざった濁流が今間近と溢れ出しそうになっていた。最新の土木技術により洪水の被害は最小限に留められたのだろうが、古代においてはそんな重機や灌漑設備もない。大河を有する中国においては、歴史的に水との共存が人々の生活の根幹であった。古代の、しかも英雄の伝説が水に関することと深く関連する物語は、人類の繁栄と水との結びつきの深さの現れでもある。それは今も昔も変わらない。我々人間は、どんなに科学が進歩しようとも、地球の上に住んでいることに変わりはないのだ。
同じユーラシア大陸でも今度は西方。古代アラビアの話である。紀元300年頃、今のアラビア半島オマーンに位置する都市ウバールが消失した。交易都市だったというから、居住するに相応しい生存環境には恵まれていたのだろう。伝説では、ウバール人が強欲になり堕落したため、アラーが戒めのために都市を破壊したといわれる。伝説ウバールの所在は以来二千年近く不明であったが、現地遊牧民の夜話や詩集で語られ続けた。やがて1990年代になりようやく米航空宇宙局(NASA)の協力で人口衛星とレーダー解析により場所が特定された。それは何と砂漠の地中深くに位置し、綿密な発掘作業の結果、交易路や陶器、香炉、要塞まで見つかった。伝説の都市は、当時の大規模災害によって消失したことが解明されたのだが、同時に要塞跡の地下に巨大な石灰石洞窟が確認されたのだ。つまり専門家の見解によると、ウバールが地下の洞窟空間へと崩れ落ち、崩壊したという。しかもそれは、地下水を使いすぎたことで大規模な地盤沈下が起こり、都市ごと地下の奥底へ崩落した可能性が高いというものだ。
現代でも地盤沈下は地域の水と深い関わりのある問題だ。場所により様々その要因はあるものの、特に都市部で発生するそれは、工業用水や農業用水、消雪用水等利用のために、地下水を過剰に揚水することが原因であり、実質的に密度が薄くなった土地で、上部の建築物の重さに耐え切れなくなり、地上の町並み諸共に崩落するというものだ。その数、実に全国60箇所以上に及ぶ。
古代のどの例を通してみても、人間の所業は今も昔も変わらず、またその結果被る被害もまた、甚大に及んでいる。
我々は、こういった事態を静観しているわけにいかない。歴史に学んでしか、未来においての人間の発展はないのである。
しかし水は生活全てに関わっており、一度にその諸問題全てに触れるわけにはいかない。ついては本レポート(1)において、水にまつわるいくつかの主要な問題を指摘し、その原因及び今後の具体的な方策を検討(2)することにしたい。
今なぜ、「水」なのか。それは、水こそ人間を含む生命の根幹であり、人類の生存・繁栄に無くてはならないものだからである。世界を取り巻く驚愕の事実から、日本の対策を早急に打ち出さねばならない。
(世界の水事情)
地球という限られた空間に存在する我々としては、水の全体像の把握を務めなければならない。
“水の惑星・地球”といわれるが、実は我々の生存に直接必要な水、つまり利用可能な淡水の割合は極めてごく僅かである。世界水フォーラムをはじめとする各国の調査では、地球上に存在する水は、約13億8,600万立方kmという。その殆ど(97.5%)は海水(塩水)であり、淡水は僅かその2.5%程度にしか過ぎない。しかもその淡水割合の中には、北極や南極、またシベリアをはじめとする氷河や雪、永久凍土まで含まれるので、我々が活用できる水は全体の0.8%という。さらにその殆どが地下水として地中深くを流れているものであり、河川や湖沼水としてその表層に流れ手頃に活用できる水はなんと、全体の0.01%しかないということなのである。現在65億人程度である世界人口のうち、既に5億人が水に欠乏し、加えて15億人の人々は汚染や渇水による“水ストレス”を抱えている。更には、21億人の人々は、水不十分の環境下にある。アフリカやアジアの最も乾燥した地域の人々は、世界中でも水の困窮している環境下にある。実はその上で、更に問題がある。それは我々人間がいまだ増加しているということである。それも急増中している。2050年、世界人口は90億人を突破するとも言われる。そのような中で、現在でさえ5億人の水困窮人口が、慢性的な水不足になんと40億人もの人々が陥るという重大な可能性を指摘されているのだ。あくまでも予想、と言いたいところなのだが、これほど切迫した状況を、どれほどの人々が認知し、自覚しているだろうか。
水不足とは、国内水資源賦存量*で推計される。日本の近隣諸国でも韓国やインド、そして中国は水不十分の状態を迎えている。水不足は、食糧不足、不衛生、貧困…と様々な現実問題を引き起こす。それがゆえに、世界中で水の輸出入が既に展開されている。トルコから中東地域へ、アルプス山脈から南欧へ、カナダからアメリカ南部へと供給している現状がある。その方策は石油の代わりに水をパイプラインで運搬したり、巨大な袋に淡水を詰めて船で牽引したり、タンカーに水を積載し水不足の地域に輸出しているのである。
石油危機が差し迫った今日、それに取って代わるように水危機が国を超えて広がっている。
*国内水資源賦存量…
自然の水循環によって最大限利用可能な水資源の量。
年間の降水量から蒸発散量を差し引いた値で、実際には河川の流量や地下水への涵養量となり、人間が利用するもの。年間一人当たりの本量が3000立方mあれば水分量はほぼ十分とされ、日本は現在このランクに該当する。中国では年間一人当たり1700~2999の水不十分な環境に位置し、韓国やインドでは1000~1699という水ストレスを日常的に感じる環境下にあるといわれる。
(日本の水事情)
そのような中、「日本は問題ないだろう、洪水になるほど水はあるし。現に水道だって出る。」という声が聞こえてきそうである。北から南まで、水と緑に囲まれた国・日本―。そんな妄想を打ち砕く事実を紹介したい。
確かに他国に比べ環境は恵まれている。歴史の中でも日本は温暖多湿な気候と、それを生かした生活を行ってきた。特に江戸期には、欧米諸国が産業革命で燃料が木材から化石燃料と言われる石炭、石油に変わっていった。長い間日本は、少ない資源を工夫し生活してきた。使用分だけ山から木を伐採し、伐採分だけ自然の状態に戻すよう植林を励行してきた。こうした自然の循環の中で人間生活もその一部を活用させて頂く、自然と人間の共生社会を継続してきたのだ。しかし明治初期に3000万人程度であった人口はここ200年足らずで一気に4倍に増加した。史上誰しもが経験しない、考えられない人口増加である。そうした中の、水環境の変化がある。
日本の降水量は、世界の中でも恵まれているということは想像に難くない。世界平均の年間降水量が973mmに対し、日本のそれは1,718mm(昭和46年~平成12年平均値)である。しかしながら、一人あたりの一日の降水量は世界平均の59.7立方mに対し、14.0立方mと格段に少ないことが分かる。それでも一人につき、毎日水を満たした1m四方のハコが14個もあるのだと考えると余裕を感じるが、これは単純に降水量を人口で割った数値なので、お風呂・水洗トイレや洗物、また工業用水や農業用水、酪農やその他口に入る食物を作る際に必要な水の量はそこに加味されていない。ということは、人口比の水資源が如何に貴重かお分かり頂けるのではないかと考える。
それでも、一年のうち、殆ど水道は出る。それは違いない事実である。
ところが、である。実は我々日本でも、水不足は確実に進行しているのである。その多くは、まだ多くの人の目に晒されていない。
日本の地方都市の一つ、福岡地区。中でも福岡市を中心とする人口約250万人を抱える地区は、九州の中でも随一の商生活圏だ。実はそこに、水枯渇の現状がある。
何と、20~25万人もの人々が、自然から得た水を飲んでいない、というものだ。
元々福岡地区は、近郊に大きな河川を有しない地区であった。加えて人口の集中により都市化が進展、また市民の生活レベルの向上が伴い、年々水の枯渇が深刻化してきた。それは博多湾北部の宗像市から西は糸島地区の二丈町まで、南に至っては筑紫野市までの八市九町に至る。この地域の水、特に上水道の安定供給を目的として、既に昭和48年に対策が打ち出された。福岡地区水道企業団の設立がそれであり、平成9年には広域的水道整備計画にて海水の淡水化事業計画を検討、平成17年度から共用を開始しているのである。
当該地区約250万人に対し、およそ60%にはその居住域にある河川を引導する一般水源がある。しかし残りの40%に対しては、流量不足から他地域より導水を引くことで水を供給し、加えて建設した日本最大規模の海水淡水化施設「まみずピア」で“生産”した淡水を上水として配給している。その淡水量は、およそ日量4万トン。最大で5万トンというから、約25万人に相当する。裏を返せば、もし万が一何らかの理由で淡水化施設が突然停止した場合、直ちに25万人に相当する水量が供給出来なくなる。最も淡水化施設を通じて生産した水も、一度河川の水と混合し、上水道を通じて水を供給しているから、明確に25万人の世帯が供給されないわけではないが、全地域人口の60% にあたる一般水源がある地区も含め、地区全体とした場合でも、通常の10%以上の断水になることは明白なのである。
同様に、離島では更に深刻な事態だ。
沖縄本島においては、同様に水資源に対する人口や需要の増加が進み、昭和47年の需要量20万トン/日だったものが平成11年には43万トン/日と倍増している。結果、平成11年までの28年間で給水制限のあった年は半分の14年にも及ぶ。年毎に渇水状況も変動があるものの、最も厳しい情勢下では、年間326日の制限給水があったという。
断水により洗濯が十分に出来ず、風呂に入れず、また水道管に流れる水が少ないため蛇口をひねっても水が劣化する可能性がある。こうした生活全般に支障を来たすのはもちろんのこと、特に製造ラインに不可欠な水は企業における工業被害損失額に直結し、雇用問題にもつながる。更に顕著なのは季節により大量に水を使用する農業用水であり、特に春季に需要が大きく、夏の少雨を前にした渇水が春から秋にかけて慢性的に続く年もあるという。
大雨や洪水は目に付きやすくメディアにさらされることも多いが、実は慢性的にあるのは、水不足、という地味ではあるが現実的な問題が少しずつ我々の生活に脅威を及ぼしている。
(日本は水の大輸入国)
安全で美味しい水を手に入れる方法、それはミネラルウォーターを考え付くであろう。
日本ミネラルウォーター協会によると、現在日本では国産品が約600種類、輸入品が200種類、合計800種類ものミネラルウォーターが販売されている。1986年発売当初は8万キロリットルだった国内消費量(輸出輸入含む)は、2006年には235万キロリットルと、およそ29倍にまで増加した。その内、国外から輸入しているのは年間50万キロリットルにも及ぶ。しかも年々増加の一途である。国民均等に一人当たり計算しても年間20リットルはペットボトルからミネラルウォーターを飲んでいることになる。もちろん、赤ん坊からお年寄りまで含めての人口割りであるため、膨大な量であることを考えねばならない。おおよそ水道水の1000倍もの値段を拠出して我々はペットボトル水を買い求めている。水質の悪化と安全性への投資、はたまたファッション性など理由は様々であろうが、この大きな流れは、止まりそうもない成長市場である。しかし強調しておかなければならないのは、直接飲む水でさえ、これほどまでに輸入ニーズがあるのである。
直接口にする飲み水だけを想定していないだろうか。
水は農業の生産に必要不可欠な要素であることは繰り返し述べてきた。
農業自給率40%程度の国である日本は、裏を返せば水の大量輸入国であるとも言える。
それを、「バーチャルウォーター」という。
「仮想水」や「間接水」とも訳される言葉は、1990年代から使われだした言葉だ。つまりは、実際に他国で生産した農作物には大量の水を使用しており、間接的に大量に水の消費があることを指摘している。
この考えをもとに、国連が主要農作物について1キログラムの生産に必要な水の量を、以下表のように算定している。日本の主食である米は1キログラム生産するために約2656リットルの水を要する。牛肉の場合、1キログラムの生産に、15.98トンもの水が必要である。これは家畜の飲み水だけでなく、エサとなる穀物を育てるためにも大量の水が使われるためだ。
上記したように、世界人口は増大の途上にある。その中で世界の穀物需給が逼迫し、主要な農産物生産国で水不足が進行する中、農産物そのものの貿易の概念を超えた、“水資源としての農産物”の取引に制限がかかるような事態になりかねない。現在の日本国内の海外用水の使用量が570億立方mであり、上記のバーチャルウォーター概念に基づく水の輸入量は650億立方mとなり大きく上回ることになる。当然、途上国の需要増加により現在よりも大幅に農産品の輸入に制限がかかった場合、食に与える影響は計り知れない。かつ、その対策として異常に低下した国内農業の生産高を上げる方策は考えねばならないが、一層の日本の水不足を深刻化させることになる。日本の現実的で、かつ実務的な舵取りを今こそ求められている。業者や業界単位ではなく、まさに国家レベルの戦略が求められる課題である。
(海外資本の台頭)
改めて水にまつわる世界の情勢を鑑みると、世界の大資本による水関連ビジネスが急拡大していることに触れねばならない。何故なら、それらが日本の水環境を大きく揺るがすことに直結するからである。
世界の水供給ビジネスの本命は、上記したミネラルウォーター市場ではなく、水道事業及び海水淡水化関連事業などの淡水供給市場である。
世界には既に「ウォーターバロン(水男爵)」と称される圧倒的な力を持つ3社の水企業が存在している。フランスのスエズ社、ヴィヴェンディ社、及びドイツのRWE社が保有するイギリス本拠のテームズ・ウォーター社である。これらの3社をはじめとする世界的な水関連企業は、世界的な「水道の民営化」の背景として、あらゆる地域をターゲットに水供給事業を拡大している。かつて日本もそうであったが、水を治める者がその土地を治める感覚があったように、上下水道事業は公的セクターが担うべきとしてきた。しかし欧米先進国では過去、財政難のため老朽化した水関連施設の更新が難しい状況に直面し、サッチャー政権の下、電力・ガスに続き、上下水道事業も規制緩和の一環で開放したのである。公共分野を開放することで民間の業務効率化を図り、サービス向上を狙いとしたのである。こうした流れの中で、現在世界では「フルコスト・プライシング(水道事業にかかった費用を消費者から取り戻す)」という利用者負担の考えが打ち出されている。
国際調査ジャーナリスト協会によると、世界全体で民営企業が運営している水道の割合はまだ5%に過ぎない。しかし、イギリスでは既に100%民営化されており、フランス80%、ドイツ20%、米国35%という。アジアも既に10%に達しており、現在、韓国・中国で進行中という。
結果、何が引き起こされるか。
それは、運営する民営企業によって価格に大きく変動が生じ、また水を確保するための権益や設備への投資によって、価格が高騰する可能性がある、というものだ。もちろん安価な価格を実現するために企業活動は行われると信じたいが、そのためには、同じ市場内で同業者との競争原理が働くことが不可欠であり、また現在、税金を通じて公共投資で賄われる水道施設も、直接支払う必要が出て来ることになる。つまり、現在は水道使用量分の料金を支払えばよいが、税金の一部で賄われている水道関連の公共投資負担分も、民間の水道料金に跳ね上がる可能性があることを言及しておかねばならないのである。
(日本の水事業)
日本では2002年4月、改正水道法が施行され、公営企業の民営化や外資参入が始まった。民営化第1号として注目されたのが広島県三次市の下水道事業である。受託先は三菱商事と日本ヘルス工業が共同出資したジャパンウォーターという会社であるが、下水道処理の維持管理のみである。海外企業の進出はまさにこれからであろう。ただ、投資の観点として、今後人口減少がはっきり予測される日本の水道市場において、海外企業が進出するメリットはそれほど大きくないと考える。同じ投資価値を考えるのであれば、普及率や生活水準向上の考えられる中国や韓国のほうが進出の価値は大きいと考えられなくもない。
その際、日本として考えるべきは、現状の自治体負担分をどのように解消していくか、という問題がある。地方財政健全化法が一部施行され、新財政指標で自治体の財政状況が企業財務のように明らかになってくる。その際、必ず財務面で足を引っ張ってくるのは、公共病院と上下水道による赤字の計上である。双方とも民間参入が難しく、かつ公共の高い業務のため、これまで単独での採算性が取りづらいのは言うまでもないが、今後30年、50年というスパンで安全性と安定供給を図るならば、なおさら、経営基盤とその工夫が求められる。水道事業に限っていうと、問題はこれまでの経営の中で培ったノウハウや運営を行政内にしか蓄積していない、ということだろう。設備・供給・料金徴収・メンテナンス等の一連の業務ノウハウをどう民間に委託し、もしくは分割委託し、公と民で安定供給を実現するか、そこが日本の水市場においての特殊性といえるかも知れない。
(日本の水系管理)
水環境を語るには少なくとも、川の源流から河口までの水系をどう管理するか、という課題を検討せねばならない。そこにあるのは、行政の縦割り管理と、利権なのである。
たとえば、一級河川を例に川下から考える。
海に面する港湾でも、国交省、県、市と所管部署が分かれ、水産資源に関しては水産庁、自治体。流域に民間の淡水事業等を営めば厚生省、一級河川土手の維持管理は国交省であり、上下水道は自治体であるも、渇水等の場合必要な水量を決めるのは国交省、自治体土木整備果、企業関係団体、農業団体、そして自治体である。中流域まで遡ると河川によっては一級河川といえども管理は自治体に委ねられ、更に川の源流に至っては、源流に流れる水を育む山は林野庁、自治体、個人所有者と利害関係者だけでも多岐に渡る。こうなると、長期的なビジョンを持って、一つの水系に住む住民の安定的な生活を保障することが出来ず、ダム問題や渇水時の水配分の調整で汲々としている。日本の一級河川のうち、およそ半数が一つの都道府県で完結する河川という。ならば河川を中心に水の一括管理を進める方策が今後望まれるところである。
(水は、人間そのもの)
水、水といっても、人間にとって水の摂取が必要というよりは、人間は水そのもの、といってもいい過ぎではないほど、水分で占められている。
成人男性では、体重の約60%、女性で55%程度が水分にあたる。水の質量は1であるから、体重×60~55%が、自分の身体に含まれる水の量というわけだ。更には、生まれたての赤ちゃんは全体重の75%もが水分である。
同時に成人にとっては、一日に2.5リットルの水が必要といわれている。ということは、体重65キロの成人男性で、単純に水が人間の身体を通過して出て行く構図を考えると、15日少々で完全に体内の水が入れ替わることになる。発汗や尿、そして血液の循環を考えると、如何に水が大自然の中を巡り、そして身体の中を巡っているかがよく分かる。
自然環境全体を考えると、化石燃料の場合は数万年の蓄積を一挙に人間が消費している。しかしながら水の循環は、たとえば海水が蒸発し、雲となって陸地で凝結し、雨となって地上に降り注ぎ、河川や地下、植物や動物を巡ってまた海に帰る構図を考えると、如何に早いサイクルで回っているかが容易に想像できる。翻して考えると、日本人に昔からあった水の清めの精神は、実は十分に的を得たことである、とも言えるかも知れない。清浄な水環境で生きることが出来れば、体内を流れる水についても清浄な水が流れ、それがひいては体内の過半数を占めることになる。科学以上の精神性も加味すれば、極めて合理的な循環の中で身を置き、自然と人間の共存が図られてきたといえる。やはり水は、生命の源、なのだ。
だからこそ、水を包む環境を大きな視点で見、かつ長期的なビジョンに基づき安定的に安全な水を供給できる方策を検討せねばならないのである。
(次稿に向けて)
本稿においては、世界の水事情から紐解き、日本の置かれた水環境における問題点の表層を洗い出してきた。ついては、第二部において今回の問題点に対し、どのように解決を図っていくのか、その糸口を検討したい。具体的には、水の官民共同経営、淡水化を中心とする水関連ビジネスのメリット・デメリット等を中心に考える。
水の切り口によって、行き詰まる多くの自治体経営の問題と可能性を示すことが出来るものであろう。引き続き、住民に最も身近で、かつ必要不可欠な、安定供給を求められる水の環境整備のあり方を検討して参りたい。
【参考文献】
「世界の水が支配される」国際調査ジャーナリスト協会 佐久間智子訳 作品社
「水の世界地図」Robin Clarke and Jannet King 沖大幹訳 丸善株式会社
松下幸之助発言集
国連 世界水発展報告書2006
国土交通省 日本の水資源 資料
国土交通省中部整備局 個別研修資料
福岡地区水道企業団 個別研修資料
中西祐介の論考
Thesis
Yusuke Nakanishi

第28期
中西 祐介
なかにし・ゆうすけ
参議院議員/徳島・高知選挙区/自民党