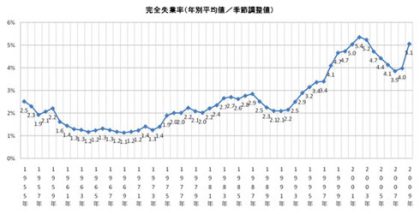Thesis
昭和は遠くになりにけり ~過去との対話から未来を開く~
平成元年生まれが成人式を迎える。すでに平成生まれの新入社員が入ってきている職場もあるだろう。「昭和は遠くになりにけり」。今、薄れゆく昭和の記憶をもう一度しっかり見つめなおす時期がきているのではないだろうか。
<はじめに>
平成元年生まれが成人式を迎える。すでに平成生まれの新入社員が入ってきている職場もあるだろう。まだまだ若いつもりの昭和48年生まれの私にも「昭和は遠くになりにけり」の思いが芽生える。この言葉は、「降る雪や明治は遠くなりにけり」を拝借させていただいた。中村草田男の第一句集『長子(ちょうし)』(昭和11年)に収められている。「昭和」、それは私の両親が生きた時代でもある。特に昭和の前期においての戦時中、終戦後の体験談は何度も聞かされてきた。
戦後60年以上が過ぎ、戦争を体験した人たちがどんどんこの世を去っていく。そしてリアリティが失われていく。しかし、靖国問題、日中関係をはじめとする様々な戦争に絡んだ問題が今なお大きく我々の前に立ちはだかっている。現在の日本の教育のなかでも大正から昭和、現在に至る歴史教育は頼りないものがあると私は思っている。扱う内容もそうだが、私自身の経験でも、このあたりの歴史は学年最終の3学期に時間切れとなり、「後は自分で教科書を見ておくように」と尻切れトンボで終わってしまった記憶がある。イギリスの歴史家、E.H.カーはその著書『歴史とは何か』の中で「歴史とは現在と過去との対話である。現在に生きる私たちは、過去を主体的にとらえることなしに未来への展望をたてることはできない」と語っている。今、薄れつつある歴史の記憶をもう一度しっかり見つめなおす時期がきているのではないだろうか。
<父母から聞く思い出の昭和>
父は1925年(大正14年)生まれ。母は1935年(昭和10年)生まれ。太平洋戦争(大東亜戦争)の終戦は1945年(昭和20年)なので、父20歳、母10歳のときである。私の世代でこの時代を実体験している親をもっているのは珍しいのではないか。
「霞ヶ浦にあった予科練にあこがれていたけど、目が悪くて入れなかった」という父。そのころの子供はみな、「日本男児は兵隊さんになってお国のために働くのだ」ということが喜びであり、疑問をもったことはなかったそうだ。父は兵隊に入ったものの、戦場に出ることはなく終戦を迎える。父の兄(私の伯父)二人はそれぞれ東南アジアの島で終戦を迎えたそうだ。終戦後は「とにかく貧乏で食うものには困った。貧乏のつらさが身にしみた。お金は大切にしなさい。1円を笑うものは1円に泣くということを覚えておくんだ」と、私は幼い頃から何度も聞かされていた。
「時代の過渡期、過渡期を生きてきた」というのが母の口癖。「弟(私の叔父)をおぶって母さん(私の祖母)と食料を調達しに行ったのよ」、「戦争に負けてからは全部の価値観がひっくりかえっちゃった。学校に行って最初にやったことは教科書の文章を墨で消していくことだったのよ」と笑いながら話していた母だが、当時の生活の苦しさは二度と味わいたくないとも。岩手県北上の山奥、和賀仙人という地に疎開していた母は、「ある日B29が飛んできたのね。そしたらあなたのお祖父さんが、『ここまで飛んでくれば日本は負けたな』って言っていたわ」という話も聞いたことがある。
戦時中の体験は両親にとって、大きな苦労と、耐え難い思い出として語られていた。時代を必死に生き抜く両親の姿が浮かぶ。ぽろぽろと出る当時の思い出話の一つ一つが今、あらためて思い出される。そして二人とも「今の日本は平和でいい時代だよ。やりたいことは何でも出来るんだから」としみじみと話していた。終戦までのこの激動の昭和前期、約18年とおよそ8ヶ月に及ぶ期間とはどのような時代だったのであろうか。
<昭和の戦争の軌跡>
日中戦争、第二次世界大戦、太平洋戦争(大東亜戦争)と名づけられる昭和時代の戦争とはどんなものだったのか。時代の大きな出来事を追って簡単に確認したい。
1926年(大正15年)12月25日、大正天皇が崩御し昭和と改元される。1930年(昭和5年)、世界恐慌の余波で昭和恐慌へと突入する。国民は貧困に苦しみ、失業による自殺や一家心中が急増し、学校に弁当を持参することができない「欠食児童」が問題となった。こうした国民の不満は、1930年代の急速な軍部の台頭を招く空気を作っていく。
翌年、1931年(昭和6年)奉天(瀋陽)北郊の柳条湖で南満州鉄道の路線が爆破された。満州事変の勃発である。今日、この事件が関東軍による自作自演だったことが明らかになっている。それに気づいていた日本政府は、閣議で事件の不拡大を決定したが、関東軍はこれを無視。戦火は拡大へと突き進んでいく。
このような日本の行動に対して諸外国は当初、一定の理解を示していた。しかし、同年におきた上海事変をきっかけに状況は一変する。国際連盟からの脱退を通告した日本は国際社会から孤立し、ワシントン体制から離反していく。出口の見えない不況に加えて、国際社会から孤立するという新たな問題を抱えた昭和初期の日本。そんな中、国民の支持を得て力をつけてきた軍部は政治や財界に対するテロを引き起こしていく。
中でも有名な事件は1932年(昭和7年)に起きた、犬養毅首相が殺害された五・一五事件であろう。また、1936年(昭和11年)、武装した青年将校が首相官邸、陸軍大臣官邸などをいっせいに襲撃した二・二六事件も。事件をきっかけに軍の発言力が強まっていき、政治的な圧力を強めていくこととなる。
1937年(昭和12年)から8年間にもおよぶ日中戦争の口火が切られたのはそんな中でのことである。北京郊外の盧溝橋付近で夜間演習をしていた支那駐屯軍歩兵第一連隊第八中隊に向けて、中国陣地から実弾が飛来した。盧溝橋事件である。この事件をきっかけに中国との事実上の全面戦争に突入する。
日中戦争が行き詰まりをみせる一方で、欧州で勢力を拡大していたのはドイツ。1939年(昭和14年)、ドイツがポーランドへ侵攻し、独ソはポーランドを分割。ここに第二次世界大戦がはじまる。さらにドイツはデンマーク、ノルウェーを制圧。さらにオランダ、ベルギー、ルクセンブルクに攻め入った。そしてその勢いのままパリを陥落させ、イギリスにも激しい爆撃を加えた。東アジアを支配していたフランス、オランダが敗北したことが、日本の東南アジア戦略にも影響を与えていく。スローガンを「東亜新秩序」から広く東南アジアを含む「大東亜新秩序」に拡大。日本は南進を開始した。そして1940年(昭和15年)日独伊三国同盟が締結される。日本の行動に怒ったアメリカは日本への輸出制限を始めるとともに、中国やイギリスへの援助を強化した。日米の関係は次第に悪化していき、開戦は避けられなくなっていく。
そして1941年(昭和16年)、日本海軍の航空隊はハワイ・オアフ島の真珠湾を奇襲。太平洋戦争(大東亜戦争)が始まる。日本軍は開戦からわずか6ヶ月で東南アジアの主要部を含む、太平洋沿いの広大な地域を占領した。快進撃を続けていた日本軍が転機を迎えたのは、1942年(昭和17年)のミッドウェー海戦だった。暗号解読によって事前に動きを察知していたアメリカ海軍によって、日本軍は主力空母4隻が撃沈され、3500人の兵を失った。この結果、太平洋正面における日米の形勢は一気に逆転した。
緒戦における日本の勝利は、奇襲作戦の成功とアメリカ側の準備不足によるところが大きかった。しかし、大本営と政府はともに日本の力を過大評価し、戦線拡大へと突き進んでいく。日米の国力の格差(1941年における日米のGNP比と鉄鋼生産量比は約12倍)は、戦争が進むにつれてそのまま戦力格差となって表れていく。
戦局の悪化により、防戦一方の日本軍は戦線縮小を決定。マリアナ諸島の陥落で東條英機内閣が総辞職となる。日本の国土は連日の空襲で、町は焼け野原と化していく。そして本土決戦を目前にアメリカが広島、長崎へと原爆を投下。さらにソ連が対日宣戦する。1945年8月15日正午、ラジオを通じて昭和天皇の肉声による「終戦の詔勅」が放送された。日本は降伏し、ここに太平洋戦争は終結となる。
簡単に書いてはみたものの、一つ一つの事件の相関関係は複雑で、見方も様々だ。書いてみてあらためて思ったことは、歴史を客観的に表現するのは難しいということである。しかし、史実を丁寧に見ていくと、日本が戦争を引き起こしていく過程には、一部やむ終えない状況があったのではないか、という思いも沸き起こる。
<松下幸之助塾主にとっての昭和の戦争>
塾主も同様に戦争を体験し、平和な世の中への希望を強く持っていた人である。終戦時には、私の両親よりずっと年上の50歳。この時をきっかけにPHP活動を始めるのである。塾主にとっても大きな転換期となる体験だったのだ。
著書『PHPのことば』には終戦後の見聞を引いて、その活動の動機を以下のことばで綴っている。
「法を守ってヤミの物資を買わなかった判事さんが餓死するという悲惨な事件もあったわけです。そういった姿を見、また私自身も体験させられているうちに、よくわからないながらも、“こんなバカなことはない。どこかまちがっている。人間とは本来もっと尊く偉大な存在であって、お互いの自覚と協力いかんによっては、もっと平和で豊かで幸せな生活を送れるはずだ”という思いが日一日とつよまってきたのです。そして、そういう思いを多くの人びとに訴えてみたいという、矢も盾もたまらない気持ちから、PHPすなわちお互い人間の真の繁栄と平和と幸福を求める研究と啓蒙の運動をはじめるようになったというわけです」。
松下電器自体も戦時中、軍へ協力したものの戦後その資金が回収できなくなる。さらに財閥にも指定され、会社は解体の危機、塾主は公職追放並びに個人財産の凍結という事態になってしまう。塾主いわく「日本で一番の借金があったと思う」。ある方が塾主宅に伺って冷蔵庫の中をみたら芋のつるしかなかった、というエピソードもある。そんな体験の中から「繁栄、平和、幸福」への強い気持ちが芽生えたのだろう。
こうした「繁栄、平和、幸福」への思いは、当時の多くの国民が抱懐するところであった。そしてそれが日本人本来の姿なのだと、塾主は日本の伝統精神を顧みて語っているのである。「なるほど日本は戦争に負けた。そのために戦争をしてはならない、と心から反省することはまことに結構である。しかし、その反省するのあまり、今まで長いあいだ“和を以って貴し”としてきた日本人の基本的な精神が、その根底に流れていることを忘れてしまって、なんだか日本が好戦国であるかのごとく、またそういう精神を伝統的にもっているかのごとく考えるようなことがあるとするならば、それは自己認識の不足もはなはだしいと思うのであります」。終戦後、混乱の空気の中で、日本人本来の姿を過たず、前向きに見据える塾主の歴史観・日本人観は現在なお学ぶことが多い。
<日本政府の歴史見解について思うこと>
昭和前期は日本にとっても世界にとっても、20世紀のもっとも重要な時期にあたっている。それは原爆の発明と投下にみられるように、人類が新たな段階に足を踏みいれた時期ということが言えるのではないだろうか。それだけにその観点に立って、日本人は日本人なりに歴史を総括しなければならない立場に置かれている。
現在の政府の歴史見解は、平成7年8月の村山富市総理の談話をそのまま踏襲しているようである。「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで、国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました(後略)」として全面的な反省とお詫びで括られた談話だ。
この談話の外交的、政治的な意味は大いにあると思う。しかし私が憂えるのは、これからの日本人が、特に戦争体験を持つ身近な人と接することがなくなっていく私よりさらに下の世代の人たちが、この村山談話の歴史観、歴史認識の範囲のみで教育が施され、昭和の戦争の歴史を捉えていくことは問題が多いということである。ここに示される歴史観は、史実に対してあまりにも硬直的であり、日本人の誇りも失われてしまうのではないだろうか。
過去の歴史を反省することは必要だが、それが一方向的で、必要以上に自分たち自身を矮小化するようなものでは建設的な未来を創ることはできない。塾主は「敗戦後はそういう誇りもなくなって、この日本民族、あるいは日本の歴史はつまらんものであったと言い出して、みずからを卑しめるわけではありませんが、非常に誇りを傷つけるような考え方が一部に横行しておったと思うんです。したがって歴史を書くにしても、素直な状態で過去の歴史に対しているかというと、そうではないと思うんです」と語っている。
そうした目で見てみると、昭和の戦争はあってはいけないものであったが、当時としては、やはりそれなりの理由もあって戦争に踏み込んだのだという一面も大いに議論されてよいのではないだろうか。当時を知る人たちが高齢化し亡くなっていく中、現在に生きる我々が思考停止の状態であってはならない。村山談話が示す「昭和の戦争は日本の侵略戦争。日本が全面的に悪かった」との歴史観をそのまま受け入れるのではなく、改めて主体的に歴史を見てゆく必要があると思うのだ。
先に紹介した歴史家、E.H.カーは「ある歴史的事件は一つの視点や原因から構成されているものではなく、様々な事象、長期的・短期的事象から構成されている複雑なものである」と言う。その上で、「諸原因相互の関係を整理し、そのなかで、結局のところ何を究極的原因とみるべきか」という一連の思考の重要性を語っている。そして「完全な歴史」というものは無いが、「永続性のある、もっと完全性と客観性が多い歴史を書くこと」への努力を促している。
日本の戦争への責任は大いにあり、それから逃れることはできない。英語で「responsible」という言葉は一般に「責任をとる」と訳される。そしてさらに「返答できる」、「回答できる」という意味もある。昨今盛んに唱えられている「説明責任」と訳される「accountable」も同様の意味を持っている。このことは「責任をとる」とは「ひたすら謝る」とか「一方的に自己の正当性を言い募る」ということではないのである。なぜそのようなことが起こったのかを史実にもとづいて検証し、今一度、自分の頭でしっかり考えることが大切なのだ。
<旧満州国首都・長春と盧溝橋に降り立って>
2008年11月20日、気温マイナス14℃、雪の長春に降り立った。長春は旧満州国の首都、新京と呼ばれた街。旧日本軍の傀儡として清朝最後の皇帝となった溥儀の皇宮を訪れる。ロの字型の皇宮の中庭に杏の木が植わっている。溥儀は杏が好きだったそうだ。それと、口の中に木で困る、口の下に木で呆。「杏が好きな、阿呆が、困った場所」という自虐的な意味もこめられているそうだ。時代に翻弄された溥儀と夫人の人生を偲ぶ資料が多く所蔵されていた。さらに私達は国務院やその他、満州国時代の様々な建造物や場所を訪ね、当時に思いを馳せた。
翌21日には北京郊外にある盧溝橋へと足を向ける。日中戦争の引き金になった事件の舞台だ。マルコポーロ橋(盧溝橋)のすぐ手前には抗日戦記念館がある。現在は少し展示物の内容が変わったということだが、旧日本軍の残虐さを物語る写真が多く展示されている。江沢民国家主席時代の抗日政策の影響で、その時代に教育をうけた若い人たちの間での反日感情は根強いという。歴史を語り継ぐことは大切だ。しかし、意図的で行き過ぎた歴史教育での歴史観は長い目で大きな障害となるであろう。マルコポーロ橋から盧溝橋事件の引き金となった旧日本軍の演習場所を眺める。書籍で位置関係を確認したが、その風景は当時とほとんど変わっていないようだ。書物から得る歴史とは違う臨場感。
研修の一環としての歴史観ツアーであったため、個人的なつながりを重視した地への旅とはならなかった。しかしそれでも、この時代を生きた父母への思いは深まった気がする。今後、両親が戦時中過ごした地や伯父達が終戦を迎えた東南アジアの島へも足を運んでみようと思っている。そうすることによってより深い理解へとつながっていくのではないか。
<おわりに>
私の両親は10も歳が離れているのに仲良く2006年9月と11月に時をおかず他界した。二人の葬儀に参列してくれた人たちから、私の知らない両親の思い出を聞いた。亡くなって「もっと話しを聞いておけばよかった」と悔やまれる。両親から語り継がれる昭和はまさに生な実体験の歴史だった。
人は過去を無視して生きることはできない。それにも関わらず、関心も寄せず、思考停止のままステレオタイプの昭和の戦争史観を受け入れている現在の状況を、自分のことも含めて反省したい。歴史の事実をしっかり認識し、自分の頭で今一度考え直すことが大切だ。もし自分がその時代に生きていたらどのような生き方をしていたのだろうか、ということを想像することで、その時代の温度も感じることができるのではないだろうか。そして私たちの父母、祖父母の世代がどのように生きたのか、それを次世代に伝えていくという姿勢が大切なのである。過去との対話の上に、新な歴史が開かれていかなければならないのだ。
参考文献
PHP総合研究所研究本部「松下幸之助発言集」編纂室『松下幸之助発言集 全45巻』 PHP研究所 1993年
佐藤悌二郎『松下幸之助 成功への軌跡』 PHP研究所 1997年
E.H.カー著・清水幾太郎訳『歴史とは何か』 岩波書店 1962年
保阪正康『昭和史入門』 文藝春秋 2007年
後藤寿一『日本人として知っておきたい 早わかり近現代史』 PHP研究所 2007年
中村粲『大東亜戦争への道』 展転社 1989年
北村稔・林思雲『日中戦争』 PHP研究所 2008年
鳥海靖『日・中・韓・露 歴史教科書はこんなに違う』 扶桑社 2005年
坂本多加雄『歴史教育を考える 日本人は歴史を取り戻せるか』 PHP研究所 1998年
半藤一利『昭和史』 平凡社 2004年
前野徹『新歴史の真実』 経済界 2003年
大谷明の論考
Thesis
Akira Ohtani

第29期
大谷 明
おおたに・あきら
茨城県ひたちなか市長/無所属
Mission
地域主導による地域経済の活性化