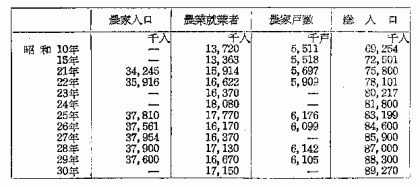Thesis
新しいアジア~日本の歴史観試論~(3) 近代日本の歴史パラダイムの転換
西欧的な優れた文化価値を、より大規模に実現するために、西洋をもう一度東洋によって包み直す。東洋の力が西洋の生み出した普遍的な価値をより高めるために西洋を変革する。これが今の問題点になっている。これは政治上の問題点であると同時に、文化上の問題である。日本人もそういう構想を持たなければならない。(竹内好)
1. はじめに
本稿は、日本のアジアをめぐる自画像がどのような変遷をたどり、どのような転換点を経てきたのかを検討することを目的とする。これまで序章において、明治以降の「アジア主義」と「脱亜論」の系譜を辿ることによって、方法論こそ違うものの根底の部分で「欧米に対するアジア」という自画像があったのではないかということを検討してきた。
さらに前回稿では、先の大戦によって日本が自らの自画像を描ききれない中で、ナショナル・アイデンティティーを模索し、「喪失したアジア」にならざるをえなかったことを検討した。しかしながら「欧米に対するアジア」の自画像の根底にあった「屈辱のアジア」という自画像は依然として消えてなかったのではないかということもあわせて論じた。
続く本稿では、かつてのアジアのイメージであった「停滞」や「貧困」、「専制(独裁)」というものが、いまや「発展」「繁栄」「民主化」に転換したという事実を踏まえ、その転換点はいつだったのかを検討するものである。転換点は何を分析の対象とするかによって異なり、いくつかの転換点が挙げられることになる。検討のためには、日本自身の転換だけでなく、国際環境の変化や現時点で行われている東アジア共同体に向けた動きも考慮に入れなければならないが、まず日本自身の転換点をいくつかの事例や文献に書かれているものを紹介していく。その際、日本の転換点をあげる前に、そもそも近代日本の歴史パラダイムの起源を探ることからはじめる。
2. 近代日本の歴史パラダイムの起源
-「欧米に対する」以前のアジア、西洋の呼称から自己の呼称へ
本稿は日本における「アジア像」の変遷を辿ろうとするものであるが、一体「アジア」という言葉はいつから使われたのであろうか。「亜細亜」という言葉自体は、マテオ・リッチの『坤與万国地図』(1620年)の伝来や、1708年に日本に上陸したイタリア人宣教師シドッティの供述などから日本にもたらされたという。西川如見が著した『日本水土考』(1700年)では、「亜細亜大洲図」と記した地図と説明があった。日本は「亜細亜アサイア」の東端にあって、「朝陽始めて照らすの地」にして「水土」が優れており、そのために人は「勇壮」かつ「仁愛」に満ちていたという。新井白石はシドッティを尋問して記録した『西洋紀聞』(1715年)を著したが、その中巻や『采覧異言』(1713年)の中で、「亜細亜」や「亜細亜ヤアスイヤア」という表現を用いている。つまり「亜細亜」、「アジア」という呼称は西洋からもたらされたものなのである。現在では使われなくなった中国の呼称である「支那」も、西洋からの呼称であり、以前は地理的認識を妨げないために利便性があるとして使用されていた。この他者からの呼称は当時の蘭学者や儒者の間で議論されていたという。例えば、山片蟠桃は「大秦国(ローマ帝国)を日の入る処に近しとし、扶桑国(日本)を日の出る処と云。日本の名も本よりこれよりをこる」として、日本の呼称もおかしいと指摘した。日本の自称(本名)はそもそも「やまと」であって、日が出るという意味の「日本」という字は渋々承認されるにすぎないのである。
さらに会沢正史斎は、「西夷は其の地を分けて、亜細亜州・欧羅巴州・阿弗利加州と称すれども夷輩の私に名づくる所にして、天朝にして定め給へる呼称にもあらず、又、上古より定りたる公名にも非るなり。今、彼が私に称する所の亜細亜等の名を以て、神州までをも総称するは悖慢の甚だしきものなり。」と述べて、それぞれの国名は自ら称するものを用いるべきで西夷の私称を用いるべきではないとしている。蘭学者は利便性から「亜細亜」という呼称を用いたが、当時の知識人にとって西洋に対抗するためには「亜細亜」という呼称は拒否するべきものであったのである。
本稿で取り上げている「アジア」とはもともと欧米によってもたらされた呼称でありながら、「アジア主義」として用いられた頃にはすでに自らの呼称として転換を遂げていたことになる。幕末の時点では未だに、「そもそもなぜ日本が『亜細亜』に含まれねばならないか」という徳川時代の思想を継承していた。福沢諭吉先生のアジア論にもその傾向が見られる。1884年3月の『時事新報』において福沢先生は、「日本は支那の為に蔽はれざるを期すべし」と題した論文で、「蓋し西洋人が外国を看るには其国民、知徳の高卑を問はず、其歴史の新旧を論ぜず、唯目下自国に関係する利害の大小軽重を標準にして判断を下すものなるが故に、先ず第一に地図を披て日支の位置を見れば、甲は区々たる蜻蜒形の一島嶼、乙は堂々たる亜陸の一大国、東洋の形勢を知らざる者の考へにては、日本は恰も支那の属島の如くに思い込み…恰も東洋の名號は支那の為に私せられたる者となるべし」と、「そもそもなぜ日本が『亜細亜』に含まれなければならないか」という疑問を呈している。さらに、日本の努力次第では是正することが可能であることを次のように述べている。
「尤も日本現在未来の文明に於て、一歩も支那に譲る可らざるは我人民の覚悟にして、且つ実際に難きことに非ずと雖も、彼の支那国は土地広く人民多く物産豊かに、又外交事件の広く大にして、毎々西洋人の耳目に感じ易く、俗に言わば所謂見栄へのする国柄にて、此丈は之を支那国の仕合なりと云わざる可らず。然るに我日本国は人民の知徳こそ支那人に愧ぢざれども、土地人口将た物産の支那に及ばざるは無論、又外交事件の紛議葛藤に至ては、開国以来嘗て之が為に大敗北を取りたることもなければ又大勝利を得たることも非ざれば、何分にも人に知らるるの機会なきなり。唯我国人が金城鉄壁とも恃むべきは、愈々益々進んで西洋の文明を用ゐ、貿易を拡め国権を張り、堂々正々、最も名誉あり最も光輝ある文明の手段に依頼するの外ある可らず」
福沢先生のアジア論は、「文明」の高みから日本の現状や「亜細亜」を非難し自らは非難されない警告者の優位性を得ようとするねじれた自尊心の産物としての論ではなく、徳川期の議論における「亜細亜」という呼称への違和感を、「自由」と「文明」の原理を日本の歴史の中に探ろうとする努力と結び付けているものであると言えるのではないか。一方で福沢先生は、1869年に『世界國盡』の「亜細亜州」の中で、次のように述べている。
「『支那』は『亜細亜』の一大国…そもそも『支那』の物語、往古陶虞の時代より、年を経ること四千歳、仁義五常を重じて、人情厚き風なりと、その名も高く聞こえしが文明開化後退去(アトズサリ)、風俗しだいに衰て、徳を修めず知をみがかず、我より外に人なしと、世間知らずの高枕、暴君汚吏の意にまかせ下を抑えし悪政の、天罰遁るるところなく…支那の政事の立方は、西洋の語に『ですぽちっく』といへるものにて、唯上に立つ人の思ふ通に事をなす風なるゆえ、国中の人皆俗にいふ奉公人の根性になり、帳面前さへ済めば一寸のがれといふ気にて、真実に国の為を思ふ者なく、遂に外国の侮りを受るよふになりたるなり」
このような福沢先生の「支那」と「日本」を明確に分け、「亜細亜」への違和感を日本の歴史的経験につなげる論とは若干異なるものの、この時期には、「亜細亜」イコール「デスポチック」(独裁的、専制的)という図式はこの頃から語られるようになった。箕作麟祥はモンテスキューの『法の精神』を翻訳して「亜細亜州」がなぜ「圧制と隷属」の原理を支配しているのかを紹介している。西周は「国民気風論」で、「亜細亜風の奢侈又亜細亜風の専擅」を問題にしており、日本人の「忠諒易直」の性質が「支那」よりも甚だしく、隷属的気風を強めると述べている。さらに日本人は人種的に「模擬に長じて思索発明に短」で、大陸文化の強い影響下にありながら創造的な知的活動を生み出した英国と比べてはるかに見劣りがすると述べている。遅れた「亜細亜」の中でも日本は一層「亜細亜」的かもしれないと表明しているのである。つまり「亜細亜」という言葉の中に、日本の自画像も見出されつつあったと言うことができる。
1890年代には徳川期以来の知識人が強く意識した中国・朝鮮と日本との社会的歴史的違いや「亜細亜」がそもそも西洋の呼称であったという違和感は消し去られている論説がみられるようになった。1892年2月に政教社の雑誌『亜細亜』に掲載された、「亜細亜旨義とは何ぞ」と題した論説では、「亜細亜の東海に位置し、亜細亜諸国に先ぢて其の文物を完美に」した「先覚としての日本」、という主張がなされている。同じ政教社の『日本人』に掲載された、「亜細亜経論策」では、欧州の争いに乗じた「東洋革命」すなわち「黄色人種」の「一大新国を創設」する「革命」のリーダーは、欧米の「文明の精神」と東洋の「野蛮の身体」をあわせもつ日本こそがふさわしいと主張しており、「アジア主義」の萌芽がそこにみられる。
「亜細亜」という言葉はそもそも西洋からもたらされたものである。だからこそ、日本を「亜細亜」の一部とすることに日本の知識人は当初、違和感を持っていた。その「亜細亜」の中に日本の自画像が見出され始めたのが19世紀後半の日本であったということができる。「亜細亜」という言葉の使い方によって、「脱亜」と「アジア主義」との間で意味合いが異なることが明らかになったが、両主張の根底部分では共通していた「欧米に追いつけ追い越せ」という日本の近代化プロセス、「欧米に対するアジア」という近代日本の歴史パラダイムはここから始まったといえるのではないか。
それではその近代歴史のパラダイムはいつ転換期を迎えたのであろうか。先の大戦の直後では、自らのアイデンティティーを模索するために、アジアという自画像を喪失せざるを得ない状況であったと、前回稿で述べたが、「繁栄のアジア」という自画像に転換するには至らなかった。以下では、戦後日本のいくつかの転換点をあげることによって、近代日本の歴史パラダイムの終焉していく過程を検討していく。
3. 日本の自画像の転機、「繁栄のアジア」の起源
-1956年経済白書「もはや『戦後』ではない」
1956年7月に公表された「経済白書」の中に、あまりにも有名になった言葉が織り込まれた。「もはや『戦後』ではない」という一節である。しかしこの言葉の前後までを吟味している評論はあまり存在しない。少し長いが現在にも通ずる貴重な資料なので、前後の全文を次に引用する。(下線部は筆者によるもの)
「戦後日本経済の回復の速やかさには誠に万人の意表外にでるものがあった。それは日本国民の勤勉な努力によって培われ、世界情勢の好都合な発展によって育まれた。 しかし敗戦によって落ち込んだ谷が深かったという事実そのものが、その谷からはい上がるスピードを速やからしめたという事情も忘れることはできない。経済の浮揚力には事欠かなかった。経済政策としては、ただ浮き揚がる過程で国際収支の悪化やインフレの壁に突き当たるのを避けることに努めれば良かった。消費者は常にもっと多く物を買おうと心掛け、企業者は常にもっと多くを投資しようと待ち構えていた。いまや経済の回復による浮揚力はほぼ使い尽くされた。なるほど、貧乏な日本のこと故、世界の他の国々に比べれば、消費や投資の潜在需要はまだ高いかもしれないが、戦後の一時期に比べれば、その欲望の熾烈さは明らかに減少した。もはや「戦後」ではない。我々はいまや異なった事態に当面しようとしている。回復を通じての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支えられる。そして近代化の進歩も速やかにしてかつ安定的な経済の成長によって初めて可能となるのである。
新しきものの摂取は常に抵抗を伴う。経済社会の遅れた部面は、一時的には近代化によってかえってその矛盾が激成されるごとくに感ずるかもしれない。しかし長期的には中小企業、労働、農業などの各部面が抱く諸矛盾は経済の発展によってのみ吸収される。近代化が国民経済の進むべき唯一の方向とするならば、その遂行に伴う負担は国民相互にその力に応じて分け合わねばならない。
近代化–トランスフォーメーション–とは、自らを改造する過程である。その手術は苦痛なしにはすまされない。明治の初年我々の先人は、この手術を行って、遅れた農業日本をともかくアジアでは進んだ工業国に改造した。その後の日本経済はこれに匹敵するような大きな構造変革を経験しなかった。そして自らを改造する苦痛を避け、自らの条件に合わせて外界を改造(トランスフォーム)しようという試みは、結局軍事的膨張につながったのである。
世界の二つの体制の間の対立も、原子兵器の競争から平和的競存に移った。平和的競存とは、経済成長率の闘いであり、生産性向上のせり合いである。戦後10年我々が主として生産量の回復に努めていた間に、先進国の復興の目標は生産性の向上にあった。フランスの復興計画は近代化のための計画と銘うっていた。
我々は日々に進みゆく世界の技術とそれが変えてゆく世界の環境に一日も早く自らを適応せしめねばならない。もしそれを怠るならば、先進工業国との間に質的な技術水準においてますます大きな差がつけられるばかりではなく、長期計画によって自国の工業化を進展している後進国との間の工業生産の量的な開きも次第に狭められるであろう。
このような世界の動向に照らしてみるならば、幸運のめぐり合わせによる数量景気の成果に酔うことなく、世界技術革新の波に乗って、日本の新しい国造りに出発することが当面喫緊の必要事ではないであろうか。」
この経済白書を発表した当時の経済企画庁長官の高碕達之助は、白書の前書き部分で、昭和31年度の白書の主題を「復興過程を終えたわが国が、経済の成長を鈍化させないためには、如何なる方途に進まねばならぬか」として取り上げ、その方向性は「日本の経済構造を世界の技術革命の波に遅れないように改造してゆくことである」と述べている。つまり白書の本文でもあるように、「今後の成長は近代化によって支えられる」ことを強調しているのである。
さらに高碕は同年、経済企画庁が発表した「国民生活の変貌」という文書で、「消費生活においでは古きものから新しきものへの移行が激しい勢いで起っている」ことを明らかにしている点を取り上げ、「われわれはこの流れに積極的に棹さして日本の生産構造のみならず、貿易構造も、消費構造も新しく改編する意力を振るい起さねばならない。その仕事は恐らく明治の先覚者が、遅れた農業国日本をともかくアジアの先進国工業日本に改造した努力にも比すべきものであろう。いわば第二の維新ともいうべき大事業である。しかし困難さの故にその仕事を怠るならば、アジア諸国は容赦なくわが国に追いつき追いこすであろうことを忘れてはならない」と述べている。
白書の本文では明治の先人が「遅れた農業日本をともかくアジアでは進んだ工業国に改造した」点を評価しているものの、その改造が外部、つまりアジア諸国への軍事的膨張へと繋がったと指摘している。その理由はそれまでの日本が新たな構造改革を断行することを、自ら怠ったためであるとし、昭和31年に訪れた日本の経済構造(生産構造・貿易構造・消費構造)を改編する、「第二の維新」というべき大事業を行わなければ、アジア諸国に容赦なく追い越されると主張しているのである。
この時期の企業は軒並み業績が飛躍的に伸びている。例えば、松下電器の創業者である松下幸之助は、1956年1月の経営方針発表会で、「松下電器5ヵ年計画」を発表し、「昭和30年(1955年)現在で年220億円の販売高を、昭和35年(1960年)に年800億円に、従業員を11,000人から18,000人に、資本金を30億円から100億円にする」と述べている。構想の大きさに、全員は驚き、当時民間企業でこうした長期計画を発表するところはなく、各方面に大きな反響を呼んだという。この計画は、4年間でほぼ達成され、5年後の昭和35年(1960年)には、販売高1,054億円、従業員約28,000人、資本金150億円となり、目標をはるかに上回ったという。
政治的にもこの時期は大きな転換期を迎えており、大規模な政界再編が進んだ。前年の1955年には共産党が武装闘争路線を放棄し、再軍備の是非をめぐって分裂していた左派社会党と右派社会党が合体して日本社会党が結成された。さらにその一ヵ月後、日本社会党結成の動きに対抗して、自由党と民主党が保守合同して自由民主党を結成した。いわゆるその後の日本政治において約40年間続く「55年体制」が出来上がったのである。
小熊英二は『民主と愛国』の中で、「それは、一つの『戦後』の終わりであり、もう一つの『戦後』の始まりであった。共産党の武装闘争放棄に象徴されるように、革命と闇市に象徴される激動の『戦後』は、敗戦後10年で終わりを迎えていた、それに代わって、高度成長と『55年体制』に象徴される、安定と繁栄の『戦後』が始まろうとしていたのである」と述べている。
それに伴って日本人の生活環境も著しく変化した。冷蔵庫・電気釜・洗濯機などを総称する「三種の神器」という言葉が登場したのも1955年である。1958年にはインスタントラーメンと中性洗剤が発売され、1959年には国産初の普通乗用車が発売された。また1957年にはテレビ普及台数が100万台を超え、1962年には1000万台を超える爆発的な伸びを示している。さらにこの時期を境に農村から都市への人口移動、それに伴う農業人口の減少が始まった。まさに日本が近代を脱する萌芽の時代であったのではないだろうか。言い換えればそれは、日本の自画像の転機であり、「繁栄のアジア」の起源であったと言えるのではないだろうか。
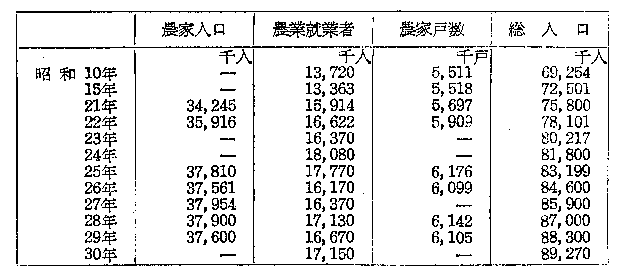 |
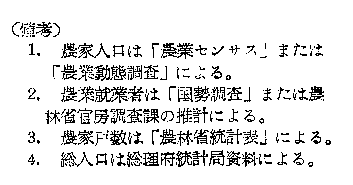 |
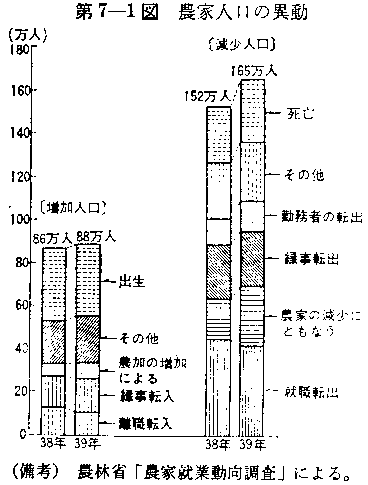 |
| 経済白書データベースより引用。 |
4. 1964年社会転換説-松本健一「竹内好『日本のアジア主義』精読」
高度成長時代を迎えて、日本の社会の構造転換がなされたのは1964年であるとする論者がいる。「竹内好『日本のアジア主義』精読」を著した松本健一である。松本は自著『谷川雁 革命伝説-一度きりの夢』(河出書房新社、1997年6月)の中で次のように述べている。
「1964(昭和39)年というのは、改めて指摘するまでもなく、東京オリンピックの行われた年である。それは、アジアで最初のオリンピックとよばれた。だが、このオリンピックは日本が明治以来ひたすら欧米化の道筋を歩むことによって成し遂げられたものであってみれば、明治以来の近代日本を挟み撃ちにしてきた『ヨーロッパ 対 アジア』という対立構図も、そこでは意味を喪失していた。とすれば、この『ヨーロッパ 対 アジア』の暗黙の前提のうえに立って提起されていた『東洋の村の入り口で』とか、『日本の民衆の夢とは何か。それはアジアの諸民族とおなじく法三章の自治、平和な桃源境、安息の浄土であります』といったような表現が意味不明になり、急速に色褪せてゆかざるをえない。1990年代の現在、二十歳前後のアジアのイメージを問えば、『経済発展』とか『ビジネス・チャンスの場』という答えが返ってくるだろう」
松本の論を借りて、言葉を変えれば、1964年は日本が「アジア」ではなくなった最初の年であった。そしてアジアの近代化とは、「アジアがアジアでなくなることの百年の過程であった」という。日本がその近代化イコール欧米化百年の最終過程を迎えたのが、1964年であったのだ。
1960年代は短期的に見ると、先の大戦の米ソ冷戦下における日本の高度経済成長がはじまり、日本がいわゆる「戦後」を脱していた時期であったといえる。しかし長期的にみるならば、日本の百年におよぶ近代化(脱亜入欧)の過程が終わり、「近代日本」という歴史パラダイムを脱していった時期だった。松本はその転換点の指標を、「いま具体的な年号でいえば、それが東京オリンピックに象徴される1964年だったろう」と述べている。そして「近代日本」というパラダイムが意味するものとは、日本が遅れたアジアから脱しつつ西洋近代化を後ろから追いかける「脱亜入欧」という構図によって成り立っていた社会のことであり、それが大きく転換したのが1964年であったというのだ。
さらに松本健一は1979年に朝日新聞のエッセーでつぎのように書いている。
「この十数年間における社会の変貌は、ちょっと言葉ではいいあらわしにくいほど急激である。テレビや冷蔵庫や自動車などがもうずっと以前からそこにあるように家庭におさまり、高層建築や歩道橋や高速道路やハウス栽培のためのビニール室も見慣れた光景になった。ニュータウン、ニューファミリー、ニューミュージック、ニュージャーナリズムといったような、頭にニューのついた社会現象、文化現象も、この十数年間の社会的変貌によって生み出されたものにほかならない。ところで、この社会的変貌は、1964年(昭和39年)あたりからはじまっているようにおもわれるが、どうだろう。なぜ、なぜ1964年にその指標をおくか、といえば、この年に東京オリンピック、新幹線、ビートルズなどの新現象というか新事態が、わがくにに出現しているからだ。そしてそれらは、たんに新現象、新事態なのではなくて、社会の構造上の変化そのものを表象しているような気が、わたしにはする。」
「この1964年を指標とした社会の構造上の変化は、ある意味で、1945年8月15日の前と後での変化よりも、はるかに大きかったのではないか。たしかに、八・一五の前と後では、表面上のファイシズム体制から戦後民主主義体制へ、といった政治体制的な意味での変化はあったろう。しかし社会的な構造においては、ファシズム体制も戦後民主主義体制もともに『近代日本』という枠組みによって支えられていたのだ。『近代日本』とは、日本が遅れたアジアから脱しつつ西欧近代を後ろから追いかけるという構図によって成り立った社会のことである。」
1964年の転換は、1945年8月15日の変化よりも社会構造上においては重視すべきであり、「近代日本」という歴史パラダイムが終わったというのだ。これが松本健一の「1964年社会転換説」である。それでは1964年に転換した以後の日本はどのようなものであったのだろうか。松本健一は続けて次のように書いている。
「これに対して、1964年以後のわが国は、その『近代日本』の枠組みをはずして、西欧と横一線の『近代そのもの』に到達したとみてよいのではないか。いや、それどころか、公害といった現象にも明らかなごとく、わがくにはきわめて急速な近代化によって、西欧に先立って『近代の末路』を突き出した感さえなくはない。」
「この年あたりから、わがくには「近代日本」といった過去百年の基本的な枠組みから脱し、欧米近代と横一線にならびはじめた、とおもわれる。そしてそこでは、かつての『近代日本』といった枠組みの内部で成立していた、さまざまな対立構図、アジア対西欧、中央対地方、ムラ対都市、演歌対ポピュラー音楽、純文学対大衆文学、右翼対左翼、知識人対大衆・・・などが意味を喪失しはじめた。これ以後の、ベトナム反戦運動、学生反乱、石油ショック、原子力発電をめぐる対立、ニューミュージック、ニュージャーナリズムなど様々な社会現象は、かつての『近代日本』おける対立構図において理解するよりも、むしろ世界的共時性において理解したほうが、より分かりやすいのである。」
つまり、これらのことを本稿で述べてきた論旨に置き換えると、1964年を境にして、これまで本稿で述べてきた「欧米に対するアジア」という自画像は、日本においては終焉を迎えたということができる。戦後の「喪失したアジア」にならざるをえなかった状況が、社会的な構造変化によって自らの自画像を転換させたのである。
5. 結論
本稿では、かつてのアジアのイメージであった「停滞」や「貧困」、「専制(独裁)」というものが、いまや「発展」「繁栄」「民主化」に転換したという事実を踏まえ、その転換点はいつだったのかを検討してきた。
また検討のためには、日本自身の転換だけでなく、国際環境の変化や現時点で行われている東アジア共同体に向けた動きも考慮に入れなければならないが、まず日本自身の転換点をいくつかの事例や文献に書かれているものを紹介してきた。
日本の転換点をあげる前に、そもそも近代日本の歴史パラダイムの起源を探ることからはじめたのが本稿の第2節である。そもそも「アジア」という言葉は、西洋からもたらされたものであった。それだけに当初、日本の知識人は「日本はアジアの一部」であることに違和感をもっていた。その「アジア」の中に日本が自画像を見出し始めたのが19世紀後半以降であり、その時期から「欧米に対するアジア」という近代日本の歴史パラダイムがはじまったのではないかということを検討した。
「欧米に対するアジア」はいつ終焉を迎え、発展や繁栄をイメージする「新しいアジア」へといつ転換したのかということに関し、日本自身の自画像の転換の起源を探ったのが第3節である。1956年の経済白書に「もはや戦後ではない」と謳われ、人々の生活も向上してきたこの時期は、小熊英二の言うように、「一つの『戦後』の終わりであり、もう一つの『戦後』の始まりであった。高度成長と『55年体制』に象徴される、安定と繁栄の『戦後』」がまさにはじまろうとしていたのである。言い換えればそれは、日本の自画像の転機であり、「繁栄のアジア」の起源であったのではないかということを述べた。
次に第4節において、松本健一の「1964年社会転換説」を紹介し、1964年を境にして、「欧米に対するアジア」という自画像は、日本においては完全に終焉を迎え、戦後の「喪失したアジア」にならざるをえなかった状況が、社会的な構造変化によって自らの自画像を転換させたことを述べてきた。
つまり、19世紀後半にはじまった日本の「欧米に対するアジア」という枠組みは、先の大戦という制度的な衝撃を乗り越えて、1956年前後を起源とした「繁栄のアジア」の自画像が芽生え、1964年前後に、転換期を迎えたと言うことができるのではないか。この日本の自画像は、その後のアジアに対する外交姿勢にも現れている。1965年には佐藤栄作内閣において韓国との国交を回復し、1973年には田中角栄内閣が中国との国交を回復、1977年には福田赳夫内閣が東南アジアへの「連帯」を表明するなど、日本の対米自主を模索するアジア外交が展開された時期でもあった。
ここに次の検討課題がでてくる。それは、日本自身の自画像の転換が図られたとしても、それは日本自身の「繁栄」に留まるものであり、「アジア」に向けた自画像ではなかったことである。日本のアジア像が真に「繁栄のアジア」として認識し、「未来のアジア像」を展望するのには、もう少し歴史の時間軸を先に延ばす必要がでてくる。
前文教大学教授で、現在は思想評論家の立川健二が『ポストナショナリズムの精神』(現代書館、2000年3月)に、松本健一の「1964年社会転換説」を引用して次のように述べている。
「松本健一は・・・1964年前後の日本社会の変化が大東亜戦争の敗戦の前後のそれよりも根底的であると指摘するが、それは、言葉をかえれば、日本が『アジア』から『ヨーロッパ』に変貌をとげたということにほかならなかった。1979年という時点で提出されたこのような指摘は、驚くべき直観に裏付けられている、と言うほかはない。しかしながら、わたしたちは、これ以後、歴史の頁がさらにめくられ、新たな世代が成人として台頭してくる段階にいたったという事態に眼を閉ざすわけにはいかないのだ」
つまり、松本健一の「1964年社会転換説」は驚くべき直観によって裏付けられた真理であるものの、立川は現代の社会はさらに頁がめくれられていると述べているのだ。それは日本が自画像として描いていた「繁栄」が、1980年代末には、NIES(新興工業経済地域)として注目された、韓国や台湾、香港、シンガポールの「四つの小竜」の興隆によって「アジアの奇跡」を具現化し、アジア自身の自画像が変化したことを意味している。20世紀末の1997年に、香港がイギリスから、1999年にはマカオがポルトガルから、中国へと返還されたことは、ヨーロッパのアジア侵略の歴史が終わったことを象徴している。
次回稿では、それらの前提を踏まえた上で、日本の東アジア外交や多国間の枠組み形成の過程を整理し、特に「東アジア共同体」の形成に向けた議論から「新しいアジア」を模索していく。
【参考文献】
松下幸之助『リーダーを志す君へ』(PHP研究所、1995年3月)
小熊英二『民主と愛国-戦後日本のナショナリズムと公共性』(新曜社、2003年10月)
丸山真男『現代政治の思想と行動』(未来社、1994年5月)
日本政治学会編『日本外交におけるアジア主義』(岩波書店、1998年)
日本政治学会編『危機の日本外交-70年代』(岩波書店、1997年)
国際政治学会編『日本外交の思想』(有斐閣、1982年8月)
国際政治学会編『環太平洋国際関係史』(有斐閣、1993年2月)
国際政治学会編『終戦外交と戦後構想』(有斐閣、1995年5月)
笠原一男『詳説日本史研究』(山川出版社、1965年10月)
木下康彦・木村靖二・吉田寅『詳説世界史研究』(山川出版社、1995年7月)
帝国書院編集部編『詳密世界史地図』(帝国書院、1994年3月)
松本健一『竹内好「日本のアジア主義」精読』(岩波書店、2000年6月)
松本健一『戦後世代の風景-1964年以後』(第三文明社、1980年1月)
「昭和31年度版経済白書」、経済白書データベース
外務省ホームページ
東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室ホームページ、
「データベース『世界と日本』」
松下電器株式会社ホームページ「松下幸之助の生涯」
http://panasonic.co.jp/company/person/life/cl_0097.html
小野貴樹の論考
Thesis
-
新しいアジア~日本の歴史観試論~(3) 近代日本の歴史パラダイムの転換
-
新しいアジア~日本の歴史観試論~(2) 喪失するアジア~ナショナルアイデンティティーの模索
-
新しいアジア ~日本の歴史観試論~ 序論 アジアの自画像-「欧米に対するアジア」
-
大事を成す為に必要な人間観
-
日中FTA・EPAの政治的インパクト ~21世紀の新しい日中関係~
-
100年前の戦争、その後100年の日本 ~日露戦争の教訓~
-
日本のビジョンを議論せよ!!~憲法前文の改正に向けて~
-
- 2004/1/29
- 法律・法制度
台湾総統選挙視察を前に
-
- 2003/11/28
- 外交・安全保障
対外援助の外交的意義
-
- 2003/10/29
- 思想・哲学
The former U.S. Secretary of States was an immigrant. ~Madeleine Korbel Albright~
-
- 2003/9/28
- 外交・安全保障
日本外交における地域概念
-
- 2003/7/29
- 思想・哲学
松下幸之助が伝えたかったこと ~松下政経塾と日本伝統精神の継承~
-
- 2003/6/28
- 思想・哲学
中国西部大開発の現状と課題 ~現場で見た西安・重慶経済発展の目に見える光と影~
-
- 2003/5/29
- 外交・安全保障
日本外交の要諦 ~「国力」を再検討し「国益」を見据えた外交を~
-
- 2003/4/28
- 思想・哲学
日本の国益を考える
Takaki Ono

第23期
小野 貴樹
おの・たかき
Mission
北東アジアスタンダードの構築に向けた日本の取り組み