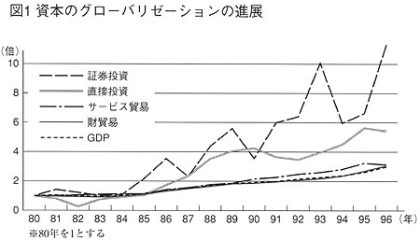Thesis
闘う政治家達 ~英国デモクラシーの考察~
4月末に渡英以降、日本に一時帰国した1ヶ月を除くと、まだ英国滞在は2ヶ月とわずかではあるが、議会政治の本場である英国政治を見ると、度々日本の政治との違いを思い知らされることが多い。今回は、渡英以降に触れた英国政治や、6月一時帰国して携わった日本の国政選挙での経験を踏まえ、レポートをまとめてみたい。
巨大ファイル!?
さすが議会制度の本場を自負する英国だけあり、議会の会期中は一般向けに議会の傍聴席を常時開放している。またケーブルテレビでは、国営放送のBBCが常に国会中継専門の番組を放映している。
私も一度国会を訪れたがまず始めに驚かされたのが、会場の狭さである。我国の荘厳とも言うべき巨大な国会の風景と比べると、やや拍子抜けするような狭さであり、かつベンチ形式で座るところがあるだけで、机すらない。下院の定数659名に対し、座席は346人分しかないという。(これは聴いた話で確認資料はないが、かつて二次対戦で痛んだ議事堂を改装した際にも、時の首相チャーチルが、議会の熱気が拡散するのを避ける為、敢えて議場を拡大することを避けたと言う。)
毎週水曜日には、日本でも導入された首相に対する「クエスチョンタイム」(党首討論)が行われる。この狭い議場で、かつ与野党が向かい合って座ると言う状態で、党首討論は異常な熱気に包まれる。与野党ともに、党首の後ろから相手への攻撃に一丸となり、まさに言論による「合戦」の様相を呈する。
攻めるヘイグ保守党党首も、反撃するブレア首相も決して期待を裏切らない弁論で激論を交わす。期待以上・想像以上の激しさだ。しかし、一点想像と違う部分があった。双方ともに、全身を使い役者さながらに雄弁に語るが、いつも手元に巨大なファイルを抱えている。相手の弁論を聞きながら忙しなくファイルをめくり、またその大きなファイルを抱えて発言場所と自席を行ったり来たりする双方の姿は少し愛くるしい滑稽なものを感じる。その一点だけがあまりスマートではない。しかし、そのファイルの存在こそ日本の党首討論との本質的な違いを象徴しているように感じる。
英国のクエスチョンタイムでは、日本の党首討論のような概論的な話に終始することはなく、現実の数字にまで突っ込んだシビアな議論が展開される。
例えば犯罪率の上昇に関する議論においては、その統計の取り方にまで踏み込んで議論が行われるのであり、好い加減な記憶に基づいた議論など許されない。また当然代役やメモを差入れてくれる人もなく、討論者にとってはそのファイルだけが頼りなのだ。
かつてレーガン米大統領の側近が、「米国に導入したら大統領は死んでしまう」と言ったという厳しい環境の中で、英国政治の指導者たちはその能力と政策の是非を問われ続ける。その結果常に党首こそが党内切っての政策通として党をリードする体制が出来ている。クエスチョンタイムに耐えられないような人間は、如何に党内政治が巧みでもリーダーにはなれない。英国では、絶対に竹下首相や小渕首相は生まれない。ブレア首相が44歳、ヘイグ首相が37歳という若さなのも頷ける。50・60代の人ではとても体力的にも精神的にも耐えられるものではないと思う。
国民皆激論!
この議論の激しさは、政治家だけのものではなく草の根レベルにまで浸透している。
先日、CPS(Centre for Policy Studies)という、右寄りのシンクタンク主催のディベートに参加した。「The Third Way」を掲げるブレアのイデオローグと言われる人物で、英国社会科学の最高峰の一つであるLSE(London School of Economics)の学長・左派の重鎮Anthony Giddens氏と、CPSの代表との討論だった。CPSの代表も、かつてはゴールドマンサックス欧州の代表やイングランド銀行の理事を務めたと言う大物同士の討論だ。
日本では、左右両巨頭の対談という考えにくい企画の上,ともに大物同士、社会的立場を有する人物同士の対談なので、ディベートと言っても、所詮は CPS代表によるギデンズ氏へのインタビューみたい温和なものとタカをくくっていたが、これが大間違いだった。
会場は、壇上の両端にそれぞれのスピーチコーナーが設けられ、真中には、司会を務める人物がタキシードに身を包んで陣取っている。ギデンズ氏の「サードウェイとは何か」という立論に続き、CPS代表によるポライトながらも痛烈な反論、そして再びギデンズ氏の発言の後は、会場からの質問を呼び水に様々な角度から議論が続けられた。
サードウェイというと、日本では、市場(原理)主義というパラダイムとの関係でのみ論じられ、「市場主義vs反市場主義」というやや観念的な図式に凝り固まってきているが、この討論では、それぞれが「市場をどのように利用するか」、という英国人らしい現実主義的な前提を共有した上で、「市民社会の在り方」(家族や学校という伝統的な制度とNGO
POのどちらを優先すべきか)や、「政府と市場の関係のあり方」(富を創造する市場を如何にうまく活用するか)と言った、より一歩踏み込んだ議論が行われていた。
そして更に驚かされたのがディベートの激しさにも負けない、質問時間における聴衆の積極的な姿勢だ。多くの(ほとんどと言うべきか)聴衆が我こそは手を上げ、堂々と自分の意見を述べてディベーターである両巨頭に挑む姿は圧巻だ。この国のデモクラシーの厚みを感じさせられると共に、これこそが、塾主松下幸之助が塾生にその必要性を説いた「衆知を集める」ということだと実感させられた。
激論・競争・闘い、どう言っても構わないが、とにかく英国では、そう言った激しい環境の中、妥協を廃し徹底的に議論するという風土から、多くの知恵が生まれてきているのを感じる。
翻って我国の現状を見るとその散々たる状況に愕然とする。6月の衆議院選挙の際は一旦帰国し幾つかの選挙区でそれぞれの選挙を実地で観察した。またテレビでの政治家間の議論等も多く見たが、その議論の中身の無さ・甘さに失望した。
今回の選挙の争点の第一はおそらく不況対策であったと思う。
多くの政治家がそれに言及しつつも、公約は、「不況対策」の一言。小学生でも「不況脱出のために自分は、不況対策をします」、くらいのことは言える。本来であれば、現在の日本の不況の原因は何か、そしてそれに対し如何なる処方箋が必要か、という議論が為されるべきである。しかし、そこまで言及していた政治家は、少数の候補者を除いて、見当たらなかったように思う。
これはある衆院選候補者にインタビューした際に話したことであるが、不況対策と財政再建がさも議論の論点であるかのように語られ、不況対策VS財政再建派のような構図が出来ている。
しかし、不況対策も財政再建も、共にすぐに取りかかるべき課題であり、どちらを優先してどちらを後回しにすれば良いと言った単純な問題ではない。その双方をどういうビジョンの中で同時に取り組んでいくのか、ということこそが重要なテーマであるはずであり、政治家はそのビジョンで持って競い会うべきである。しかし現状は不況対策・公共投資派VS財政再建・公共投資反対派とも言うべき安易で無意味な構図に陥っている。
さらに言えば、日本の政治家の場合、選挙で不況対策をいうだけでも立派な部類に入るのかもしれない。地方の候補者は、地元対策ばかりを有権者に訴えている。
都市部の候補者は、国会議員の仕事は、地元への利益誘導ではなく国政をすることだ、ともっともなことを言う人が増えてきたが、ではその「国政」の中身は?となるとトタンに心もとない。塾のOBにも多いので残念だが、首相公選制とか政治資金の規制とか、制度論ばかりを口にするばかりで、一体どういう方針・政策で国家を運営するのか、という中身の話が見えてこない。中身の話にならないので、有権者としても議論に参加するインセンティブが沸いてこないのではないか。極端なことを言えば、政治制度がどうなろうと国民には直接関係ないことであり、重要なのは、国民の生活がどう変わるのか、ということだと思う。そういう視点から見れば、「自分たちの手で首相を選ぶ」とか「政治資金の規制」云々の議論は、簡単なので話し易いのだが、国民には関係のない話なのだ。「不況の原因はこういうことで、だから私達はここを変えねばならない、そして私達の生活はこう変わる」ということこそが重要なハズだ。もちろん制度論は無意味ではないし、社会変革のためには制度改革は当然必要だ。私自身首相公選制も必要だと考えている。しかし、日本の政治の議論の仕方に対する疑問として以上のように考える。
もちろん、日本のデモクラシーの貧困を政治家のせいだけにするべきではない。ある銀行経営者の言葉だが、「国民のレベルを越える政治家など生まれない」と言う。鳶は鷹を生まないのだ。選挙の投票率では一概に判断できないということは承知しているが、英国では下院選挙の投票率が戦後72%を下回ったことはないという。翻って我国今回の選挙の投票率はわずか65%に過ぎない。それも、10年近くもほぼ実質経済成長ゼロを記録し、失業率は上がりつづけ、国家財政は破綻しかかっているという状況にも関らずである。
今回の日本の選挙結果を見てこちらの新聞は、「10年以上も不況脱出に失敗し続ける政党が簡単に信任されるということが理解できない」と言う。普通の国でこれだけ散々足る状況を続ければ、時にはクーデターも起こりうる。多発する少年犯罪は、少年法の不備などと言う表層的な問題ではなく、潜在的なクーデターにもつながり得る社会的不満の表れではないのか。彼らの短い人生は、ほぼ「失われた10年」に符合する。森首相個人よりも、この散々たる状況でも「寝ている」国民・大人の有権者こそが、我国の問題だと感じる。我国にはデモクラシーはない。それは、与えられていないのではなく、単に放棄しているのだが。
政治家の説明責任
話がやや脱線したので元に戻す。
先に述べたことから、私は、英国のデモクラシーの優れた点を主に、「議論による競争」と「多くの人間が参加する開かれた議論」の2点にあると考える。しかし、この2点は、ともに同時にデモクラシーの問題点とも直結すると多くの論者から指摘されるものだ。
まず、後者の「多くの人間が参加する開かれた議論」だが、特に外交政策等微妙な問題においては、国民世論は安易な感情的な方向に流れガチで現実的な選択を妨げる危険があるという指摘がある。過去の歴史を見ても、ほぼ全ての戦争において、国民世論は基本的に戦争突入を支持し、最前線の情報に触れている政策担当者達の現実的判断を押し流してきた。今回の中東和平交渉においても、キャンプデービットで妥結へ向けて現実的に解決策を模索する指導者達とは対照的に、彼らの祖国の国民は激昂し妥結を拒否していた。
また現在英国が直面する問題としては、英国のユーロ加盟問題が挙げられる。政府は、長期的観点からは、ユーロ加盟なくして英国の経済的発展はありえずユーロ加盟は避けられないのであるのだから、それならば出来るだけ早期に加入して、加盟国間において英国の意思をなるべく強く反映できる指導的ポジションを確保すべき、という立場を取っている。
しかし、欧州大陸に対する不信、特に仏独主導体制への不信や通貨政策の自主権の確保と言ったナショナリスティックなやや非合理な観点から(もちろん他にも幾つかの理由があるのではあるが)、国民のユーロ参加反対は70%にも達し、リベラルな立場からユーロ参加の国民投票を公約にしてしまった現政権は完全にこの問題に関しては行き詰まっている。ゆえに多くの国民が参加する議論が必ずしも正しい政策を産むとは限らないのではないかと感じる。
先日、ブレアの最も若きブレインと言われ、労働党系政策シンクタンク「Foreign Policy Centre」の代表を務めるMark Leonard氏にこの質問をぶつけた。彼は、ブレア労働党の政策を支持するためだけではなく、自身も「ストリート外交(政策)」を掲げ、国民参加型の外交の在り方を提唱している。
彼は私の質問に対し、ストリート外交において最も重要なのは、政治家の説明責任だと答える。ユーロ加盟問題に関してもブレア首相が、国民を説得できることを信じていると言う。リーダーと国民の対話から正しい答えが生み出されるはずだという信念こそ、デモクラシーに最も必要なものかもしれない。
デモクラシーもしくは、ストリート外交とは、決して単純に国民の意思を政治に反映させる、ということではない。政治家と国民の対話から、よりよき方向・方策を模索するのがデモクラシーの意義であり、それには、政治家が国民と対話する姿勢と、十分に政策を説明できる能力が必要なのである。
ではもう一つ、「議論による競争」に関してはどうか。
この効用に関しては、小選挙区制導入前後から日本でも二大政党制を論じる際等に言及されてきた。しかし、逆にこの問題点としては、議論による競争は、時には相手を打ち負かすためだけの詭弁を生んだり、もしくは国民に膾炙されやすい迎合的な安易な政策を産みガチだという指摘がある。
先の例と全く同様の例を使うが、歴史上、多くの国が戦争に向かう過程で、常に現実的に穏健路線を模索し戦争を回避しようとする政府・与党に対し、野党は与党との競走のため、人口に膾炙しやすい強硬路線を主張し戦争に突入してしまったという事例が多い。また、英国のユーロ加盟問題においても、野党保守党は、与党労働党との争点作りのために政治的な党略から敢えて強硬な反対論を展開しこの問題を深刻化させている。
このような場合、国家の未来に多大な影響を及ぼす政策(特に外交政策)に関しては、政治家の良識に基づく超党派の話会い等特別の措置が必要になるのであろう。事実、英国のユーロ加盟問題に関しても、ユーロ加盟に反対の立場を取る保守党の中からもユーロ加盟賛成を主張する党の重鎮・No,2クラスが参加して与党労働党・第三政党の自由民主党のリーダー達と共にユーロ加盟促進のためのキャンペーンを行っている。
デモクラシーの自動成熟機能
激しい議論は、時には相手を打ち負かす為だけの詭弁を生み、よりよきアイディアを求めるといった議論の本来的意義が失われることは良くある。特に政治に関する議論は、その性質上議論が党利党略から行われるゆえその傾向が顕著である。また開かれた国民参加型の議論は、時にエモーショナルな方向に流れがちで、現実的な判断を押し流す傾向がある。故にいつの時代にもデモクラシーに懐疑的な勢力はある一定の勢力を占め、デモクラシーの弊害を是正する機能を果たす。
よって、デモクラシーの浸透具合により一概に国家の先進性を判断しうるものではないことは重々承知しているが、英国の政治シーンを見ると、どうしても日本政治の後進性を意識せざるをえない。
先に述べたように、私自身、単に国民の意思を多く政治に反映することが良いデモクラシーだとは考えていないし、英国政治がより国民の意思を反映しているか、となると確かに表層的な部分では政党のキャンペーンの巧さなどからそう感じることも多いが、実際のところはよくわからない。では何が違うのか。
私はそれを、デモクラシーの自動成熟機能と呼びたい。
先に私は、英国政治の優れた点を、議論による競争と、そこで求められる政治家の説明責任に求めた。政治家には、常に、自分の政策を国民に対し、議会の議論の場で説明する義務があると考えられる。オックスフォード大学ディビット・バトラー博士は、「英国のデモクラシーの基本原則は、首相、閣僚、官僚の活動はすべて議会に説明できるものでなくてはならないということ。クエスチョンタイムでは、政府の説明責任が問われる」と言う。
では、何故説明責任があるのか、もしくは重要なのか。日本ではこれが単なる政治家の国民への義務だから、と言った説明や、政治への国民の監視・チェックのため、などと説明されている。
しかし、私は政治家の説明責任が重要である最も根本の理由は、別にあると考える。それが、デモクラシーの自動成熟機能だ。
政治家が常に説明責任を要求される以上、常に政府の政策は、その根拠や現状認識を巡り検証が加えられる。反対陣営からの攻撃は時には的外れなものも多かろうが、的外れな攻撃を野党が行った場合、その攻撃にも「説明責任」があるのであり、その攻撃の根拠・現状認識を明らかにする必要がある。そしてその根拠・現状認識は、一時的なものとは見なされず、その政党の公式見解と見なされ、仮にその政党が政権に復帰した場合(二大政党制の英国では常にこのパターンが繰り返されているのだが)、その政権の政策は、野党時代の言動からもその整合性が問われる。日本の政治家のように好い加減なことは決して言えない。
英国の各政党は、相手政党の公約や幹部の発言を二次対戦前まで遡ってデータベース化し、簡単な検索語で即座に引き出せるような体制を整えている。選挙期間中には、政策論争のためのスタッフをそれぞれの党が100名前後集める。
その結果、政権運営のソフトウエアとも言うべきノウハウの蓄積が進む。
例えば、英国の場合、常に欧州政策を中心とする外交政策が一つの大きな論点となってきた。与党との競合上、野党はどうしても現状に対し批判的にならざるをえず、現実的な与党の親欧州政策に対して反欧州政策を展開する。そのため政党の政策は、常に変化しているが(この点は同時に英国デモクラシーの大きな問題点であるのであるが)、変化する度に、その理由として現状認識の変化等を明確にする。そう言った議論のくり返しから自然に、英国の外交政策を巡る議論は厚みを増す。
政策が失敗した場合には、自動的にその根拠としていた現状認識や理念が間違っていたことが明白になるのでその政党は改めてその再検証に迫られより良きものを生み出すことになる。
先月の月例報告でブレアの欧州政策について少し触れたが、ユーロ加盟問題を語るブレアの議論は、常に戦後の英国の欧州政策を歴史的視点から総括した上で語られる。そこには、当然過去誤った決定を下した当時の政権への批判が加えられ、時には自党のアピールに終始することもあるが、国民にとってもいれば、政策判断を、一時的な感情論ではなく多くの国民も共有する歴史的経緯から説明されるので、より深く考えて判断を下すことが出来る。
翻って日本の政策運営の現状を、この「説明責任」という観点から見ると散々たる状態にある。5・6月の月例報告において我国の外交方針の転換について述べたが、官僚達が高らかにその転換を宣言しているにも関らず、議会での議論は一切ない。現在の不況の原因となったバブル経済に関しても、その原因すら未だに総括されることはなく、私は、その原因は未だに放置されたままだと認識している。
最近話題のゼロ金利政策の解除問題に関しても、ゼロ金利政策が採用された当時の議論はすっかり忘れ去られ、緊急避難的一時的要素の強かった当時の認識は消え去り、ひたすら景気対策の視点ばかりで議論されてしまっていることに疑問を感じる。
英国でも為替と金利の問題は、大きな問題となっているが、97年に政権奪取後、中央銀行を独立させ、為替政策と金融政策のそれぞれの自律性を確立した現政権のビジョンは明確である。仮にこの政策が失敗すれば、その方針を見直せばよいということになり、日本のように、何故政策が失敗したのかその理由すらよくわからないゆえに改革の必要性が認識できず、いつまでも失敗の原因が放置されるというようなことは起こり得ない。デモクラシーにとって最も恐ろしいことは、判断を誤ることではなく、判断を誤ったときにその失敗から学ぶことからよりより政策運営を目指す、ということが出来ないことだと思う。
デモクラシーも他の統治形態に比べ非常に責任の所在が不明確になりがちだが、政治家の説明責任がその所在を明確にすることが出来る。
以上を最後に整理する。英国のデモクラシーの優れた点は、活発な議論による激しい競争と、多くの国民が参加する開かれた議論にあると考える。その双方の根本を担うのが、政治家の説明責任であり、政治家の説明責任原則が確立されているため、政策立案のノウハウの蓄積等が進み、自動的に政治の成熟化が進む。
この英国政治に比して、日本政治の現状は到底デモクラシーと呼べるようなシロモノではない。小選挙区制の導入やクエスチョンタイムの導入など、日本でも多くの英国を範とした政治制度改革が取り入れられてきているが、私の言う「デモクラシーの自動成熟化機能」は日本では到底機能するような状態ではない。それは何故か。表層的な形だけを導入し、トータルな制度を支える理念や原理がナイガシロにされているからではないか。導入すべき原理は、2つ。何度も重なるが、活発な議論による激しい競争と、多くの国民が参加する開かれた議論である。それを踏まえ政治家は、自らの政策説明責任を認識するべきである。
具体的には、政治の現場の入り口から変えて行く事だと思う。出口、つまりは最終地点を変えることで政治の現場を変えていくというクエスチョンタイム導入等のアプローチも時には有効だが、やはり根本はその入り口を改革することだと考える。選挙の本選の前に予備選を実施して、政党候補者選定の過程に競争原理を導入すること、及び政党による候補者の公募を実施し、政治を多くの国民が参加できる可能性を確保すること、この2つがとりあえずの急務であろうと考える。
鈴木烈の論考
Thesis
-
- 2001/7/29
- 思想・哲学
はじめの一歩の前に
-
- 2001/5/29
- 法律・法制度
「改革」を考える②(参議院選挙奮戦記③)
-
- 2001/4/28
- 法律・法制度
「改革」を考える①(参議院選挙奮戦記②)
-
- 2001/2/26
- 思想・哲学
湘南改革者会議結果報告
-
アジア・太平洋で日本は再生する
-
- 2001/1/29
- 思想・哲学
湘南改革者会議の呼びかけ
-
- 2000/12/29
- 思想・哲学
「政治家になろう!!」~台湾編~
-
国内経済政策と国際経済政策の整合性
-
- 2000/10/29
- 思想・哲学
経過報告
-
- 2000/9/28
- 思想・哲学
誰のための政治か
-
- 2000/8/29
- 外交・安全保障
英国労働党党大会2000 参加記録
-
- 2000/7/29
- 思想・哲学
東行会の試み
-
- 2000/6/28
- 思想・哲学
闘う政治家達 ~英国デモクラシーの考察~
-
- 2000/5/29
- 外交・安全保障
日本外交の転換点②
-
- 2000/4/28
- 外交・安全保障
日本外交の転換点①
-
- 2000/3/29
- 思想・哲学
グローバリゼーションに関する考察
Retsu Suzuki

第20期
鈴木 烈
すずき・れつ
八千代投資株式会社代表取締役/株式会社一個人出版代表取締役